はじめに
本記事は、小学館から発売された『逆境に克つ力 親ガチャを乗り越える哲学』の著書・立命館大学教授の宮口幸治先生にインタビューをおこなった内容を記事化したものです。取材は2024年3月25日に行いました。
近年、SNSの発達により家庭の様子が見えやすくなり、よその家と自分の家を比べる機会が増えました。その影響もあり、「親ガチャ」に関する議論や本を目にする機会は多くあります。しかし、よくよく考えてみると「親ガチャを乗り越える方法」についての議論はなかなかされていないように感じます。
では、「親ガチャを乗り越えるためにできること」とはいったい何なのでしょうか?
困難を乗り越える姿を見せる
子どもの家庭環境を少しでも良くするために教員に何ができるのでしょうか?
そもそも、大前提として教員が子どもの家庭環境を良くしようと首を突っ込んでしまうことは危険なことです。
※ただし虐待など危険な状態であると判断できる場合には、まずは校長先生など管理職に相談し、学校全体でのケースカンファレンス(問題となっている事項について検討すること)等を行う、児童相談所に繋げるなどが必要となります。
教員は、子どもの家庭環境を良くしようとしたり、家庭環境による悩みを減らそうとしたりするのではなく、大人として「困難を乗り越えていく姿」を見せることが大切です。つまり、子どもたちにとってのよい「モデル」となるということです。

跳び箱の跳び方がわからない子どもに跳び方を口頭で教えても、跳ぶことはなかなかできません。子どもはお手本となる「モデル」を見ることによって、跳び箱の跳び方をイメージし、跳べるようになるのです。これと同じように、普段から先生ら大人が身近な「モデル」となって困難を乗り越える姿を見せることで、子どもたちは困難に直面したときに、乗り越えるためのイメージができるでしょう。
また、困難を乗り越える姿を知るという意味で、偉人の「伝記」は役立ちます。近くにモデルとなる大人がいなくても、偉人が苦難を乗り越えてきた姿から生き方を学び取ることができます。

子ども自身に「気づかせる」
先生が逆境を乗り越える「モデル」となるということが大切だとおっしゃっていましたが、子どもたちが逆境を乗り越える力をつけるために、ほかにも先生にできることはありますか?
そのほかに必要なことを挙げると、「子どもたち自身に気づかせる」ということです。つい、「子どもたちの世話をしてあげよう!」「子どもたちに教えてあげよう!」と考えてしまいがちですが、それは必ずしも子どもたちにとってよい効果を生み出すとは限りません。先生は全てを教えるのではなく、「子ども自身が自分で気づく力をつけさせる」ことが大切なのです。
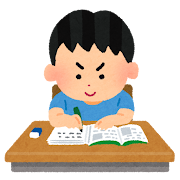
また、子どもたちには誰かの「世話をする」経験も大切です。特に、普段から世話をされる側の子どもたちにとっては、誰かの世話をして感謝されたい気持ちがあります。ただ同級生の世話をする機会はなかなかないので、自分よりも低学年の子どもたちの世話もいいでしょう。そのような経験の機会を学校で作ってあげることで、子どもたちは人の役に立ったと感じることができ、成長できるのです。

今後の学校教育とは?
これからの学校教育についてのお考えをお聞かせください。
私は学校教育には、①学習面、②社会面、③身体面の3方面からの包括的支援が必要だと考えています。
今の学校教育を思い浮かべてみると、①学習面は、教科学習は通してしっかりとなされていますが、その土台となる認知機能面の系統的な支援はほとんどなされていないと感じます。②社会面と③身体面はどうでしょうか?
②社会面は、今の道徳教育だけではやはり十分とは言えないでしょう。③身体面にしても、身体を動かすことが苦手な身体的に不器用な子どもたちに向けての、体育の特別支援教育のような取り組みが必要だと考えます。それぞれ注1「コグトレ」などを行って、学習の土台、感情のコントロール方法、うまい身体の使い方などを整える必要があると考えます。
注1 コグトレとは、社会面、学習面、身体面の3方面から子どもたちを支援する包括的プログラム。
みんなの教育技術,【宮口幸治先生インタビュー】 コグトレで子供の学力の土台となる力を鍛えよう,2022 (https://kyoiku.sho.jp/139487/)
頑張る先生へのメッセージ
最後に、先生方に伝えたいことを教えてください。
私自身、小学校のときに先生から言われたひとことが何か迷ったときの一つの判断指標になっています。先生の一言は非常に大きな影響力を持っています。日本の将来を担う子どもたちを支えるのは現場の先生たちです。
プロフィール
宮口幸治 みやぐちこうじ

立命館大学教授・児童精神科医 一般社団法人日本COG-TR学会代表理事
京都大学工学部を卒業し建設コンサルタント会社に勤務後、神戸大学医学部を卒業。児童精神科医として精神科病院や医療少年院等に勤務、2016年より現職。困っている子どもたちの支援を行う「日本COG-TR学会」を主宰。医学博士、子どものこころ専門医、日本精神神経学会精神科専門医、臨床心理士。著書『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)が大ベストセラーになる。
プロフィールは以下サイトの引用です。
(https://kyoiku.sho.jp/294278/)
※2024年6月時点のものです。
『逆境に克つ力 親ガチャを乗り越える哲学』についての詳細はこちらから↓
(https://www.shogakukan.co.jp/books/09825446)
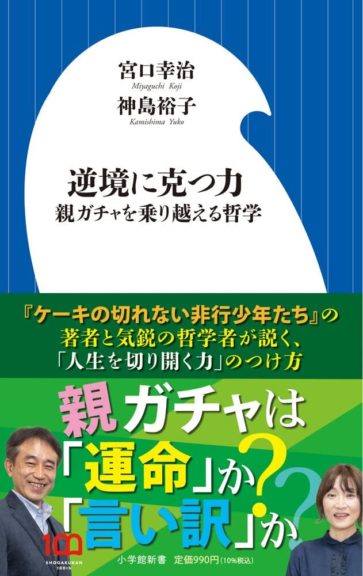
編集後記
教員が子どもの家庭問題を解決しよう・なんでも教えてあげようとするのではなく、モデルとなる姿勢を示すことが大切だと分かり、自分自身にとっても大きな学びのある取材となりました。取材にご協力してくださった宮口先生・小学館の阿部さまに感謝申し上げます。
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 森田 陽菜)









コメント