本単元で身に付けたい資質・能力
本単元では、読むことを通し、人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりする力を身に付ける。また、文章を読んでまとめた意見や感想を共有し、自分の考えを広げる力を養う。
単元の評価基準
知識・技能
- 比喩や反復など、表現の工夫に気づいている。
- 文章を音読したり朗読したりしている。
思考・判断・表現
- 「読むこと」において、人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりしている。
- 「読むこと」において、文章を読んでまとめた意見や感想を共有し、自分の考えを広げている。
主体的に学習に取り組む態度
- 意見や感想を共有し、学習の見通しをもって物語の魅力を伝え合おうとしている。
単元の展開【全5次(9時間)】
第1次(1時)物語を読み、第一次感想をもつ
① 物語と出会う。
(物語との出会い方の例)
- 舞台となった栗野岳や湧水町にある三日月池の写真を見る
- 「ガン」という鳥について知る
- 挿絵とともに、大造じいさんと残雪についてざっくりと知る など
② 物語を読む。
③ 感想を書き、発表する。
児童:「大造じいさんもなぜあのとき残雪をうたなかったのだろう。」
児童:「じいさんはただ残雪をつかまえたいだけじゃなくて、残雪たちと戦いたいと思っていると思う。」
引用:EDUPEDIA「大造じいさんとガン~1次感想を書こう」子どもたちの感想の一部(2025年3月5日)
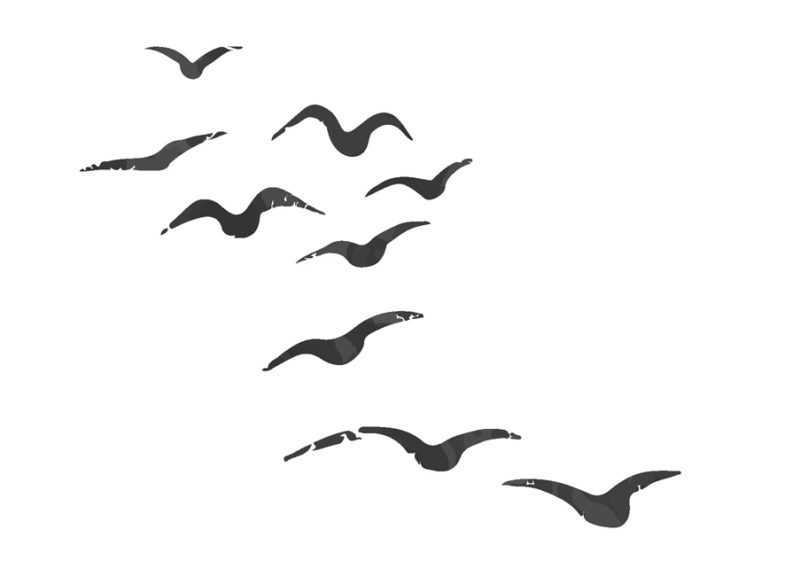
第2次(2~4時)作品の構造を読み解く
2時間目
① 意味が難しい言葉を書き出し、調べる。
(例)
- 感嘆
- りこう
- 会心のえみ など
② 物語の内容を大まかに書き出し、とらえる。

3時間目
③ 物語の「山場」を探る。
教師:「『山場』とは、物語の中で、中心となる人物の心情や、人物同士の関係が大きく変わるところです。」
(山場を見つけるポイント)
1. 読む人により強くアピールする書き方になっているところ
教師:「緊張感が高まるような言葉や文章を探してみましょう。」
(例)
- 「ぱっと、白い羽毛が、あかつきの空に光って散りました。」
- 「残雪です。」
- 「ぱっ ぱっ」
- 「羽が、白い花弁のように、すんだ空に飛び散りました。」など
2. 事件の流れが決定するところ
教師:「残雪は生き残ることができました。そうなることが決まった瞬間はどこでしょうか。」
4時間目
④ 事件の「発端」を探り、物語の仕掛けを見つける。
教師:「そもそも、物語は何をきっかけに始まったのでしょうか。」
→大造じいさんは、沼地を狩場にしていた。
→残雪が来るようになってから、一羽のガンも手に入れることができなくなった。
→かねて考えておいた特別な方法に取り掛かった。(作戦1)
⇒作戦1で捕まえたガンが、山場となる場面で活かされている。(2時間目の画像参照)
第3次(5~6時)物語の主題を探る
5時間目
① 登場人物の心情の変化をとらえる。
教師:「登場人物の気持ちや様子が分かる文章を抜き出してみましょう。」


教師:「物語のはじめと終わりで、登場人物の気持ちや様子に変化はありますか。」
(大造じいさんの心情の変化の例)
- 「あの小さい頭の中に、たいしたちえをもっているものだな」
- 「いまいましく思って」
↓ - 「おまえみたいなえらぶつを」「ガンの英雄よ。」
- 「いつまでも、いつまでも、見守っていました。」
(残雪の心情の変化の例)
- そもそも、残雪の心情が書かれていない。
- 残雪にとっては、「人間もハヤブサもありません」し、「ただ、救わねばならぬ仲間のすがたがあるだけ」。
⇒(例)大造じいさんにとって、残雪は腹立たしく、どこか小馬鹿にした存在だったが、物語のおわりでは、残雪の生きざまを誇らしく思い、「ただの鳥」ではない存在となった。
6時間目
② 物語の主題は何か追及する。
教師:「『大造じいさんとガン』のテーマは何だと思いますか。」
ここでのテーマ(主題)とは、
◯ 作品の総体から見えてくる「ものの見方・考え方」
× 作品を創作した生身の作家が込めた思い
である。よって、テーマは読者の数だけありうるため、決まった正答があるわけではない。
教師:「山場の前後で、何が、どう変わり、どう描かれていましたか。」
教師:「大造じいさんの気持ちには、どのような変化がありましたか。前回(5時間目)見つけた文章を振り返ってみましょう。」
(大造じいさんの残雪に対する心情の変化に着目した場合)
- 大造じいさんは、ハヤブサとの闘いで傷を負った状態にもかかわらず、残りの力を振り絞って堂々たる態度を見せる残雪の姿に強く心を打たれた。
- 「じいさんは、七十二さいだというのに、こしひとつ曲がっていない、元気な老かりゅうどでした。」
⇒(例)人間でも動物でも、誇りをもって生きる者の美しさについて表現されている。
第4次(7時)物語を再度読み、第二次感想をもつ
① 物語を読む。
② 第1次感想を読み、今の感想と違いがあるか確かめる。
教師:「物語を読み深めることで、初めの感想と変わったところはありますか。」
③ 物語の魅力はどこにあるかを考え、理由とともに書く。
教師:「自分自身の考えや思いが変わった点にも着目してみましょう。」
第5次(8~9時)本の帯やポップを作り、物語の魅力を伝える
8時間目
① 本の帯やポップを作る。
教師:「(帯を作る場合)表紙側に、物語の魅力が伝わるようなキャッチコピーを書きましょう。物語に出てくる印象的なセリフや文章でもよいです。

9時間目
② 交流する。
(交流例)
- 作った帯を読み合い、その感想を付箋に書いて、帯に貼り付ける。
- ポップを見せながら発表し、発表に対する感想を述べ合う。
おわりに
本授業は、国語科教育研究者の阿部昇が提唱する「物語の新三読法」と「物語・小説からクライマックスを見つける4つの指標」からヒントを得て構成した。
「新三読法」とは、①構造読み ②形象読み ③吟味読みの三段階で物語を深く読み解く指導方法である。本授業では、この方法を採用し、「大造じいさんとガン」の仕掛けや魅力に迫ることを目指す。
また、本作品のクライマックスを見つける手がかりとして、「物語・小説からクライマックスを見つける4つの指標」のうち2つを選び、児童にも理解しやすい表現に書き換えて提示している(第2次4時間目)。
「大造じいさんとガン」は、一度読むだけで多くの読者が何らかの感想を抱きやすい作品である。しかし、そのために表面的な理解にとどまり、浅い読みで終わってしまう児童もいると考えられる。そこで、本授業では段階的に読みを深めることで、初見の感想とは異なる視点を得られるよう促したい。
参考・引用図書
光村図書「こくご 五下」
吉永紀子「物語・小説『読み』の授業のための教材研究―『言葉による見方・考え方』を鍛える教材の探求―」日本教育方法学会紀要「教育方法学研究」第45巻、2019年度
参考・引用URL
参考:光村図書「年間指導計画・評価計画資料」(2025年3月6日)
https://assets.mitsumura-tosho.co.jp/9417/1031/3731/06s_k_nenkei5_03.pdf
参考:国語ノート「物語・小説から『クライマックス』を見つける4つの指標」(2025年3月5日)https://kokugonote.com/climax/
参考:国語ノート「物語・小説を『読む力』を育てる指導方法―物語の新三読法[1]はじめに」(2025年3月5日)https://kokugonote.com/monogatari_shin3doku01/
引用:EDUPEDIA「大造じいさんとガン~1次感想を書こう」子どもたちの感想の一部(2025年3月5日)https://edupedia.jp/archives/13879
執筆者
MUKOせんせい
元小学校教諭としての経験を活かし、中学・高校でも講師として教壇に立つこと多数。現在は、子育てに奮闘しながら、現場で働く先生方をサポートするウェブライターとして活動中。






コメント