1 はじめに
本記事は、『ともはる先生の学級づくり ~思いを正確に伝える技術を磨こう~(第3回EDUPEDIA SCHOOL)』の内容を記事化したものです。
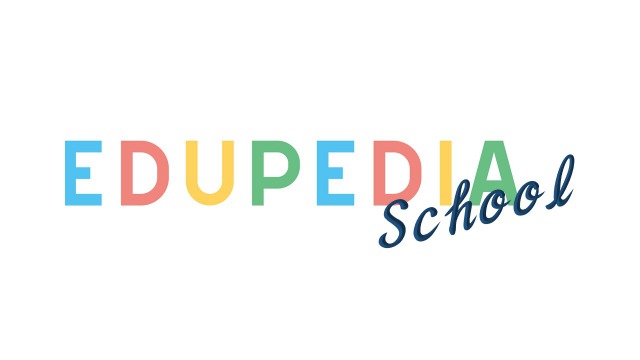
2 EDUPEDIA SCHOOLとは
EDUPEDIA SCHOOLとは、当サイトに掲載されている実践案を参加者の皆様に直接提供するための場として、EDUPEDIAスタッフが運営しているセミナーです。取材先の先生方の講演やワークショップ等を通じて、教育実践ノウハウを参加者のみなさまに提供することを目的としています。
第3回は、元小学校教諭のともはる先生(本名:前田智行先生)を講師にお招きし、特別支援の知識を生かしたユニバーサルデザイン学級の作り方というテーマでご講演頂きました。プログラム中は参加者同士で話し合う機会も多く、非常に盛り上がったセミナーとなりました。参加者には現職教員をはじめ、教員志望の学生など様々な参加者の方がいらっしゃいました。
過去のEDUPEDIA SCHOOLの記事がございますのでこちらも併せてご覧ください。
第2回 子どもの「どうして?」で授業をデザイン~子どもがワクワクする授業の条件とは~(千葉教生先生)
3 講演内容
○アメリカと日本の学級経営の違いとは?
ともはる先生:アメリカの学級では他者との関係性が低く、自己決定権を大事にします。一方、現在の日本では多様性が低いので、社会性の向上を目指していくべきです。近年、子どもの多様性が増してきました。そのため、子どもの社会性を上げるインクルーシブ教育の現場では、多様性を包括する取り組みが、現在進められています。
したがって、社会性を向上する取り組みが行われているという傾向を知ることが重要です。この傾向に合わない実践を現場で行うと、効果の無い的外れな実践になってしまいます。
学力というのは、「自力でできる状態」に持ってくるのが理想であり、これが社会性につながってきます。「子どもたちだけで楽しめる」「先生がいなくても楽しめる」これが「社会性」が身についた状態です。学校の先生はそれぞれ教育観が異なります。お互いに教育観をめぐって対立することもあります。ただ、先生がいなくても「子どもだけ」でできるようにすることに反対する人はいません。この傾向を押さえるようにするべきでしょう。

↑当日の様子
○マズローの五段階欲求を実践にした理論
ともはる先生:これは、先ほどの実践の話とつながります。それぞれの実践が、どの欲求に結びつくかは異なります。私は各々の先生が得意な実践をやれば良いと思います。ただし、バランスだけは守るべきです。
その中でも
・生存
・関係
・成長
この3つの欲求が大事です。それらを満たすために、1年間を逆算してクラス経営を考えていきます。
4 集団の特徴をいかす
ともはる先生:やんちゃ君を思い出してみてください。もしこのような子どもがクラスにいたらどうしますか? まず最初に注意するのが普通であると思います。ただ、科学的視点においては、注意することで悪い行動は一時的に減りますが、いずれ違う悪さをするようになります。
それでは、良い行動を増やすにははどうしたら良いでしょうか。
ここで、2:6:2の法則をご紹介します。
※詳しくは事前取材記事をご参照ください。
この法則にのっとると、できない子をあえてスルーすることが大事です。これをポジティブスルーと言います。これがクラスの安定に繋がります。
皆さんの中で学級崩壊をしている現場を見たことある人はいますか? なぜそれが起きるのでしょうか。ほとんどの先生は悪さをした子どもを叱ります。叱るというのは子どもにとって注目されることと同義です。すると、悪さをしない残りの8割の子どもたちは無視されていると感じます。そのため、その普通の子どもたちも「悪さをする子ども」と一緒になって悪さをするようになります。これが学級崩壊の一番多い理由です。
子どもを伸ばしたいときは、「できる」2割の子どもに注目します。すると、みんなは「できる」2割の子どもを真似するようになります。このようにして、できる子どもの方にひっぱることができます。「できる」2割の子どもを褒めるだけでクラスの雰囲気が変わります。これもまた2:6:2の法則の実践例です。
ところで、みなさんはクラスでのいじめ対応はどうしていますか? 例えば、持ち物を隠されてしまった子どもがいたとします。そのような場合のいじめ対策は、傍観者の意識を変えることです。傍観者はいじめと一緒です。「音楽」や「お楽しみ会」など、人気のある授業や行事をすべて無くして、いじめをする側が損するということを意識づけます。先生が止めるという意識と覚悟を持つことが大事です。
私のルール設定はクラスで一番できない子を基準にします。ただし、学校の基準には最低限合わせます。
5 一年間を見通した授業
一斉授業の4つのポイント
①常時活動と本時活動
- 常時活動→毎日継続して行う活動
- 本時活動→本時目標に沿ったメインの授業
ともはる先生:習得に時間のかかる技能は常時活動で確実に身につけられます。いっぽう、本時活動は本質に絞った内容のみを短時間で行います。これらを目的に応じて使い分けることが重要です。
②教師が間違える
ともはる先生:先生が「正解を言ったら褒めてくれる」と生徒に思われてしまうと、実は厄介なことが起こります。生徒は基本的に先生から褒められたいので、先生から問題を出されたら正解を当てようとします。そうなると、「正解しか言ってはいけないのではないか」という心理が働いてしまい、生徒は自分の意見を言わなくなってしまうのです。
だからこそ、あえて先生が間違えて、「あ、先生も間違えるんだ、これなら間違えても大丈夫かな。」と、生徒が間違いを恐れず自由に発言できる雰囲気を作ることが大切です。
③答えがたくさんある発問
ともはる先生:
・口に2画加えてできる漢字を答えなさい。
・「しょう」と読む漢字を書きなさい。
・平行四辺形の面積はどう求めればいいですか?
・この写真を見て気づいたことを全て書きなさい。
・この場面を絵で描きなさい。
以上のように子どもに答えがたくさんある発問をして、黒板に書かせます。黒板は、子どもが書くものという考えを持つようにしましょう。
④黒板の開放
ともはる先生:黒板の開放が大事です。黒板は先生だけが書くものという考えはありません。 クラスのみんなで書くものです。クラスの全員が動いたら、それがクラスの子どもの良い姿です。そして、クラスだけではなく最後に先生の意識も変わっていきます。
6 実践を発信する意義
ともはる先生:情報を発信をして、フィードバックを受けるときが一番ためになります。私は他のクラスに入って授業をするという教師修行をしていました。失敗したら恥ずかしいと思うので、若手の教室で授業するのがプレッシャーになります。様々な人が反響をもらえるので、SNSで情報発信するのも非常に大事だと考えます。自己成長をして楽しい学級にしていきましょう。
7 あとがき
実際に現場の経験がある先生による、普段は直接聞いたり学んだりする機会がない学級経営について考える良い機会だと思いました。参加者も少人数ながら積極的に発言をしており有意義なEDUPEDIA SCHOOLとなったのではないでしょうか。
(編集:EDUPEDIA 竹内雅浩 大森友暁 斉木梨紗)
8 関連記事
ともはる先生への事前取材記事はこちらです▼
授業中好き勝手に行動する子への対応(第3回EDUPEDIA SCHOOL)
9 登壇者のプロフィール
ともはる先生(元小学校教諭)
(本名:前田智行先生)
株式会社CAI 放課後デイサービス オレンジスクール部門児童指導員
子どもの発達科学研究所 こころの発達アテンダント認定講師
日本LD学会・授業UD学会所属
ともはる先生の実践まとめサイト:リンク
ともはる先生のTwitter:twitter
著書『特別支援教育の知識で全員を育てる! ユニバーサルデザイン学級への6原則』(教育報道出版社、2018)





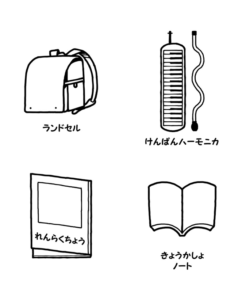

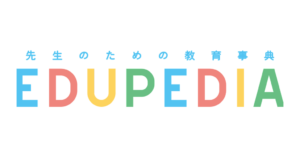
コメント