はじめに
本記事は、2023年11月9日に行った、東京理科大学の堀田義太郎先生へのインタビューを記事化したものです。
堀田先生は差別を専門に研究をされており、大学での授業のほか講演やセミナーなども行われています。
本記事では、堀田先生の研究内容、差別の問題に対する考え方、それを学校で子どもたちに教える際にどのようなことに気をつけるべきなのかについて紹介します。
本記事は2部構成の前編となっています。後編はこちらをご覧ください。

差別に関する研究
「差別」というテーマに興味をもったきっかけ
私が差別に関心をもったのは、何か特定のきっかけがあるわけではなく、さまざまな経験が重なって興味をもっていきました。ただ、ひとつは、大学院生のときに障害学という領域に触れたことは大きいと思います。また、同時期に重度の脳性まひの方の介助ボランティアも経験しました。これは、頭の中だけではなく実際の経験も含めて差別について考えるきっかけになりました。
何人かの名前を挙げると、社会学者である立岩真也さんの書籍やフェミニスト哲学者の大越愛子さんの議論に影響を受けました。大越さんに関しては、大学院生時代から長い間読書会に参加し、そこでの議論を通して自分がいかに差別に加担してきたかということを痛感しました。それまで普通だと思っていたことが、直接ではなくとも差別に関与していること、自分の考えが危険であることに気づくという意味で、非常に大きいきっかけになりました。
また、親の影響もあります。今思えば私は、子どものころから「いじめは絶対にしてはいけない」などの倫理観を強く教え込まれてきました。
障害学とは
簡単にいうと、障害当事者の観点から社会を批判的に見ていくというものです。障害学のとても重要な考え方として「障害の社会モデル」というものがあります。社会モデルとは、医学モデルと対比される考え方です。障害は、基本的に状態が固定されています。病気や怪我の場合は治療をしなければ身体が痛くなったり命が危険にさらされたりしますが、障害は、あまりそれ自体が原因で不利益を被ったり苦痛を感じたりすることはありません。不利益や生活上の制約の原因は主に社会の側にあるのです。この発想が社会モデルの基本になっています。
研究の内容と方法
本来、差別を研究するには歴史的な背景も含めて事実を知ることが重要です。しかし、私はどちらかというと哲学・倫理学の領域で研究していますので、「差別とは何か」「差別はなぜ悪いのか」「差別と区別の違いはどこにあるのか」「一見差別のように思えることが本当に差別といえるのか」などといったことを考えています。
たとえばアファーマティブアクションという取り組みがありますが、これに対して「マイノリティを優遇している」、「マジョリティに対する逆差別だ」という批判があります。たしかにマジョリティの人は、本人がコントロールできない特徴に基づいて不利益を受けるので、形式的に見ると逆差別といえるかもしれません。しかし、この取り組みには差別を是正するという目的があります。
こうした主張の違いがなぜ生まれるかということについては、実際の事例の研究はもちろんですが、哲学・倫理学の抽象的な観点から分析していくことも重要です。私はそうしたことを哲学・倫理学のアプローチから研究しています。
差別の中でも重要なテーマ
「差別」と一言で言っても、対象になるものは本当に幅広く、重要性を比較することはできないのですが、そのなかで私自身にとって最も重要だと思っているのはフェミニズムの理論です。フェミニズムの理論は歴史的な蓄積もあり、そこで考えられてきたことは他の差別にも当てはまる内容も多く、典型的な事例として差別を考えるうえで必要不可欠です。
また、私のジェンダー・アイデンティティは男性です。だからこそ「差別の哲学」という一般的な観点だけでなく、自分自身が差別する側にいるという自覚をもちながら研究をしています。また、差別の問題は日常的なやりとりや生き方にまで関わっているという点でも、非常に重要なテーマだと思っています。単なる知的好奇心だけでなく、自分の生き方への影響と重要性も研究の動機になっています。
差別について考えてもらうために
差別について考えてもらうための工夫や効果的な方法などはありますか。
私は、具体的な事例をあげることが大切だと思います。その事例に対して自分はどう考えるか、あるいはそれに関してどのような議論があるのかということを考えることは現実の問題として重要ですし、また効果的だと思います。
また、聞き手の差別に対する関心がもともと高い場合もあります。たとえば、差別に反対する活動をしている人や差別について学校で教えている教員などを対象にした講演では、スムーズに答えが出てこないような事例を扱いました。たとえば、これは知人から教えてもらった問いでもありますが、次のような問いを示したことがあります。「4、5人で話しているなかで、子どもがいる共働き家庭の母親が『仕事で帰りが遅くなることがよくある』という話をした。すると、ある人が『お母さんが家にいないなんてかわいそう』という発言をした。この状況に対して自分ならどのように問題を指摘するか」という問いです。
固定観念と言葉遣い
学生から教えてもらったことですが、マッチングアプリの男性のプロフィール欄に「家事育児に参加・協力するかどうか」という項目があるそうです。つまり、男性は家事育児を主体的に行うのではなく「参加」「協力」するという認識があるのです。その学生はそれを見て、いまだにこんな項目があるのかと驚いた、と書いてくれました。細かいことですが、やはりこうした気づきは重要だと思います。
特に、男女の役割分担に対する固定観念というのは主に言葉によってテンプレート化されています。私たちは人から言葉や振る舞い方を学ぶので、社会にある物事や考え方を内面化してしまうのです。
たとえば、「気が強い」という言い方があります。これは女性や子どもに対して使われることはあっても、大人の男性に対して使われることはほとんどないと思います。なぜでしょうか。おそらくこうした言葉を使う人は自覚していないと思いますが、女性は「弱い」のが当然または「弱くあるべき」といった考え方が背景にある、少なくともそうした考えと繋がっているのではないでしょうか。また、「女々しい」という言葉もそうですよね。
他にも、男女の言葉遣いに関して非常に興味深い話題があります。平野卿子さんの『女ことばって何なのかしら?』という新書のなかに、何か嫌なことをされたときに「やめろ」と言うか「やめて」と言うか、という議論が出てきます。女性は丁寧な言葉遣いをすることが望ましいとされているので、命令形の「やめろ」ではなく依頼形の「やめて」を使うことが期待されている、と。痴漢やハラスメントを受けたときに女性が「やめろ」と言っても何の問題もなく、むしろ言うべきとさえ思えますよね。しかし、社会の中で共有されている価値観、この場合「『やめろ』と言う女性は乱暴だ」「女性はおしとやかであるべきだ」という価値観が、言葉遣いを制約してしまっているとすれば、どうでしょうか。依頼の場合、それに従うかどうかは相手に委ねられます。嫌なことをされても相手に対して命令形を使いづらいとすれば、一見単なる言葉遣いに見えることが、身体の安全性や発言や行動の権利にも関わるような多大な影響を与えていると言えるのではないでしょうか。
様々な場面でお話をされるなかで、聴衆の方の差別に対する理解の深まりについて、感じていることがありましたらお聞かせください。
私は学生に、自分の言動や感情、ものの考え方、価値観などにどのような背景があり、どのように社会とつながっているのかということを主体的に考えてほしいと思っています。これは学生のみなさんに求めているだけではなく、私自身にとっても一生続く作業だと思います。私はそのきっかけを与えようと思って授業をしています。
もともと差別に対してそれほど興味をもっていない人でも、本や論文を読んでそれについて議論したり感想や疑問を発表してもらったりしながら進めると、かなり深いところまで話が進みます。
いまちょうど、『結婚差別の社会学』という部落差別に関する本を少人数の授業で扱っています。その授業では、自分の結婚相手が差別部落の出身だったらどうするかという問いや、親戚に部落差別の話をしてマイナスの反応が返ってきたことがあるという経験談など、さまざまな話が出ました。そして、どうしたらよいかなども含めて考察と議論を深めました。このように自分自身の問題として考えてもらえるのは、少人数の授業だからという条件はありますが、やはり教員として良かったと思います。
自分の考えを共有してもらう
また、授業のコメントペーパーで私があまり知らない情報を教えてくれることがあるので、それを授業でシェアすることもあります。そのように同じ授業を受けている他の学生の反応を聞くことで、学生の思考が喚起されていることも感じます。講義形式で教員が話して終わるだけでは自分ごととして捉えられずに終わってしまう気がします。
学生はなかなか具体的な経験もコメントペーパーに書いてくれます。たとえば、女子学生が、かつて生徒会長に立候補したときに、友人に「女なのにすごいね」と言われた、と。その高校は歴代の生徒会長は全員男子だったそうです。その人は実際に生徒会長に就任したそうですが、当時は友人の言葉の意図が分からずスルーしていたけれど、授業を受けてその言葉を思い出してあらためて考えた、という話がありました。
このように、過去の自分の経験を社会的な文脈で捉え直して、その出来事や感情が社会や歴史とつながっていることを認識してもらうことは非常に重要だと思います。
こんな話もありました。これは数年前のレポートで書いてくれたことで、本人に許可を得てお話ししていますが、女子学生が、実家に帰省した時に弟とゲームをしていたら、父親がその学生だけの名前を呼んで「お母さんを手伝いなさい」と言ってきた。弟には言わなかった、と。そこでその学生が父親に「私が女だから?」と聞いたら「それはそうだろ」と返された。さらに祖父にも「女の子を大学なんかに行かせるから口答えするようになったんだ」と言われた。これは数年前ですから最近の話です。こうしたエピソードを聞くと、今でもそういう考えが存在しているのだと気付かされますね。
プロフィール
堀田義太郎先生
東京理科大学 教養教育研究院 野田キャンパス教養部 准教授
1997年立命館大学産業社会学部産業社会学部卒業。2001年立命館大学大学院文学研究科博士前期課程修了。2006年大阪大学医学系研究科博士課程修了。

編集後記
なぜ教育者の差別への意識が大切なのか、これまで詳細な理由も考えずに漠然と思っていました。しかし今回、人は自身の周りにあるフレーズを吸収して使うようになるからとのお話に納得しました。皆が使う言葉をどのように変え、学校や社会を居心地の良い場所にするか考えていけたら良いと思います。(稲田)
今回の取材を通して、現在私たちがもっている差別的な考えや固定観念は、無自覚のうちに内面化されていったものだと気づかされました。私自身が差別というテーマについて本格的に学んだのは大学生になってからですが、学校教育、特に義務教育の段階においてそうしたテーマを扱うことが重要だと感じました。(岩井)
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 稲田蓮、岩井綾花)


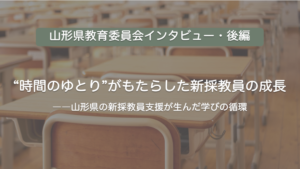






コメント