はじめに
本記事は、2023年11月9日に行った、東京理科大学の堀田義太郎先生へのインタビューを記事化したものです。
堀田先生は差別を専門に研究をされており、大学での授業のほか講演やセミナーなども行われています。
本記事では、堀田先生の研究の内容、差別の問題に対する考え方、それを学校で子どもたちに教える際にどのようなことに気をつけるべきなのかについて紹介します。
本記事は2部構成の後編となっています。前編はこちらをご覧ください。
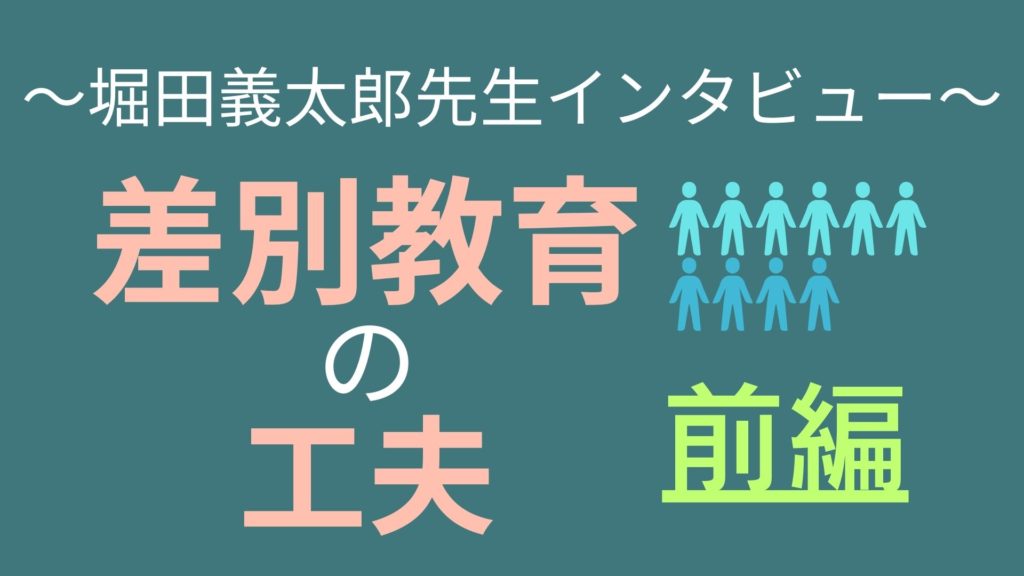
学校で差別について教えるには
学校における教員の振る舞いは、子どもの考えにどれほど影響を与えるのでしょうか。
極めて大きな影響を与えると思います。差別は文化のなかに埋め込まれてしまっているものも多いので、人は何も考えずに生きていると差別に加担してしまう、と思っておいた方がよいと私は考えています。そのため、教育に携わる人は「自分は常に差別に関与している可能性がある」という自覚をもっておくことが必要です。
たとえば、最近学生から次のような話を聞きました。その学生の友人が教育実習に行った時の話です。その友人が他の教員と地図を見ながら修学旅行の行き先について話している際に、ベテランの教員が女性の教員が見ていた地図を「女には地図は読めないだろ」と言って取り上げたそうです。ここまで露骨な行動は珍しいと思いますが、こうした振る舞いをする教員もいるわけです。
教材の影響
教員の行動だけでなく、教材の影響も大きいと思います。たとえば、これは名古屋大学高等教育センターが作った教員用の優れたティップス集の「学生の多様性に配慮する」という章で、避けるべき例として挙げられているものですが(https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/tips/basics/consideration/index.html)、「太郎君がCD‐ROMドライブを買いました」「花子さんはぬいぐるみを買いました」といった教科書の例文があります。これを、「今はもうこういう例文が出てくることはないでしょうが」と言って紹介したら、「今でも外国語の教科書の例文で同じようなものがある」と学生から教えてもらったことがあります。テレビやアニメもそうですが、子どもたちが使う教材で描かれるイメージというのは、モデルとして内面化されていくことが多いです。そのため、教材を変えていくことは学校における差別を減らしていくことに効果があると思います。あるいは、むしろ、上のような固定観念を含む例を出して、その問題点を一緒に考えたり共有したりする方がよいかもしれません。
小学生のような幼い年齢の子どもに対して、日常をもとに差別について考えてもらうのはやはり難しいのでしょうか。
高校生以上の人に考えてもらうのとは違う難しさがあると思います。実は私自身、小学生のときに女子に対して露骨な差別的発言をした経験があります。私自身の話は例として悪すぎるかもしれませんが、その経験だけでなく、小学生に向けて差別につながる考えや言動を自覚させるのは難しいような気がします。ただそれは、私自身が主に大学生を対象にした授業しか経験がないから、私にはすぐに方法を思い付くことができず難しく思えているのかもしれません。そのうえで、小学生のアイデンティティや言動に対する影響力がいちばん大きいのはやはり親だと思います。高学年になると変わっていくと思いますが、そこを教員が完全にコントロールすることは難しいことのように私には思えてしまいます。
小中学生への差別教育
そういうわけで、私は差別を教えるのは小中学校の教員の方が大変だと思います。高校生や大学生は事例を使って説明すればある程度は理解することができます。しかし、小中学生に伝えるには、それに加えてテクニックが必要になると思います。
だからといって、差別という概念やその仕組みが小中学生に伝わらないわけではないと思います。大学生と同じようなやり方では難しいかもしれません。それは、自分の行動を客観視して、対象化して思い返して反省するという行為の難しさ、そして主体的に行動する経験そのものの少なさがあると思うからです。ですから、大学生とはかなり違う難しさが当然あると思うのですが、それなりのやり方はあると思います。
最近、海外の小学校くらいの年齢の人が使う教科書や絵本の素晴らしい翻訳がいくつか出版されています。こうした教材は小学生でも使えるので、ヒントになるのではないかと思います。
あと、これは大学生か小学生かにかかわらないと思いますが、教える側、つまり教員自身が自分の問題として差別をする側に回ってしまう可能性、または実際に差別をしてしまった経験などを話して、一緒に学ぶという姿勢は大事だと思います。実際、私自身もそうですが、教師も大人だからといって、差別に加担してしまう可能性は、学生や生徒または児童たちとそれほど大きくは変わらないと思うからです。むしろ、学生や生徒の鋭い指摘から学ぶこともあると思います。
学校における差別教育の意義について、どのようにお考えですか。
常に大きな意義があるうえ、不可欠だと思います。差別に関する内容が、学校教育のカリキュラムに必修として含まれている必要があるとさえ思っています。これは義務教育にかぎらず、小学校から大学までの全課程に言えることです。
なかでもいちばん重要だと思うのは事実です。これは小学生に教えるのは難しいかもしれませんが、歴史的にあるいは現実としてどのような差別が存在しているのか、何が差別につながっているのかを考えることです。これまでに話した事例のような日常的なところから、現実に差別が存在していて我々はそれと無縁で生きていくことはできないということを教えるのは非常に重要です。「差別をしてはいけません」と言うだけでは足りません。生徒や学生が自分自身の生活や見聞きしているものを振り返ることで、実際にどのような差別が存在してきて、今でも存在しているのかということを考える、そうした教育は非常に価値があります。
日常生活と差別教育
マスメディアにおける男女の表象も大きな影響力をもっています。たとえば、多くの人が観たことがあると言うアニメ映画、『君の名は』では、主人公の2人が入れ替わったシーンで男の子が鏡を見て「おまえは誰だ?」と言います。一方、女の子は「あなたは誰?」と言うのです。先に命令形の話に触れましたが、日常的なやり取りの中での言葉遣いや振る舞いがどのような考え方や行動につながっているのかを考えるのは重要だと思っています。また、メディアに登場する政治経済のコメンテーターは中高年の男性が多いです。このように、なんとなく見聞きするものも差別につながるのだということを知らせるのは、非常に重要だと思いますね。
もちろん、大前提として、人間みんな平等で、目の色、肌の色、性別、出生地、宗教などにかかわらず等しく尊重されるべきという原則があります。それがないと、差別がなぜ悪いのかが分からなくなってしまいますので。本人に非がないにもかかわらず対等に扱わないのはだめ、ということを前提としたうえで、では、社会にどのような不平等な状況があるのか、これまでどのような歴史があってそれが現在とどうつながっているのか、ということを具体的な事例に即して教えることが本当に重要だと思います。
プロフィール
堀田義太郎先生
東京理科大学 教養教育研究院 野田キャンパス教養部 准教授
1997年立命館大学産業社会学部産業社会学部卒業。2001年立命館大学大学院文学研究科博士前期課程修了。2006年大阪大学医学系研究科博士課程修了。

編集後記
身の回りの言葉や教材から無意識に内面化してしまうという性質との向き合い方こそ、差別教育の鍵だと感じました。教育者一人ひとりが日頃から差別意識を持つべきであること、それは教育者の発する情報が常に子どもたちに吸収されうるためであるということを周知していく必要があると考えました。(稲田)
今回の取材を通して、現在私たちがもっている差別的な考えや固定観念は、無自覚のうちに内面化されていったものだと気づかされました。私自身が差別というテーマについて本格的に学んだのは大学生になってからですが、学校教育、特に義務教育の段階においてそうしたテーマを扱うことが重要だと感じました。(岩井)
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 稲田蓮、岩井綾花)


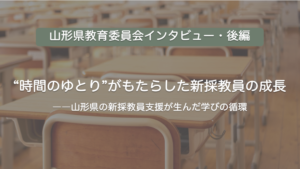






コメント