どうしてあげればよいのかわからないような学力不振
学力不振の子供が授業に入っていけない様子を見るのは辛いです。分からない授業を45分間受けるのは、長いだろうなと思います。できればガッツリと学力保障に取り組みたいです。通年で組織的に・・・。
とは言うものの、時間もないですし、何から始めればよいのかもわかりません。在籍する学年の内容では難しく、前の学年、前の前の学年の内容の学習をさせるのも「焼け石に水」であるように思えます。いったいどうしてあげればよいのか分からないぐらいの学力不振に陥っている子供もいます。
学力保障の難しさと大切さについては、ぜひ下記リンクをご参照ください。
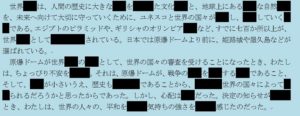
学力保障が難しいからと言って、何も手を打たなければ学力不振の子供は「無気力になる」「トラブルを起こす」「授業妨害をする」「登校を渋る」など、指導が困難化しやすいです。簡単に見捨ててしまってはいけません。見捨てていないというサインを出し続けることが大切です。
「教師はカジュアルに子供を見捨てる」(近日公開)
様々な方法で学力不振の子供たちとは心をつなぎ、指導困難にならないように留めたいですね。その子供の興味関心、趣味やストロングポイントに寄り添ってつながりを保つことは大事ですが、できるだけ学力保障で信頼関係を築いた方が良いと思います。だからと言って闇雲に在籍学年の漢字をいっぱい書かせるとか、計算をさせるとかは、悪手です。子供のウィークポイントを無理に何とかしようとしてもそう上手くいくものではありません。しんどいことはお互いにストレスを増すだけで続きません。まずは、しんどくないことから始めましょう。
なお、この方法は家庭学習でも有効ですので、是非、お家の方にも読んでいただきたいです。
漢字ドリルは有効なツール
学力不振に対応したツールは探せばあるのだろうけど、本人に何がマッチするのか分からないと思っている方も多いのではないかと思います。本人にとって負担になるツールを使ってしまうと、あまり成果が上がらなくて、ほめてあげることもできません。お互いにストレスになってしまうこともあるでしょう。苦行な学習を強いれば心が離れてしまう可能性もあります。簡単で短時間でできることでないと子供も大人も長続きしません。
そこで、「漢字ドリルを読ませる」というシンプルな方法を提案します。
やり方は簡単です。漢字ドリルの漢字で書いてある方のページを読ませるのです。
① 漢字ドリルなら、手に入りやすいし馴染みもあります。本人が在籍する学年のドリルで50%程度を正しく読む力があれば、そのままそれを使いましょう。それが難しければ本人の学力に合わせて、下の学年のドリルで50%程度を正しく読めるものを用意してあげればいいです。
② 対面で、5分程度を目途に指導します。
③ 1ページに20問ぐらいあるタイプの漢字ドリルが多いですが、1日10問(半ページ)でいいです。集中力が続かない場合には、5問でにいいと思います。本人が負担にならない量を1日分に設定してあげましょう。
④ 声を出して読ませます。よどみなく言えたら、番号に丸をします。よどんでいたり、読めなかったりする場合は、何かヒントを出してあげます。その場合はは丸印なしです。下の図では「類い」と「昔話」が読めていません。

⑤ 読めなければ、読めなかったところを教師が読んで復唱させます(3回)。
⑥ 一気に10問(5問)全部読めたら、下図のように”goood”や花丸をつけてあげます。学力不振の子供はスタンプやシールも喜びます。

⑦ 一気に読めなかったら、最後に読めなかったところをもう一度読ませて、「よしよし、じゃあ明日がんばろうね、明日はできそうだよ」と言って笑顔で終わります。これで1日分は終わりです。引っ張りません。(もし、子供が「もっとやりたい」と言えば「いーーーじゃない!そのやる気大事!」「じゃあ、あと、10問だけね」と言って乗せましょう)
⑧ 10問中5問以上を言えていたら、次の日には新しい10問に進みましょう。4問以下であれば、次の日にもう一度挑戦させてください。
⑨ 「花丸はお家の人に見せてあげてね」と言って、保護者と教師で喜びを共有します。時々、連絡帳などに「漢字を頑張ってます」などのメッセージを書くのもいいともいます。
⑩ 絶対に、読めないことを責めません。読めない時には「おしい」「もう少し」あるいはヒントを出して答えたら「そう!OK!」と褒めます。「子供を責める時間」にせず、子供が「できたこと」の方にフォーカスできるように持って行きます。ほめることが目的だと思ってください。それによって、教師に対する子供の認識を「授業でわけの分からない事を延々と教える先生」から「自分を見捨てず、力をつけてくれて、ほめてくれる先生」へと変えてゆけます。
⑪ 時々、クリアした部分に戻って定着を図るのもよいでしょう。できるようになったことを子供といっしょに振り返り、成長の喜びをかみしめましょう。
簡単&タイパ
この程度の指導であれば、隙間時間でできてしまいます。朝や帰り、給食を食べ終わってから「ごちそうさまでした」までの時間にちょっと呼び出してさらっとほめて、終わることができます。毎日でも続けられることができる簡便さです。ほめほめ作戦がうまくいき出すと、子供の方から
「せんせー、今日は漢ド(漢字ドリル)しないのーーー?」
と、声をかけてくるようになって来ます。ちょっとした子供との関係づくりになります。
漢字ドリルをクリアできたら、今度は少し長文の中に埋まっている漢字を読ませるのもいいと思います。下記リンク先をご参照ください。
小学3年生新出漢字の読みが全部入った文章【教材】 | EDUPEDIA
これ↑↑↑も、読めた漢字をマーキングし、1段落をよどみなく読めたら花丸をあげるといいと思います。シリーズで小学1~6年生までの漢字が全部入った文章をアップしています。
また、下記リンク先の記事は読みを優先した漢字教育の実践について書かれたものです。ネット上で使える教材も充実しており、お勧めです。

下↓↓↓のリンク先の記事にはこの取り組みのように、簡単で時短に繋がる指導をたくさん掲載しています。
誰にでも、簡単にでき、効果のある教育実践 ~教師の資質や負担に依存しない「点数を稼げる実践」を | EDUPEDIA


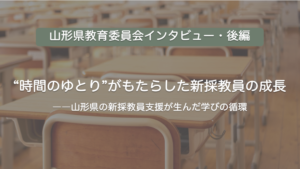



コメント