長縄もだんだん飽きてきます。特に、記録が伸び悩んでくると、いやになってきます。そんなときには、いろいろなバリエーションでやってみましょう。
長縄の連続跳びに関してはこちら↓

1 高速長縄
うまい子どもが多いときは、超高速で縄を回します。20回ぐらい連続で跳べたらけっこう盛り上がります。ただし、引っかかると派手にこけるので、こけやすいことをあらかじめ予告して注意を促しましょう。怪我のないように要注意。持ち手と持ち手の間を狭くすれば、それほど勢いをつけなくても跳べるので、安全確保ができます。目安は、クラス全員で3分間200回ぐらいでしょうか。ギネス記録の動画があるので、Youtubeで「長縄 高速」などと検索してみてください。
ギネス級は尋常ではないです。クラスであまり目標のハードルを上げてやると、どうしてもついていけない子どもが排除されるため、そこは気をつけないといけません。
2 逆回転
逆回転で跳びます。これはけっこう難しい。
3 長縄の中でじゃんけん
長縄の中でじゃんけんをします。勝ったら残るにしてもいいし、負けたら残るにしてもいいでしょう。勝った人(負けた人)が出て行くときも次の人が入ってくるときもノンストップで回し続けます。チームを組んでやってもいいと思います。
4 ダブルタッチ
単純に2本の縄を使うだけでも難しいですが、2人で入ったり、向きを変えたり、すごいのがあります。日本チームは大人も、小学生も、世界大会で優勝しているようです。Youtubeで閲覧してみてください。子ども同士では回すのが難しいです。詳しく説明すると長くなりますので省略。高学年が普通10回ぐらい跳ぶのならそう練習しなくてもクラスの半分ぐらいはできるようになります。高学年になると8の字跳びは簡単すぎて飽き足らなくなってしまう場合もありますので、そんな子どもたちには是非トライさせてあげてください。
普通の長縄連続跳びは「タタタ」で走って「トン」で跳ぶといいのですが、ダブルタッチの場合は、「タトントントントントン」と、リズムが速くなります。縄に近い場所から、自分の目の前で縄が重なったタイミング(そこから助走の間に縄が開いていきます)で入ると上手くいきます。
跳びながら曲芸
ダブルタッチの大会などを見ていると、2本のロープの中で宙返りしたり馬跳びしたりしていますが、そんなことは片手間ではちょっと難しいでしょう。1本の長縄の中で、「シェー」「ウッキー」「キャイーン」など、あほなポーズをとりながら跳ぶだけでも楽しいです。もう少しレベルを上げて、「長縄の中でボールをドリブル」「長縄の中と外でボールをパス」「長縄の中で短縄を跳ぶ」などバリエーションはいろいろ考えられます。
5 2人で跳ぶ
曲芸の一種ですが、二人組みでいっしょに入って、跳びます。できるようになったら空回りなしの連続で跳ばせてみましょう。連続で10回ぐらい跳べたら盛り上がります。うまくいったら、3人で。
6 引っかかったら減っていく
そうすると、だんだん少人数で連続跳びをしなければなりません。6年なら上手な子どもが跳んでゆっくり回せば2人でも跳びます。これは、サーカスぽくて面白いです。残った子どもには大喝采です。
7 多人数でずっと跳ぶ
人数は縄の長さにもよりますが、1列に並んで「せーの」で跳ばせます。最初は5人で10回を飛ぶことも難しいため、協力することを学ぶことができます。
8 多人数でずっと跳ぶのバリエーション1
勝ち残りです。7人ぐらいからはじめて、引っかかった子どもを1人ずつ抜けさせます。そうするとだんだん数が減ってきて、最後は2人になりますが、最後まで残っただけあって、なかなか引っかかりません。2人とも王者をかけての戦いでの意地がありますから、必死で跳びます。最後まで残って疲れているにもかかわらず、30回、50回と跳びますので、その意地の張り合いが見ていて面白いです。残ったのが男女になるとまたこれが盛り上がります。
9 多人数でずっと跳ぶのバリエーションⅡ
負け残りです。20人以上の多人数でいるときは、まず1列に並ばせます。3人~5人で跳ばせて、引っかかった1人を一番後ろに並ばせ、次の1人を補給します。10回以上(回数は実力に応じて設定)跳んだらその5人は終わり、次の5人を補給します。負け残りなので、どの子供にも克服できるまで跳ばせられます。苦手な子どもほどたくさん練習しないとなりません。
これは2011年に書かれた記事です。
(最終更新日 2025年1月9日)


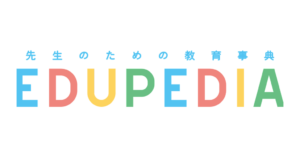
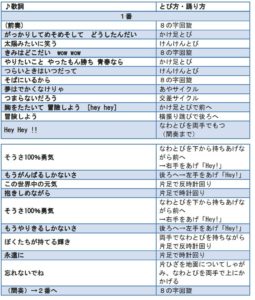
コメント