
先生方が勤務している学校の掃除時間はどれくらいですか?
おそらく15分〜20分ほどの時間に設定されている学校が多いのではないでしょうか。
たった15分〜20分ほどの時間ですが、侮ってはいけない時間です。
少ない時間でも、掃除は学校教育の一環として役割を果たしています。
ただ、子どもたちはほぼ毎日掃除活動に取り組むため、飽きややる気の低下に直面します。
毎日の活動は指導が難しく、特有の発達段階がある高学年ともなると、より一層指導が難しくなります。
高学年の掃除指導では、子どもたちの主体性を育む意識が大切です。
今回は、コーチングの手法を用いた高学年の掃除指導アイディアを紹介していきます。
高学年の掃除指導が難しい理由

はじめに、高学年の掃除指導が難しい理由を考察していきます。
掃除への飽き
5年以上ほぼ毎日取り組んできた掃除活動。
飽きてきても無理はありません。
「高学年だからできて(やって)当然!」という姿勢で指導すると、子どもたちからの反発を招くことも。
高学年だから任される掃除場所ややり方があります。
だからこそ、一つ一つ丁寧に指導していきます。
また、高学年としての役割を与え、自覚を促したり、成長を認めたりする視点も大切です。
高学年の発達段階
掃除活動に影響与える高学年の発達段階には、以下のものがあります。
- 面倒くさがる
面倒くさがって雑にやる傾向が高学年にはあります。
掃除に限らず、文字を乱雑に書いたり、簡単なルールを守らなかったりする特徴は高学年ならではです。
- 掃除の方法や意義が伝わっていない
掃除活動をただの「義務」として捉えられていると、子どもたちはその重要性や意味を理解しにくくなります。
掃除が学校やクラスの環境を良くするための大切な活動だという意識が薄れている場合、やる気が出にくくなります。
- 掃除が無駄だと思う
一部の子どもたちは、掃除をしてもすぐにまた汚れるという無力感や無駄感を感じることがあります
特に、掃除後にすぐに他のクラスメイトが汚したり、掃除の効果が目に見えて実感できなかったりすると、やる気が削がれることがあります。
- 友人との関係や他の活動を重視
高学年になると、友達との関係や休み時間にやりたいことが増えるため、掃除活動に時間を割くことが嫌だと感じることがあります。
掃除が「自由時間」を減らすと感じる子どもたちは、掃除を避ける傾向があります。
低中学年の指導不足
適切な掃除のやり方・手順を低中学年で教わっておらず、掃除に必要なスキルが身に付いていない場合があります。
また、「掃除は面倒なこと」と子どもたちが感じていると、高学年での掃除指導が難しくなります。
高学年の掃除指導のコツ
ここまで書いてきた高学年の掃除指導の難しさを踏まえて、ここからは掃除指導のコツを紹介します。
主体性を育む工夫
掃除指導を子どもたちの主体性を育てる場にしていきましょう。
命令口調や強制的で高圧的な指導はNGです。
近年、教育現場や人材育成の場でコーチングの手法が注目されており、掃除指導でも有効です。
コーチングとは、個人や組織の成長、目標達成を支援するコミュニケーション手法で、ポイントは以下の4点です。
- 自発的行動を促進するコミュニケーション
- 「教える」「アドバイスする」ではなく、「問いかけて聞く」ことを重視
- 子どもたちが主導権を持つ
- 子どもたちの気づきと行動を促す
答えを「教える」のではなく、子どもから答えを「引き出す」というイメージです。
掃除指導におけるコーチング
では、掃除指導でコーチングをどのように取り入れたらよいでしょうか?
次の3つに取り組むとよいでしょう。
- 課題設定(自己決定)
- 課題へのアプローチ
- 振り返り(点数化)
まずは掃除活動の課題を設定。
「時間内にそうじを終わらせる」「ゴミ一つない掃除」「時間目いっぱいまで掃除をする」など、学校やクラス、掃除場所に応じて課題を決めていきます。
自分たちで決定した課題をクリアすることは、自分たちとの約束を果たすことであり、責任感が向上します。
子どもたちが課題クリアに向かっている掃除中、先生方は気付きを促す問いをしていきましょう。
「ゴミは落ちてなさそうかな?」「あと時間はどれくらいだろう?」「〇〇さんの今日の目標はなんだろう?」「昨日の掃除に比べて、今日の掃除はどうかな?」など、教えるよりも聞いて気付かせていきましょう。
掃除後は振り返り。
おすすめの振り返り方法は点数化です。
例えば、10点満点で掃除を自己評価させます。
ただ点数をつけるだけではなく、もし「7点」だった場合、残りの3点は何かを問うようにしましょう。
「時間内には終わったけれど、始まりが遅かった」と、新たな課題に気付かせ、次回の課題としていきます。
子どもたちが主体的に掃除活動ができるように、コーチングの手法を取り入れてみてはいかがでしょうか?
掃除の頑張りが認められる環境を作る
掃除を頑張っている子に目をつけて、褒めることも忘れないようにしましょう。
子どもたちの中には、黙々と隅から隅まで丁寧に掃除をする子がいるはずです。
このように頑張っている子を見逃さず、褒めていきます。
「学校の役に立っているね」「頼れるお兄さん・お姉さんだね」「やればできるね」と高学年の子どもたちのプライドをくすぐる褒め言葉を子どもたちに投げかけていきましょう。
自己決定した課題のクリアをどんどん認めていき、掃除の頑張りが報われる環境を作っていきます。
また、掃除前と掃除後の写真を掲示したり、掃除の頑張りを動画撮影したりし、視覚的に努力や成果を実感させるのも一つの方法です。
掃除の意義を多面的・多角的な視点で捉える
高学年のお子さんの中には、自我の芽生えという発達段階から「なぜ掃除をするのだろう?」「掃除に意味はあるのだろうか?」と考える子どもも出てきます。
掃除の意義を考える機会を、道徳の時間、学級の時間で設けてもよいですね。
掃除の意義は、「学校をきれいにする」「快適な空間を維持して活動するため」「自分たちの健康のため」「弱い心に打ち克つため」など、多岐にわたります。
衛生面や公共面を中心に話し合ってみましょう。
4月の掃除指導が最も重要
掃除指導は学級経営と同様に、4月の指導が最も重要です。
「高学年だから大丈夫」という考えはせず、「誰がどこで、何をやるか」の最低限のルールと掃除のやり方を徹底的に指導します。
もし、ルールややり方を変えるならば、それも4月中(もしくは学期始めの区切りがよい時)に行いましょう。
4月中に基本を指導したら、あとは全体指導と個別指導を上手に使い分けて、子どもたちの掃除力をアップさせていきます。
実践的な掃除のやり方を学ぶ
家庭科では「住まい方」の単元で整理整頓や清掃について学んでいきます。
家庭科で学んだことを普段の掃除に生かしていくと、深い学びにつながり、掃除力も向上します。
また、美化委員会の啓発活動を活用したり、掃除専門家による出前授業を受講したりして、実践的な掃除のやり方を学ぶと、モチベーションも向上するでしょう。
期間を空けて実践的な掃除を学べるように計画できるとより効果的です。
下級生への掃除指導で責任感アップ
学校によっては「兄弟学級で掃除をする」「上級生が下級生に掃除を教える期間がある」など、縦割りで掃除に取り組む学校もあります。
高学年の子どもたちの責任感を高めるだけでなく、協力や思いやりを学ぶ機会にもなります。
明確な目的のもと、計画的に掃除指導をしていきましょう。
執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。

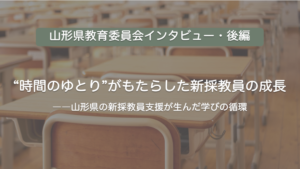







コメント