
高学年の指導は難しいと言われています。
筆者も高学年を多く担任してきました。
高学年の子どもは思春期の入口。
少しずつ大人になりつつあり、素直さが残る一方で「大人や世の中への疑問や反抗心」をもち始める子もいます。
高圧的な指導はNGですが、「ダメなものはダメ」といった毅然とした指導も必要。
その塩梅が高学年指導の難しさでもあり、学級の荒れを作る原因にもなります。
子どもを子ども扱いするのではなく一人の大人(人間)として接し、子どもたちと信頼関係を築くことが荒れ防止につながります。
今回は高学年の学級の荒れを防ぐ方法を解説していきます。
高学年の学級の荒れとは?

高学年に見られる学級の荒れは、「目に見える荒れから見えにくい荒れまである」と心得ましょう。
目に見える荒れ
- いじめ
- 物かくし
- 暴力・暴言
- 先生への反抗
- 目配せ、内緒話
- サボる
- ルールを守らない
- 教室のゴミを拾わない
など
目に見えにくい荒れ
- 発言しにくい雰囲気
- チャレンジしにくい雰囲気
- 無気力
- 無関心
など
学級の荒れの芽はいくつもあります。
高学年の先生方は、気付きにくい荒れの芽に気付けるように、アンテナを高く張って子どもたちと接していきます。
そして、見つけた荒れの芽は、大きくなる前にすぐにむしり取るように心がけましょう。
高学年が荒れる理由
高学年が荒れる理由は、低・中学年とは異なり、少し特殊な面があります。
小学校生活の慣れ(飽き)
高学年になると、小学校生活の飽きや不満が生まれやすくなります。
クラス替えを行う学校でも、子どもたち同士の関係性は5・6年間のうちにほとんどできつつあります。
良好な関係性もあれば、悪い関係性を形成する子どももいます。
力関係が明確になり、見下した行動や言葉からいじめに発展したり、他者と比較して自己肯定感が低下したりする子どもの様子が高学年では見られるようになります。
学校生活に慣れるよさもあれば、マイナス面もあることを心得ておきましょう。
また、学校のルールや世の中への反発も少しずつでてきます。
「なぜルールを守らないといけないのか? 大人だって守っていないじゃないか」
「大人の言うことはおかしい」
「大人や社会が絶対ではない」
こうした学校(社会)や大人への疑問・反発は、思春期の特徴です。
思春期の入口という成長過程
小学5・6年生は思春期の入口です。
子どもから大人への成長過程である思春期では「自我の芽生え」が注目されますが、以下の特徴も考慮して教育活動を進めていきましょう。
- 責任感が芽生える
- 面倒くさがりになる
- 勉強に対する興味が薄れる
- 人前での発表を嫌がる
- 大人の言うことを素直に聞きたがらない
- 友人関係を重視する
高学年の子どもたちは低学年や中学年の時とは全く異なる様子を見せます。
思春期はとても変化が激しい時期で、その変化の激しさに戸惑う子もいたり、不安やイラ立ちから荒れた行動をする子もいます。
こうした思春期の特徴を担任の先生は理解しておきましょう。
また、思春期には個人差があります。
クラスの子どもを思い出してみてください。
思考面、身体面で幼さが残る子もいれば、大人っぽさがすでに出ている子もいませんか?
思春期に見られるこの多様性は、高学年の学級経営を困難にさせる一因でもあります。
多様な発達段階に対応できる力が高学年の先生には必要です。
日々のストレス蓄積
高学年の子どもたちは、学習塾を中心に習い事で忙しくなる傾向があります。
中学受験を志望している子は、受験対策の学習真っ最中です。
また、他人とテストの点数や学力を比較し、劣等感を抱く子も増えてきます。
このように、高学年の子どもは習い事や学業でのプレッシャーやストレスを受けやすい環境にあります。
ストレスが蓄積し、イラ立ちを態度に表したり、物に当たったりします。
また、人間関係にも変化が見られます。
自分に合う友達とつるむようになり、合わない友達は排除していったりもします。
特に女子の友達関係は要注意です。
このように、高学年の子どもは、自分の変化と、周囲の変化に対応しなければならないストレスフルな環境にあります。
指導力不足
ここまで書いてきたような子どもたちの多様で激しい変化の中で、高学年の先生は指導しなければならず、高い指導力が求められます。
高学年の担任が初めての先生は、子どもとの接し方に苦労する様子が見られます。
中堅・ベテランの先生でも、以前に担任した高学年の子どもたちと比較し、目の前の子どもたちに対応できないケースもあります。
いずれにせよ、子どもの心理・行動の理解不足、指導方法の狭さによる指導力不足が、子どもの荒れを生み出す側面があることも否めません。
高学年の学級の荒れを防ぐ対策
高学年の学級の荒れを防ぐために軸となるのは、子どもたちとの信頼関係を作る学級経営と生徒指導です。
一人の大人(人間)として子どもに接し、人として信頼し合えるような環境を作りましょう。
ルールを守る雰囲気をつくる
ルールを守ることは集団生活の基本であり、信頼関係の第一歩です。
普段の生活の中で、学習や生活のルールを守る雰囲気を作ったり、道徳の授業でルールを守るよさに気付かせたりします。
「高学年だから大丈夫!」とうやむやにせずに、学期始めはルールを必ず確認・徹底させる期間としましょう。
ただ、ルールに順応していくのには個人差があります。
ルールの大切さを理解して必ず守ろうとする子や自分の思いを大切にしながらルールに対応する子、ルールに慣れるスモールステップが必要な子など、さまざまな子どもへの配慮を忘れずにルールを守る雰囲気を作っていきましょう。
また、子どもたちの意見を聞くことも大切です。
子どもたちの意見を募って学校のルール(校則)を変えていく学校が増えています。
持ち物や休み時間の遊び方に関するルールについては子どもたちには強い思いがあります。
実際に私が教員として高学年の担任をしていたときに、子どもたちからルールに関して以下の意見が出ました。
「中学校はシャープペンシルはOKだけれど、なぜ小学校はダメなのだろう?」
「雨の日の休み時間に教室で遊べるように、トランプなどのカードゲームをしたい」
こんな意見が子どもたちから出たらどうしますか?
私自身はとても有益な意見だと思い、次のように考えました。
「小中連携の観点から、高学年のルール変更が必要かも。学年主任・管理職(中学校の先生方)に確認し、子どもたちにルール作りの場を与えてみよう」
「自分のクラスだけでなく、1年生から6年生までの全クラスに同じトランプを用意する必要があるかも。生徒指導主任にまずは確認して、子どもたちから提案する形にしてみよう」
実際にトランプの案は、生徒指導主任と管理職に先に根回しをした後、子どもたちの話し合いで「雨の日で校庭が使えないときに、担任の先生の許可をもらってトランプを使う」というルールができました。
そして、児童会の子どもたちにトランプのルールを発表させ、全校児童に知らせました。
ルールに込めた思いや意味、話し合いの流れを、先生から発するのではなく子どもたちから発することで、「自分たちで作ったルールなんだから守ろう」という意識を高められます。
自分たちが提案したルールが学校をよくするという体験は、ルールの意味や大切さを考えるとともに、ルールを守る自覚を高める結果になりました。
「なぜルールを守るのか?」
「どうしてこのルールがあるのか?」
「変えていくとどんなよいことがあるのか?」
頭ごなしに「ルールを守る!」と指導するのではなく、多面的・多角的な視点でルールについて考えていくことは、子どもを大人扱いしているのとイコールです。
対話を通じて信頼関係を高めてほしいと思います。
やるべきことをやる
委員会活動、通学班などといった高学年ならではの活動で、責任感を高めていきます。
「学校のために活動をしている」「高学年の一員として仕事をしている」という気持ちが子どもたちに湧いてくることを目指して指導していきましょう。
まずは、学級の当番活動・係活動で一人ひとりがやるべきことをやる習慣を身に付けていきます。
やるべきことをしっかりやる集団は、学級の信頼感、一体感が醸成されていきます。
後だし指導はNG、事前指導で先手必勝
「ルールを守ること」「やるべきことをやること」を徹底させていくには事前指導が重要です。
先に指導をして、子どもたちのできる力を高めていきます。
例えば、「今日は委員会活動があるけれど、どんなことを頑張りますか?(大切ですか?)」「明日から1年生が通学班に加わります。高学年としてどんなことに気を付けますか?」と問いかけ、子どもたちが高学年として望ましい振る舞いができるように導いていきます。
事前指導をすると振り返りもしやすくなります。
「昨日の委員会活動はどうでしたか?」「1年生のペースに合わせて歩くという意見があったけれど、できたかな?」と振り返ることで、成長を実感したり、次への課題を発見したりできます。
「なぜ活動をサボったの?」「高学年なんだから1年生のことを考えて当然でしょ」と後だし指導になると、子どもたちの中に先生への不信感が生まれる可能性が大きくなります。
「高学年だからできるだろう」という意識は排除し、子どもたちが自分たちで行動を決定していけるように、先回りをして指導していきましょう。
意図的、計画的な指導で子どもの成長を
先回りの事前指導をしていくには、先を見通す力が必要です。
高学年は特に学校行事の関りが多く、成長の機会となることも多いです。
「なぜこの指導をするのか?」という指導の意図と、「なぜこのタイミングで指導するのか?」という指導の計画の2つを明確にして指導する先生の学級は荒れにくいです。
例えば、6月・11月は荒れが見える時期として有名ですが、意図的・計画的に指導する先生は、先の月に手を打っています。
「6月初めにルールの再確認を行う」「11月は子どもの意見をよく聞き、コミュニケーションの量を意識しよう」というように先を見通して指導していくと、子どもの成長過程も見えてきます。
また、先生方の心の余裕も生まれ、荒れを捉えて冷静に対応できるようにもなります。
チームで子どもを見守る
現在、教科担任制を導入している小学校がほとんどだと思います。
高学年の先生は、チームで子どもたちを指導する力が必要になってきます。
同一歩調的な指導が必要な場面、先生方一人ひとりの個性を生かした指導のバランスを大切にし、高学年の子どもたちが学校生活を楽しめるように見守っていきましょう。
中学校の先生から教科担任制の学級経営・生徒指導を学ぶ機会があるといいですね。
高学年の指導で大切なのは言葉
高学年の指導で大切なのは言葉です。
言葉は指導の基本ですが、高学年ほどより大切になってきます。
言葉の力で子どもたちの成長を促し、説得したり、感動させたりしていきましょう。
高学年の子どもたちは言葉の理解力、思考力が高まる時期でもあり、憧れや夢を抱く時期でもあります。
子どもたちの心に成長の種を植えられるように、偉人のストーリーや四字熟語、著名人の座右の銘、先生方の体験などを言葉で伝えていきましょう。
そのためにも、先生方は学ぶ必要があります。
学び手としての範を示し、子どもから信頼を得て、学級の荒れを防いでいきましょう。
執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。


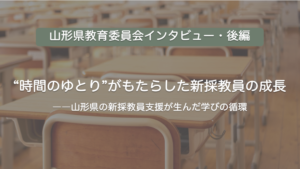






コメント