子どもたちの成長においても、学級経営の面においても給食指導は重要です。
給食指導が的確にできる先生の学級は、安定しており、安心感があります。
低学年の給食指導は、中学年・高学年の給食指導にも関わってきます。
しかし、「1年生の担任になったら、給食指導が1番不安です」「給食指導がうまくいかなくて、給食の時間になると憂鬱になります」と、給食指導で苦労する低学年の先生は多いです。
今回は「給食指導ができるようになりたい!」という先生に向けて、低学年の給食指導のポイントを解説していきます。
低学年の給食指導は見てわかるように

低学年の給食指導で一番のポイントは、子どもたちが見てわかるようにすることです。
給食指導は、言葉で説明するのが難しいことが多く、見てやってもらう方がわかりやすいです。
逆上がりや跳び箱などの体育の授業に近いイメージでしょうか。
次の方法で、言葉より視覚に訴えて理解させていきましょう。
- 先生の見本
- 上手な子の見本
- 写真
- イラスト
- 動画
給食の安全指導のポイント
給食指導で最も重要視しなければいけないのが安全指導です。
手洗い消毒の徹底
給食前には必ず手洗いをします。
手の洗い方、給食着の着用やふきんの用意、消毒の仕方などを一斉指導します。
洗面所に手洗いのやり方を写真やイラストなどで示しておくとよいですね。
食器の取り扱い
「どの食器に、何を盛り付けるのか」を指導します。
プラスチックの食器は割れませんが、中には割れる食器を使っている学校もあります。
割れないようにする指導に加え、割れてしまったときの指導もします。
熱いものの注意
汁物の食缶は熱い場合が多いです。
低学年の子どもの力では持ち上げられない場合もあります。
食缶の持ち運びや蓋の開閉は先生がやるようにします。
合わせて、食べる際はやけどしないように声をかけましょう。
食物アレルギーへの対応
食物アレルギーへの対応は、給食の安全指導で最も重要視しなければいけない項目です。
間違えれば子どもたちの生命に関わりますので、失敗はできません。
アレルギー対応が必要な子どもは何をするのか?
担任の先生は何をチェックするのか?
もし、誤食をしてしまった場合、どうすればよいのか?
各学校にアレルギー対応のマニュアルがあると思いますので、確実に対応できるようにします。
子ども自身から「アレルギーでこれは食べられない」と判断して、訴えられればよいですが、低学年の子どもには難しいです。
先生方が先回りをして対応していきましょう。
食材の誤飲防止
大きいものはよく噛んで食べること、魚は骨に注意して食べることなどを指導します。
また、給食に異物が混入していないかを確認する視点も大切です。
座って食事をする
座って食べることで、食事に集中し、咀嚼(そしゃく)を十分に行うことができます。
立ったまま食べたり、歩きながら食べたりすると、食べ物を急いで飲み込むことが多く、咀嚼が不十分になり、誤飲や喉に詰まらせる危険が増します。
食事中に子どもたちが動き回ると、周囲の物にぶつかったり、他の子と接触して食事を落としたりする可能性があり、危険です。
食事のマナーと合わせて、指導していきましょう。
配膳指導のポイント
配膳指導では以下を指導します。
- 適切な順番の配膳(汁物は最後など)
- 適切な食器の使い方(お皿・お椀・箸・スプーンなど)
- 盛り付け方
- 目安となる分量
- 配膳し忘れはないか
特に盛り付けや目安となる分量は、担任の先生が率先して手本となって指導していきます。
盛り付けが上手な子のやり方を動画に撮り、みんなで見合うのも効果的です。
T「Aさんのしゃもじの使い方が上手です。どこが上手だろう?」
C「持ち方が良いんじゃないかな?」
C「ご飯を掘り起こすようにしているよ」
T「Bさんは給食の運び方が上手です。何が大切かな?」
C「こぼさないように運んでいる」
C「静かに運んでいる」
C「周りがうるさいと危ないかも」
自分たちの配膳する様子を見ていくと、配膳するときに大切なことに子どもたちが気付き、お互いに気をつけ合うようになります。
食事中の指導ポイント
食事中は、学級全体を見渡しながら、以下の点を中心に子どもたちの様子を見守るようにしましょう。
食事の偏りや不足
子どもが栄養バランスの取れた食事をしているかを確認します。
特定の食材を残している場合、アレルギーや嫌いな食材があるか、もしくは食べ方に困っていることがないか気にかける必要があります。
また、適切な量を食べているか、食べ残しが多い子がいないかも確認します。
過剰に食べ過ぎている子や、食事量が少ない子には声をかけることが大切です。
食事マナー
子どもたちが適切なマナーで食事をしているか確認します。
例えば、食べ物をこぼさずに食べているか、ナプキンを使ったりしているかなどです。
食事中におしゃべりが過ぎないようにしたり、他の子どもたちと楽しく会話をしたりしているかを見守ります。
食事の進行状況
あまり早く食べ過ぎている子や、逆に遅く食べている子がいないか確認します。
急いで食べるとむせたり、逆にゆっくり過ぎて冷めてしまうこともあるので、バランスよく進められるよう指導します。
食べる量や食べる速さは子どもによってそれぞれです。
家庭環境も子どもたちの食べ方に影響しています。
子どもたちの背景にある状況に配慮し、過度なプレッシャーを与えないように指導しましょう。
アレルギーや食べ物の制限
事前にアレルギーや食べられない食材がある子どもがいれば、その子どもが安全に食事を取れているかをチェックします。
食事に対して不安を感じている子がいないかを確認し、必要に応じて対応をします。
全体の雰囲気
子どもたちが仲良く食べているか、または一人で孤立している子がいないかを気にかけます。
給食の時間が楽しく、リラックスできる雰囲気であるかを意識し、子どもたちに積極的に声をかけて、食事を楽しめる環境を作ります。
個別の状況に対応
食事中に気になること(例えば体調不良や食事に関する悩み)を抱えている子がいないか、表情や行動からサインを読み取ることも重要です。
片付け指導のポイント
給食の片付けは、ただの作業ではなく、食事を終えた後のマナーや協力の精神を養う大切な時間です。
以下を指導していきます。
汚れた食器の扱い
汚れた食器をきちんと持ち、他のものに触れないように気をつけます。
食器を置く際にも、しっかりと食べ残しを捨ててから片付けをすることを指導します。
食器や道具を大切に扱う
食器を乱暴に扱わないように、慎重に運ぶことを教えます。
割れやすいものもあるので、「落とさないように注意する」「食器の中身をよく捨てる」などの基本的なことを守らせます。
食器は重ねて運ぶ場合もありますが、無理に重ねすぎないように、バランスよく重ねて運ぶ方法を教えます。
整理整頓と順番
残飯、プラスチック、紙など、ゴミをきちんと分別するように指導します。
ゴミ箱の位置を把握させ、決められた場所に捨てるよう促します。
片付けは一度にすべてを行うのではなく、決められた順番で行うようにします。
例えば、食器類→ゴミ捨て→テーブル拭きの順番で、段階的に行うようにします。
協力して片付ける
片付けは一人でやるものではなく、みんなで協力して行うことを強調します。
班ごとに分担し、効率的に片付けが進むように指導します。
机や椅子の整理
食べ物がこぼれた場所をきれいに拭くように指導します。
テーブルクロスが使われている場合も、汚れを確認し、丁寧に拭き取るようにします。
時間内に片付けを終わらせる
片付けを適切な時間内に終わらせることを心がけます。片付けが長引くことなく、次の活動に支障が出ないよう、スムーズに進行することを意識します。
片付けの目安となる時間を設定し、その時間内に終了できるように導きます。
栄養指導のポイント
食に関する知識や栄養の学習は、栄養教諭をゲストティーチャーに招いて授業するとよいです。
担任の先生ではなく食のスペシャリストから学ぶ特別感は、子どもたちの印象にもよく残ります。
また、紙芝居や絵本の読み聞かせも低学年の子どもたちにはわかりやすく、少し難しい食のお話も印象に残りやすいです。
栄養指導と合わせて、食への感謝を表現する活動も重要です。
「いただきます」や「ごちそうさまでした」の意味を話し合い、「食事を作ってくれた人にありがとう」という気持ちを持つように指導します。
まとめ 手、声、目をかける
低学年の給食指導は、最初は手をかけることが多いです。
特に1年生は、給食の配膳や片付けなどは初めての経験ですので、担任の先生が見本を見せたり、声をかけて指導していく必要があります。
慣れてきたら子どもたちの力で給食活動ができるように少しずつ声と目をかけていく段階に移行していきたいですね。
執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。


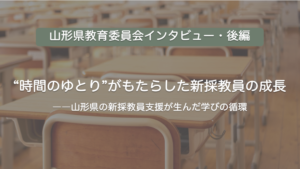






コメント