1 はじめに
近年、低学年でも学級が荒れるケースが増えています。
2024年に発表された文部科学省の調査によると、2023年度の小学校での暴力行為の発生件数は前年度比8554件増の7万9件でした[注]。
学年別に見ると特定の学年が突出しているわけではなく、低・中・高学年どの学年でも暴力行為が発生しています。
先生方は低学年でも子どもたちが荒れる可能性があることを認識し、適切な指導・対策をすることが求められます。
今回の記事では、低学年の荒れの原因と荒れへの具体的な対策について解説します。
[注]文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf)
2 低学年の学級が荒れる主な原因
まず初めに、低学年の子どもが荒れる原因を解説します。
(1)自己コントロールが未発達
自己コントロールとは、自分の感情や行動を適切に調整する力ですが、低学年の子どもたちはまだこの力が十分に発達していません。
そのため、思ったことをすぐに口に出したり、衝動的に行動したりすることが多く、授業中に席を立ったり、大声で話したりするケースも見られます。
また、自分の気持ちをうまく言葉で表現できず、友達とのトラブルにつながる場合もあります。
さらに、注意を持続させるのが難しく、先生の指示を最後まで聞かずに行動したり、できないことにイライラを募らせたりします。
(2)生活習慣の乱れ
十分な睡眠が取れていなかったり、朝食を抜いていたりすると、子どもは集中力が続かず、落ち着きのない行動をとりやすくなります。
夜更かしの習慣があると、朝の目覚めが悪く、学校に行くこと自体が億劫になり、遅刻や忘れ物が増える場合もあります。
イライラしやすくなり、そのイライラを先生や友達にぶつける子もいます。
また、家庭でのしつけが十分でない場合、挨拶やルールを守る意識が低くなり、授業中の私語や立ち歩きが起こって学級の荒れの芽が生まれてしまうこともあります。
(3)人間関係の未熟さ
人間関係の未熟さも、低学年の学級が荒れる原因です。
低学年の子どもは、まだ相手の気持ちを深く考えることが難しく、自分中心の行動をとりがちです。
そのため、友達との些細なトラブルが頻発し、口げんかや手が出る場面が増えやすい傾向にあります。
また、相手の気持ちを傷つける言葉を無意識に発することもあり、人間関係の摩擦が生じやすくなります。
深刻な場合は「仲間外れ」や「特定の子をからかう」といった行動も見られます。
(4)指導方法のミスマッチ
子どもは一人ひとり性格や学習のペースが異なります。
先生の指導方法が子どもたちの発達段階や特性に合っていないと、授業に集中できず、落ち着きのない行動をするようになります。
一方的な説明が多すぎると集中力が続かず、私語や立ち歩きが増えることがあります。
先生方の指導が学級の荒れを生んでしまう可能性もあるのです。
その他にも、厳しすぎる指導は子どもたちの委縮や反発を生み、逆に指導が緩すぎると学級の規律が乱れやすくなります。
成功体験を積む機会が少ないと、子どもたちはやる気を失い、不適切な行動をとることがあります。
3 低学年の学級の荒れを防ぐ効果的な対策

(1)教室の環境づくり
子どもたちは環境の影響を受けやすいです。
整理整頓された安心できる教室を目指しましょう。
落ち着いた学級づくりにつながります。
掲示物を工夫し、ルールや約束事を視覚的に分かりやすく提示して、子どもたちが自然とルールを意識できるようにします。
温かみのある装飾や子どもたちの作品を掲示し、教室・クラスに愛着を持たせ、居心地の良い空間を作りましょう。
また、先生方がこまめに教室の雰囲気を確認し、変化があればすぐに対応することも必要です。
快適な教室環境に整えると、子どもたちは安心して学び、落ち着いた行動をとるようになります。
(2)ルール・約束の明確化と徹底
ルール・約束の明確化と徹底は、学級の秩序を保つために不可欠です。
低学年の子どもたちは、ルールを理解し、守る力が完全に身に付いていません。
そのため、最初にルールをわかりやすく説明し、何を守らなければいけないかを明確にすることが大切です。
例えば、授業中のルールや、友だちとの接し方について具体的な例を挙げて説明し、徹底して守らせていきます。
ルールを守れたときには積極的に褒め、子どもたちに成功体験を積ませていきましょう。
ルール違反があった場合は、ブレずに一貫した対応をします。
子どもたちに「なぜそれがダメだったのか」を説明し、次回から守ろうという意識を育てていきます。
家庭とも連携してルールを共有することで、子どもたちの行動が安定し、学級内のトラブルが起こりにくくなります。
(3)コミュニケーション力を育てる活動
コミュニケーション力を育てる活動は、学級の荒れを防ぐのに即効性はないものの、長期的に見て効果が高いです。
低学年の子どもたちはコミュニケーション力が不十分なため、日常的に、意図的にコミュニケーションの練習を取り入れましょう。
ペアでの会話練習やグループの話し合いを通じて、相手の意見を聞く姿勢や、自分の意見を言葉で伝える力を育てます。
「目を見て話を聞く」「話し手に体を向ける」「相づちを打って聞く」などのコミュニケーションスキルを教えていきましょう。
そして、コミュニケーションスキルを実際の生活場面(あるいは授業)で使っていたら、積極的に称賛していきます。
そうすることで、子どもたち同士が対話を大切にし、相手を尊重する態度や、共感力を高められます。
学級内のトラブルが減り、円滑な人間関係を形成できるでしょう。
(4)生活習慣の見直しをサポート
低学年の子どもたちにとって、規則正しい生活は学習や行動に大きな影響を与えます。
先生や保護者は、子どもが十分な睡眠を取れるように支援し、朝食をしっかり摂る習慣をつけさせていきましょう。
また、就寝・起床時間を一定に保つことで、子どもたちの心身の健康を支え、集中力も高まりやすくなります。
養護教諭や栄養教諭をゲストティーチャーに招いて睡眠や食の大切さを学ぶ授業をしたり、早寝・早起き・朝ごはんチェックシートを用意したりし、生活習慣の見直しをサポートしましょう。
学校と家庭で協力して、生活リズムや食事、運動の重要性を教え、子どもたちが自分で意識的に生活習慣を改善していけるようにサポートすると良いです。
(5) 子どもとの関わり方を見直す
低学年の子どもたちは、先生との関係が学習や行動に大きな影響を与えます。
子どもたち一人ひとりをよく観察し、個々の性格やニーズに応じた関わりを持つスキルが低学年の先生には特に必要です。
自己主張が強い子には意見をよく聞き、控えめな子には自信を持たせるような声を積極的にかけます。
また、子どもたちが感情を適切に表現できるよう、共感的な姿勢を示すことが大切です。
子どもたちが感情的になったときには子どもたちの声をしっかり聞き、冷静に対応しましょう。
落ち着いた対応が、先生と子どもたちの間に信頼関係を生みます。
先生方が一貫して穏やかで優しい対応を心がけ、子どもたちが安心して自分を表現できる環境を作り、学級の荒れとなる原因を排除していきましょう。
4 おわりに
低学年の学級が荒れる背景には、子どもたちの発達段階や生活環境、指導方法の影響が関係しています。
しかし、適切な環境づくりやルールの徹底、コミュニケーション力の育成など、先生方の工夫次第で落ち着いた学級を築くことができます。
日々の小さな積み重ねが、子どもたちの成長につながります。
ぜひ今回の内容を参考に、先生ご自身の学級に合った対策を取り入れてみてください。
子どもたちとともに安心して過ごせる学級づくりを目指しましょう。
執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。


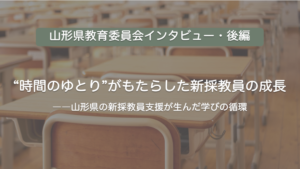






コメント