1 はじめに
卒業式は、子どもたちにとって小学校生活の集大成となる大切な節目の行事です。
小学校での成長を振り返り、友達や先生、家族へ感謝の気持ちを伝える場でもあります。
しかし、卒業式を単なる「儀式」と考えてしまっては、子どもたちの心に深く刻まれません。
卒業式を子どもたちの成長チャンスと考え、参加する全ての人が一体感を持った感動の卒業式を6年生の先生方は目指してほしいです。
本記事では、一体感のある卒業式を実現するための指導のステップと成功のポイントについて解説します。
子どもたちも先生方も「やってよかった」と心から思える卒業式をつくっていきましょう。
2 一体感のある卒業式とは?
一体感のある卒業式とは、子どもたち、保護者、教職員が心をひとつにし、共に感動を共有できる卒業式です。
ただ決められた流れに沿って進めるのではなく、一人ひとりが卒業式の意義を理解し、主体的に関わることで、その場にいる全員の心がつながります。
特に卒業生(6年生)には一つ一つの所作に心を込めることを伝えます。
卒業証書の受け取り方、呼びかけでの感謝の伝え方、歩き方から椅子の座り方まで、一つ一つに心を込めることで、参加者に「成長した姿」や「感謝」が伝わります。
在校生はその卒業生の姿を目に焼き付け、最高学年のバトンを受け継ぎ、教職員はこれまでの教育活動の成果を振り返ります。
そして、保護者はお子さんとの6年間の苦楽を思い起こし、お子さんの成長を実感します。
こうした心のつながりが生まれる卒業式は、一体感が生まれ、参加者全員の心に刻まれる卒業式になります。
3 卒業式指導のステップ

(1) 卒業式の目的を話し合う(1ヵ月前〜)
最初の卒業式指導は、「卒業式の目的」を子どもたちと話し合うことです。
「なぜ卒業式をするのか?」「誰のために卒業式をするのか?」を子どもたちと共に考えていきます。
在校生として過去の卒業式に参加したことがあればその記憶をたどり、参加したことが無ければ過去の卒業式映像を見て、「卒業式の目的」を考えていきます。
もし中学生に話を聞く機会があれば、体験談を聞いてもよいですね。
子どもたち自身で「どんな卒業式にしたいか」「その卒業式に向かって何を頑張るか」を明確にしていくと、主体的に卒業式の練習に参加する態度を育てることができます。
(2)所作や式の流れを指導する(3週間前〜)
目的を確認したら、式に必要な所作と大まかな式の流れを指導していきます。
起立・礼・着席の所作は全員が揃うようにし、一体感を形成できるように指導します。
「起立・礼」の号令からいくつ数えて体を起こすかを確認しましょう。
卒業証書の受け取り方は、学校によって所作が異なります。
特に「どちらの手足を先に動かすか」「礼はどのタイミングでするか」は、初めのうちに確実に指導しましょう。
間違った所作を教えてしまうと、癖になってしまい修正するのが大変です。
呼びかけや合唱は、自分たちの言葉として伝えられるように指導します。
(3)動き心を合わせる(1週間前〜)
全体練習を通して、式の流れを確認します。
仕上げの時期に大切なのは、心を合わせることです。
所作はもちろん、呼びかけも合唱も気持ちを込めて練習するように声を掛けていきます。
「背筋がピンと伸びて良い姿勢です」「声が響いていてさすが最高学年」と良い点をどんどん褒めていき、子どもたちの気持ちを高めていきましょう。
(4)最終確認と気持ちの準備
子どもたちが「卒業式をどう迎えたいか」を考える時間を作ります。
最後の通し練習では「一緒に卒業する」という意識を高めていきます。
そして、先生方から励ましの言葉をかけ、安心感を持たせて卒業式に臨めるようにしましょう。
また、体調が悪くなった場合やトイレに行きたくなった場合などのアクシデントへの対応方法も伝えておきます。
4 一体感を生む成功のポイント
(1)子どもたちが主体的に取り組める環境を作る
子どもたちが練習に主体的に取り組んだ卒業式は一体感があります。
「やらされている」「儀式」といった印象がなく、「感謝を伝えたい」「成長した姿を見せたい」といった子どもたちの心が見えるからです。
先生主導ではなく、子どもたちが考え、動く機会を増やすようにしていきましょう。
そのために、卒業式実行委員会を作ります。
実行委員は練習の進行や練習前後のコメント、クラスでの話し合いを指揮します。
例えば練習前に、「3回目の卒業式練習を始めます。今日は卒業証書の受け取り方を全クラス通して練習します。歩き方や受け取り方が雑にならないように、一つ一つの動きに心を込めて練習しましょう」といった実行委員の言葉で練習を始めていきます。
先生が言うよりも子どもたちが言う方が意識が高まります。
また、自分たちが目指す卒業式に向けてやるべきことをリストにし、教室に掲示するのも有効です。
先生方は卒業式実行委員へのアドバイス・フォローになるべく徹し、必要最低限の指導にとどめます。
(2)形式的ではなく、心を込めた式にする
卒業式の所作は、繰り返し練習していると飽きが生まれてきます。
機械的な所作になり、少しの雑な動きが気になってきます。
そのようなときは、「なぜこの所作が必要なのか?」「どんな卒業式にしたいか?」を子どもたちに問い、卒業式の目的を確認しましょう。
胸を張って堂々と歩いたり、所作がそろったりする最高学年の姿が、在校生や親御さんの目に焼き付き、伝統が受け継がれることを伝えましょう。
「自分たちの卒業式だけれど、在校生・保護者・学校のための卒業式でもある」という、他の視点を与えることで、より心を込めて練習しよう意欲が高まります。
また、呼びかけや合唱は言葉の意味を考えながら練習できるようにします。
「はばたく」や「ありがとう」といった言葉を単なるセリフではなく、自分の言葉として伝えられるように指導していきましょう。
(3) 友達や先生との思い出を振り返る時間を作る
卒業式直前に「6年間の思い出」を共有する時間を設けます。
共に過ごしてきた思い出を振り返り、子どもたちは成長を実感したり、友達の良さに気付いたりし、小学校卒業の実感がじわじわと湧いてきます。
クラスメイトや先生、親御さんへの感謝の気持ちを手紙に書く活動も、6年間のあゆみを振り返るのにおすすめの方法です。
(4)先生自身も「一緒に卒業する」気持ちで関わる
子どもたち主体の一体感ある卒業式を実現するには、先生方の関わり方が重要です。
「指導する」という意識を薄め、「一緒に最高の式を作る」という意識で子どもたちの練習を見守っていきます。
ときには、子どもたちの様子や態度にいろいろと言いたくなる場面もあります。
しかしグッとこらえて、子どもたちに気付かせたり、言いたいことを実行委員に言ってもらうなど、子どもたちが「主」になるように立ち回りましょう。
こうした、先生方の意識や態度が、子どもたちへの頑張りにも影響します。
5 まとめ
卒業式は子どもたちが小学校生活を締めくくる大切な場です。
本記事で解説した指導のステップを踏み、子ども主体で一体感のある卒業式を実現していただければと思います。
「気持ち」が成功のポイント。
子どもたちと共に「最高の卒業式」をつくっていきましょう。
6 執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。


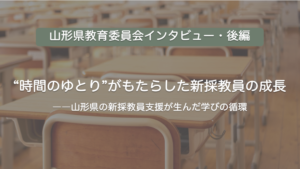






コメント