1 連絡帳を使って
子供の学校での様子というのは、思ったほど家庭に伝わっていないことがあります。子供が無口である場合、子供が連絡物を親に渡さない場合、親が多忙であったり無関心であったりする場合などで、連絡がつきにくい家庭があります。
外国では家庭と学校は全く連携していないと考える国も多いようですが、日本では家庭との連携には力を入れた方がうまくいくことが多いです。
通常は学校便りや学級通信、学期末の通信簿やあゆみでの所見、家庭訪問・学級懇談・個別懇談といった家庭とのコミュニケーションをとる手段があります。
これに加えて、連絡帳を使うという手もあると思います。子供がちょっとした成長を見せたことを、連絡帳に書いてあげることができると、親は楽しみにしますし、連絡帳を見るようになるので忘れ物や事務連絡にも注意を払ってくれるようにもなります。「九九を全部言えました」「新しい友達ができて、楽しそうです」「音楽専科の先生が褒めていました」などといった些細であっても、プラスな情報を伝えられるといいと思います。
ところが、日々忙しくしていると、そんなことでもなかなか連絡帳に書くというのは難しいです。褒めることが多い子供はいいのですが、そうでない子供はついつい後回しになってしまい、書く回数が少なくなってしまうこともあります。そこで私は、名前が入った短冊を全員分作って、机の中に入れています。全員書けたらまた全員分作ります。朝の会や終わりの会といったタイミングで、その短冊を日々、少しずつ子供に渡します。渡された子供はそれを連絡帳に貼ります。
子供に渡すときに、ちょっと口でも褒めてあげれば、家に帰ってまた親にも褒められるので、子供は2倍得した気分になります。こうして「プラスの関係作り」をしていくとクラス全体の雰囲気が良くなっていきます。親も喜んで、「ちょっと安心しました」などと返事を書いてくれることが多いです。
通信簿や懇談で、学期末にまとめて家庭とのコミュニケーションをとるのではなく、日々の中に少しずつのつながりを作っていくというのも大切です。WinWinの関係を築きましょう。
2 ICTを使って
児童全員にGIGA端末が配られ、家庭のICT環境も整ってきました。これらを用いてメールやメッセージをを送るのもいいかもしれません。これも、全員にもれなく送る形を作るのが大事です。勤務校でのルール作りが必要である場合がほとんどだと思います。管理職と相談して、職員会議に提案する機会を得ましょう。全員の親と双方向でのやり取りをするのは大変なので、
「原則一方通行です。返信をいただいてもそれにまた返信する余裕はありません。」
などと、断わっておかないと、「一対多」の状況で返信を期待されて教師側がしんどくなってしまうので、要注意です。「特に気になる子供の保護者限定」でやるのもいいかもしれません。とはいうものの、多忙化が進む中、たくさん発信するのは難しいです。私も低学年を担任したときしかやったことがありません。できれば1か月で全員に発信するぐらいのペースで十分だと思います。
・
EDUPEDIAでは、「褒める」について書かれた記事がたくさんありますので、是非、キーワードで検索してみて下さい。
・
EDUPEDIAには「ほめる」「褒める」をキーワードにした記事がたくさんアップされています。ぜひ「褒める」「ほめる」をキーワードにしてサイト内検索をしてみてください。

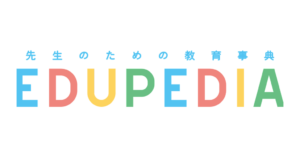



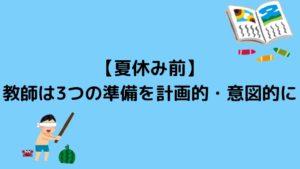

コメント