保護者会は、保護者のために開かれる学校行事です。
教員や子どもたちにとってではなく、保護者が学校に足を運んだ価値を感じてもらうことが最も重要です。
そのために、保護者が「学校に来て良かった!」と感じるような内容を提供していきます。
保護者が有益だと感じる情報を提供して、保護者と学校のつながりを深める保護者会にしていきましょう。
保護者会は単なる報告会ではなく、保護者と学校が一緒に子どもたちを育てていくための重要なステップです。
ここで得られる情報や感動が、家庭での会話や子育ての参考になることを意識して、保護者会を構成していきましょう。
年度初めの保護者会は担任の所信表明から

年度初めの保護者会は、担任の先生が学級経営の所信表明をする絶好の機会です。
保護者は、これからの一年間で子どもたちがどんな学びを得るのか、どんな成長をするのかについて大きな関心を抱いています。
この場を活用して、学級経営の方針や1年間の行事について話すことで、保護者と学校の共通理解を深め、協力し合う意識を醸成できます。
学級経営方針
学級経営方針では、1年後にどんな子どもに育ってほしいのか、どんな学級にしていきたいのかを明確に伝えます。
具体的な目標を設定し、保護者にその達成に向けた協力をお願いすることが重要です。
例えば、「子どもたちが自分で考えて行動できるような学級を作りたい」といった目標を掲げ、そのためにどのような活動や取り組みが行われるのかを説明します。
保護者は担任の考えや教育方針を理解し、自分たちがどう協力できるかを考えることができます。
1年の学校行事
1年間に行われる学校行事については、ただの日程の報告ではなく、各行事が持つ意味や価値についても触れます。
運動会や学芸会、遠足といった行事は、子どもたちにとって大切な学びの場です。
それぞれの行事がどんな形で子どもの成長を促すのかを保護者に伝えることで、行事の重要性が理解され、家庭での協力もしやすくなります。
持ち物やルールの確認
学年ごとに必要な学習用具や学校生活のルールについても確認します。
保護者と学校が共通の理解を持ち、子どもたちがスムーズに学校生活を送れるようにするためです。
また、持ち物やルールについて、家庭でどのようにサポートできるかも伝えましょう。
宿題や家庭学習への協力
宿題や家庭学習に関しては、目的やねらいを保護者に理解してもらうことが重要です。
宿題は単に「やらせる」ことが目的ではなく、学びを定着させるための大切な時間であることを伝えます。
自主学習の意義や、家庭でどのようにサポートしてほしいのかについても話すと、保護者の協力が得やすくなります。
保護者が一番知りたいのは子どもの様子
保護者会で最も関心が高いのは、子どもたちが学校でどのように過ごしているかです。
保護者は自分の子どもがどのように成長しているのか、どんな良い点があるのか、またどんな部分を伸ばしていきたいのかを知りたいと考えています。
子どもたちの様子
子どもたちの良さを伝えることは、保護者にとってうれしいことです。
具体的なエピソードを交えながら、子どもたちがどんなところで成長を見せているのかを伝えましょう。
また、これからどのように伸ばしていきたいのかも共有することで、保護者が家庭での支援を意識しやすくなります。
写真や動画で伝える
言葉だけでは伝わりにくい部分も多いため、写真や動画を活用すると良いです。
実際の授業風景や子どもたちの活動の様子を視覚的に見せることで、保護者は子どもたちの学校生活をより実感しやすくなります。
個別よりかは、学級のエピソードを語る
保護者会では、個別の話よりも学級全体のエピソードを中心に語りましょう。
個別の子どもの話は、個人面談で詳しく行うべきです。
クラス全体での成長や活動の様子を語ることにより、多くの保護者の共感を得やすくなります。
語るエピソードは
語るエピソードとしては、子どもたちが成長した瞬間や、他の先生に褒められたこと、クラスで協力して取り組んだプロジェクトなどが適しています。
保護者は子どもたちの社会性やチームワークの向上を感じ、学校生活に対する信頼感が増します。
学年によって変わる話すこと
学年が進むにつれて、保護者が関心を持つ内容も変わります。
低中学年では成長や安全面、高学年では思春期に関連する問題が話題になります。
学年に応じて、話す内容を工夫していきましょう。
低中学年は子どもの成長や安全面を中心に
低学年や中学年では、子どもたちの学習面の成長や、日々の安全に関する話が中心になります。
子どもたちがどのように学び、生活しているか、また家庭でどうサポートできるかについて伝えることが大切です。
高学年は思春期の特性を話題に
高学年では、思春期の子どもたちに関連する話題が増えます。
特に、スマホやSNS、お金に関する課題については保護者にとって大きな関心事です。
これらの課題について、学校と家庭がどう協力して対処していくかを話し合うことが重要です。
良いことだけではなく、気をつけてほしいことを共有する
良いことだけでなく、気をつけてほしいことについても共有します。
子どもたちの成長において、注意すべき点やリスクを保護者と共有し、どのように対処していくかを話すことが、子どもたちの安全を守るためには欠かせません。
保護者も話す工夫を
保護者会は、先生だけでなく、保護者同士が交流する場でもあります。
保護者同士が意見を交換し、子育てに関する情報を共有することで、さらに充実した会になります。
質疑応答
質疑応答の時間を設けることで、保護者が気になることや不安に思っていることを解消できます。
質問に対して、わかりやすく丁寧に回答することが、保護者との信頼関係を深めるポイントです。
グループトーク
グループトークを活用すると、保護者同士が気軽に話しやすくなります。
少人数でのディスカッションを通じて、共通の悩みや意見を交換できる場を提供することが重要です。
サイコロトーク
サイコロトークは、参加者の緊張をほぐし、積極的に意見を話すきっかけを作ります。
サイコロを振って、出たテーマについて話すことで、自然に会話が広がり、保護者同士のつながりが深まります。
まとめ
保護者会では、保護者の満足感を最優先に考え、有益で感動的な情報を提供することが求められます。
保護者が学校とのつながりを感じ、家庭での会話が自然に生まれるように工夫していきましょう。
保護者会は、教員と保護者が一緒に子どもたちを育てていくための重要なステップです。
子どもたちの成長を支える力強い支援を提供できる場であることを意識していきましょう。
執筆者プロフィール
マー
小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。

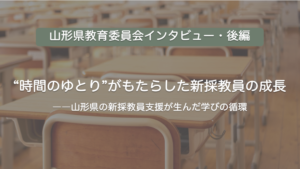







コメント