1 はじめに
平成26年9月6日に行われた、「クラスづくりセミナーin京都」を取材させていただきました。この記事では、セミナーで講師としてお話された、松森靖行先生の学級経営について紹介します。
2 大切にすること
①目標を明確化させる。
『一年の最後、どういうクラスにしたいか』ということを明確にして、一年間の学級経営を考えることが大切です。
②日常生活を大切にする。
学校生活の大半は、日常生活です。その日常生活こそを大切にすることで、学級経営は成り立ちます。クラスマネジメントは、子どもの安心を保証する管理だといえます。
3 そもそも論
当たり前にしていることを「そもそも」何のためにやるのか、やる意味があるのか、疑ってみることが大切です。疑うとは、それが「大人になって生きて働く力」となるかどうか立ち止まって考えてみるという意味です。いくつか例を挙げてみると、挨拶、音読、配膳などが挙げられます。しかし、やりたいと思ったことが、「大人になって生きて働く力」となるかどうかわからないこともあります。そのようなときはまず、やってみることです。いろいろ試してみるうちに、教えるべきではないこと、やっても意味がないものは、淘汰されていきます。そうして、自分の実践が出来上がっていくのです。
こうして出来上がった松森先生の実践の核となるものは「思いやり」を中心として考えるということです。「なぜ勉強するの?」というのも、思いやりをもつためと言えます。心を豊かにするためと言えます。思いやりも教えないと身につかないものです。全てを「思いやり」を核として日常に少しプラスを加える、というのが松森先生の学級経営です。
4 授業経営・子どもを「ゆさぶる」方法
ここで、日常に少しプラスを加える例を一つ紹介します。
授業中、子どもを「ゆさぶる」ことも、大切です。その方法は、まず教師がわざと間違ったことを言ったり、失敗したりします。すると、子どもたちに指摘されます。そこで、「わからない」「なんで違うの?」と、子どもたちに質問を返します。つまり、子どもたちから正しい意見が出ても、「なぜ」を繰り返すのです。こうすることで、子どもたちが意見を言うようになり、話し合いが進みます。
5 編集後記
日常にこそ、工夫できるポイントがたくさんあるということ、その一つ一つについて、教える価値を問い直す必要があるということをこの実践で学びました。この日常の工夫や価値を問い直す姿勢によって、先生それぞれの、オリジナルの実践が出来上がっていくのだろうなと思います。
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 森七恵)
6 実践者プロフィール
松森 靖行 先生
1976年 岡山県生まれ。岡山大学教育学部卒
2013年まで岡山県小学校教員
2014年より大阪府小学校教員
岡山県の浅口市では、市全体若手研修を担当、月1回の教師塾の立ち上げを担当。
現在、寝屋川市立木屋小学校で3年生担任、若手教員研修担当
木屋教師塾塾長
MY KOHAN大阪事務局
「思いやり」を中心にした学級経営
「楽しみながら鍛える」授業論を展開。週末は各地のセミナーに講師として
そして、受講生として参加。
内田洋行「学びの場.com」で教育論、実践論を執筆中。
明治図書「THE 教師力」シリーズ 『3D理論で学級が変わる』(土作彰編著)
中村堂『徹底反復でクラスが変わる』(徹底反復研究会中国支部編著)
黎明書房『爆笑クラスの作り方12か月』(中村健一編著) など
各教育雑誌に共著、執筆多数。
授業力アップトーナメント関西大会にて優勝。
現在、初の単著を明治図書より執筆中。

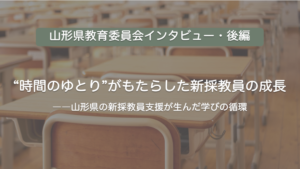





(後編)-1-300x169.png)
(後編)-300x169.png)
コメント