はじめに
本記事は、2025年1月発売の『本当は大切だけど、誰も教えてくれない 子ども対応 35のこと』(明治図書出版社)について、著者の大前暁政が皆さまに紹介する記事となっております。
書籍について
◎概要
本書は、「子ども対応」に関して「理論」と「方法」を解説したものです。
最初に、「具体的な事例」を紹介しました。「具体的な事例」は、「手痛い失敗例」となります。その「失敗例」から何を学び、子どもにとってよりよい対応にするにはどうしたらよいのか解説しました。
◎類書との違い
最大の違いは、「理論」と「方法」をセットで解説したところです。
私たち教師は、実は、「子ども対応」に関して「体系的に学ぶ」ことをしてきていません。自らの経験と価値観で、日々「無意識に」子ども対応を行っていることが多いのです。本書が類書と決定的に違うのは、「重要な知識」に絞り、かつ、体系的に示したところです。
◎こんな先生に読んでほしい
「子ども対応」に関して、網羅的に、全て学びたいという人には、必読の1冊となります。子ども対応に関する「最新の研究の知見」と共に、先人が築き上げてきた「不易として重要な知恵」も学び、日々の子ども対応を充実させてほしいと思います。
特に重要なのは、「理論」と「方法」をセットで知ることです。本書は、学校関係者だけでなく、「子どもに日々対応している」全ての人に読んでほしいと願っています。
一部を紹介!
本書の骨格部分を紹介します。
①「子ども対応」をしていく上で、大切にしたい考え方とはどのようなものでしょうか?
教員研修では、「子ども対応」に関して学ぶ機会は大変少ない現状があります。
また、「子ども対応」に関して、網羅的に、理論と方法を示した書籍も少ないのが現状です。
その結果、理論と方法を学ばないまま、教壇に立つことになってしまうのです。
各教師は、理論と方法を体系的に学ぶことのないまま、自らの経験と価値観に従って、日々、子ども対応をしています。 このことの一番の問題点は、「無意識」であることです。
自分の対応がよいのか悪いのか、判断する視点がないわけです。
だからこそ、私たち教師は、そして、子ども対応をしている全ての大人は、どんな対応がよくてどんな対応が悪いのか、その理論と方法をセットで学ぶ必要があるのです。
そうすれば、「よりよい子ども対応」に関して、自分の対応がよいかどうかの評価の視点を得たことになります。
この評価の視点をもって、自らの対応を振り返ることが必要になるのです。
②具体的に、子ども対応に関してどのような内容を学ぶ必要があるのでしょうか?
本書では、例えば、次のような内容を紹介しています。
・子どもの実態調査の落とし穴と、実態調査の本当のやり方とは?
・子どもが見えなくなるのはなぜか?どうしたら見えるようになるのか?
・情熱と愛情をもっていても、子どもが荒れるのはなぜか?
・「こういう子どもだ」と思うと、本当にその通りになるのはなぜか?
・「無意識の教育行為」を、意識化するためにはどうしたらいいのか?
・対応するほど、頑張る子どもが少なくなっていく理由はなぜか?
・なぜ教師の教育行為が、子どもに響かないのか?効果を発揮しないのか?
・子ども対応の「即効性」と、「遅効性」とは何か?
・「マイナスからの0対応」と、「0からのプラス対応」では、何が異なるのか?
・子どもが変わるまでに意識すべき「教師の対応の順序性」とは何か?
例えば、親身に、丁寧に、時間をかけて、子ども対応をしている教師が現場には数多く存在します。
心から子どもの成長を願い、真摯に子ども対応を行っているわけです。
ところが、親身に関われば関わるほど、対応に時間をかければかけるほど、荒れはひどくなっていくという現象が見られます。
この現象にも理由があります。
親身だろうが、情熱があろうが、時間をかけようが、対応の理論と方法に合致しないやり方で対応してしまうと、それは裏目に出てしまうのです。
例えば、どうしてもやる気の出ない子、頑張れない子に、「やる気を出させよう」と思っても、子ども対応の理論と方法を知らないと、まったく見当違いの対応になってしまうのです。
個別に対応すればするほど、上手くいかないのなら、そもそも、子どもが見えてない、子どもの問題行動の原因を勘違いしている、集団や環境への指導を怠っているなど、様々な反省すべき視点があるのです。
子ども対応の理論と方法をセットで知ることで、初めて私たちは、その理論と方法を視点として自らの教育行為の反省が可能になるのです。
③なぜ「手痛い失敗例」を紹介することが重要なのでしょうか?
本書では、まず「手痛い失敗例」が出てきます。
この「手痛い失敗例」を学ぶ意味は何でしょうか?
実は、教師の多くは、同じような失敗の道を辿ってきています。
毎年毎年、新しい教師が誕生していますが、皆似たような失敗の道を歩むことになるのです。
それは、「失敗例」が、教師の世界で共有されていないからです。
こんな代表的な「子ども対応の失敗例がある」ということを、誰も教えてくれないのです。
だから、失敗してみて初めて「このやり方では、子どもは何も変わらない」、「このやり方では、子どもに悪影響すらある」ことに気付くのです。
いや、下手をすると気付くことすらできないかもしれないのです。
なぜなら、子ども対応の理論と方法をセットで学び、反省の視点を得ないことには、どの教育行為のどこがいけなかったのかを振り返ることすらできないからです。
だからこそ、「手痛い失敗例」を知るだけでも、大きな学び、一生の財産になるはずです。
同じ失敗を避けることができるからです。いわゆる「コピペミス」を防ぐことができるのです。
そして、「手痛い失敗例」から何が学べるのか、そして、どう対応すればよかったのかを、重要な知識に絞って、系統的に、網羅的に紹介しました。
上に示したような知識を、私たち教師がみんな知っていたら何の問題もありません。
ところが、上の内容に代表されるような子ども対応の理論と方法を、私たち教師は、実は教わってきていません。
なぜ、「重要な知識」になればなるほど、誰も教えてくれないのでしょうか?
深掘りした知識は、「重要であればあるほど」、伝達が難しくなるからです。
だからこそ、本書では、次のような工夫をしたのです。
「具体的な対応場面をまず挙げ、そしてその対応の改善策を示す」
④子ども対応に対してもっておきたい考え方や姿勢はありますか?
一番は、子どもにとって価値のある対応になっているのかを、常に振り返る姿勢です。
「子ども理解」1つとってすら、理論と方法を学ばないと、うまく行うことができません。
子ども理解が出発点ですから、対応の出発から躓いてしまうわけです。
子ども対応に対してもっておきたい一番重要な考え方・姿勢は、最新の研究の知見と、これまでに不易として伝わってきた先人達の知恵を、謙虚に学ぶことです。
だからこそ、一人ひとりの子どもに合わせて、臨機応変に、個別に最適な対応ができるようになるのです。
学び続ける姿勢。これが最も重要なのです。
学んだ教師だけが、子どもに合わせて、子どもファーストで、最高の対応ができるようになるのです。
本シリーズは、本書で5作目となりました。既刊書も、教師の本当に大切な知恵に絞って紹介しています。是非、既刊書にも触れてほしいと思います。
既刊書についてのご紹介はこちら
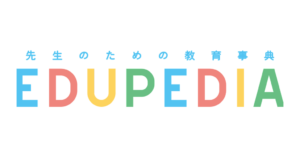

プロフィール

大前暁政(おおまえあきまさ)
京都文教大学こども教育学部こども教育学科 教授
岡山大学大学院教育学研究科(理科教育)修了後、公立小学校教諭を経て、2013年4月より京都文教大学に着任。教員養成課程において、教育方法や理科教育に関する教職科目を担当。「どの子も可能性をもっており、可能性を引き出し伸ばすことが教師の仕事」ととらえ、学校現場と連携し新しい教育を生み出す研究を進めている。文部科学省委託体力アッププロジェクト委員、教育委員会要請の理科教育課程編成委員などを歴任。理科の授業研究が認められ「ソニー子ども科学教育プログラム」や「日本初等理科教育研究会優秀論文賞」に入賞。研究分野は、教育方法、理科教育、学級経営、生徒指導、特別支援教育、科学教材、教授法開発、教師教育など多岐に渡る。
Amazonページ
読者へのメッセージ
学校関係者はもちろんのこと、日々子ども対応を行っている全ての人に、是非本書を贈りたいと思っています。


kai--282x300.jpg)

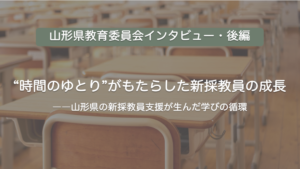






コメント