はじめに
1989年の開業から長きに渡り文化・芸術を発信する「Bunkamura」。
芸術を通して子ども達に残せることとはどのようなものなのでしょうか。
長期休館を機にアウトリーチとして開始された教育分野の活動を軸に、文化や芸術がどのような役割を果たせるのか、そして、「Bunkamura」のこれからについて、株式会社東急文化村執行役員マーケティング統括部統括部長を務める荒木久一郎さんにお話を伺いました。
なお、本記事は、2025年3月13日に行った取材を記事化したものです。
芸術鑑賞会及び日ごろの学校生活での芸術の取り入れ方についてご紹介した後編記事もあわせてお読みください。


「Bunkamura」が行ってきた教育分野の活動
まず、「Bunkamura」は劇場や映画館、美術館で構成される複合文化施設であり、株式会社東急文化村が運営を行っています。それらに加えて、演劇や音楽公演など実演芸術の自主制作もしています。そのため、直接的に学校教育の場に携わるわけではありません。
特に、「Bunkamura」が取り組む芸術鑑賞教室に関しては、我々の立場としては「お客様」です。
「Bunkamura」の活動には教育面も含んではいますが、「児童・生徒・学生をお客様としてお呼びする」という目的でずっとやってきました。しかし、コロナ禍や施設の長期休館を機に、「自分たちが外に出て、今まで直接関わることができなかった方々に何かを届けたり、一緒に何かをしたりする」というアウトリーチ活動「Bunkamuraオープンヴィレッジ」を始めました。
この活動には3つのテーマがあります。育成、地域振興、デジタル技術との融合の3つです。教育にまつわるものはこのうちの「育成」というテーマです。我々からすると、教育よりは「未来の観客をどのように支援できるか」ということを目的にしています。
ただ、当然ながら学校を始めとする教育機関と行うことも多いので、そのときにこちらから提供しているものが、学校側にとっては教育的な価値に繋がっています。
長野県の大日向小・中学校との取り組みでは、実際のアーティストの方をお招きしてのワークショップを行いました。また、東京都中野区にある宝仙学園幼稚園の先生に向けてもプログラムを行っています。先生に対して、ワークショップを行い、アートを通じた物の見方、そういったものを子どもに伝えるときの伝え方など気づきを得ていただいています。東急グループが運営する学童保育「キッズベースキャンプ」でも子どもたちの想像力を刺激する取り組みをしています。
「文化」と「芸術」が子ども達に残せるものとは?
「文化」から異なるものに気づく
前提として、「文化」と「芸術」は微妙に異なるものだと思っています。
「文化」というのは、簡単に言えば、国ごと・民族ごとの違いやその民族が固有に持っているもので、具体的にはサブカルチャーやマンガといったジャンルなどを指します。つまり、「特定の集団がもつ価値観」と考えられると思います。
そして文化とは、異なるものと触れることで認識され、人によって相当認識が変わるものです。例えば、巨人ファンと阪神ファンが話をしていれば、おのずと「どちらの球団がよいのか」という話題になり衝突すると思います。しかし、ここにサッカーが好きな人も加わると、サッカーの良さと野球の良さをそれぞれ語ることになるでしょう。そうすると、先ほどは敵対していた人が同じ立場になって話し合うことになるのです。
異なるものと交わるということについて子ども達の視点で考えると、同じ学年やクラスといった毎日会う人とずっと一緒にいる環境においては当たり前だったことが、学校が変わったり学年が違ったりすると当たり前ではなくなるというのが挙げられます。そういうときに文化というものは、「自分たちが常に正義ではないのだな」と多様性を自覚できる有効なものになると思います。
「芸術」から考える
芸術とは、それぞれの見方を養ったり、異なる価値観と触れ合ったりすることを疑似的に体験することができるものだと思います。例えば、「ヨーロッパの人はこういうものの見方をするのか」「今はないけれど江戸時代はこういうことが当たり前だったのか、どうしてなくなったんだろう」といった気づきは、実際に芸術に触れるから理解できるようになることだと思います。
異なるものを受け入れつつ認めながら、自分の目で見て、自分の頭で考える力を養う営みに意味があると思います。
エンターテインメントと芸術の違い
自分の頭で考えるときに気づきを与えてくれることが、娯楽としてのエンターテインメントと芸術が持つ価値の違いになるかと思います。娯楽としてのエンターテインメントでは、特定の何かに関する熱狂的なファンで、批判的に見る人がほとんどいない状況になります。そういう場において、批判的な人や違う考え方の人がやってくると楽しめなくなったり、それぞれのサポーターが争いになってしまったりする場面も見られます。異なる価値観を受け入れる力を養うべきだと思いますが、なかなかそうはなりません。
しかし、芸術作品は、一つの世代だけではなく何世紀にもわたって受け継がれています。時代を超えて残っているものであるからこそ、多くの人々にとって普遍的で距離の近過ぎない存在なのだと思います。異なる価値観を受け入れる力を養ったり、今の自分や世の中と境遇を置き換えて何かを考えたりすることがしやすいのは、自分と適切な距離を保ちやすい芸術の持ち味だと考えています。
ファスト教養が進む今、「芸術」をどう捉える?
また、「芸術」に対する社会の見方は3つあると思います。
まず、「芸術は娯楽である」という見方です。例えば、クラシックコンサートは芸術だと主張する人もいれば、あくまでも娯楽でしかないと捉えて芸術ではないと主張する人もいます。2つ目は、「芸術には人格形成や道徳的な価値がある」という見方です。3つ目は、「『音楽が人を一つにする』といった、人との繋がりや芸術によって人は感動したり感受性が高まったりして人生が豊かになる」という見方です。
ここで大切なのは、こういった芸術への認識には、正解はないということだと思います。
例えば、コロナ禍や震災に社会が見舞われ、芸術は不要不急だとみなされる際、芸術は娯楽に過ぎないという認識で捉えられているのだと思います。
それに対して、大変なときだからこそ芸術が必要だと主張する人もいます。例えば、東日本大震災のときにあるアーティストが避難所でコンサートをしたら、みんなが涙を流して喜んだり、希望をもらったりしたということもあります。こういった感動は無駄ではないと思います。たしかに、芸術でお腹はいっぱいにはならないですが、心を癒してくれるという面も大事なのだと理解してもらうことが必要です。
手段ではなく、目的としての教養を。
本来は目的であるはずの教養が、手段になってしまっていると感じます。かつて、芸術を含む一般教養は人格形成や人としての価値を高めるものとされてきました。しかし、今はお金を生まないものに価値が置かれなくなって、世の中がディールになっていると感じています。しかしながらそれは本当に良いのかと問いかけたいです。
例えば、映画を観るのに今は2,000円くらいかかることに対して「コストパフォーマンスが悪い」という考え方もあると思います。費用対効果の良し悪しだけに留まらず、学問やビジネスの場においても同じような見方が広がりつつあります。理系に進路を決めた人にとって芸術は必要ないとする考え方までも出てきているようですが、私は違うと思います。一般的な教養はすべての分野で必要であるはずなのに、技術志向に価値を置き、物事の多くを役に立つか立たないかだけで判断するのが本当に自分にとって良いことなのか、一歩引いて考える必要があるように思われます。
大学の一般教養はそのためにあったと思うのです。
「Bunkamura」にいらっしゃるお客様には、「人生を豊かにするものを学びたい」「人としてもう少し自分を磨きたい」というシニア層の方が多くいらっしゃいます。会社をリタイヤされてから大学に行く方がおられるという話もよく聞きます。そういった方は大学で文学を学ぶ方が多いように感じます。大学生のときにも時間はあったものの、そのときには気づききれずシニア層になってからお金や時間の費用対効果ばかりで測れないものにこそ価値がありそうだと考えて、学び始めるというパターンです。このような方々の姿を見ていると、若い頃にこそ自分のものの見方を高めることが必要だと思います。
書店にも「教養のための」「すぐ分かる」といった言葉で始まるタイトルの本が並んでいると思いますが、これは手段としか教養や芸術を見ていないことの表れだと思っています。本当の教養や芸術は、すぐに理解しきれるようなものではないと思うのです。生涯分からないかもしれない、でもそれを分かろうとすることが大切になるはずなのに、2時間で分かった気になるのはちょっと違うように思います。
「Bunkamura」のこれから
学校における文化部の部活動への支援や活動の後押しとなる取り組みをしていきたいです。
部活動等の機会をお借りして生徒様に何らかの文化的な活動へ触れてもらえれば「一度見たことがある」「やったことがある」というように文化や芸術へ触れることへのハードルは高くないと感じてくれる人が増えそうだと考えています。
また、「Bunkamura」に来てくださる方やクラシックコンサートに足を運ぶ習慣のあるお客様に、「学生時代何をしていましたか?」と聞くと、吹奏楽やピアノを習っていた経験のある方が多いです。こうした経験をこれまでに持ってきたかが文化や芸術に触れる際へのハードルや捉え方に差を生んでいると感じます。だからこそ、子どもたちが少しでも芸術を身近に感じられるような機会をこれからも作っていきたいです。
さらに、文化部で活動されている子ども達が、目標や活動の方針にできるような場を作りたいと思っています。例えば、高校の野球部においては甲子園という目標があるからこそ、毎日練習を重ねるモチベーションができてここまで高校野球も盛り上がっているのだと思います。それに対して文化部の活動では、そういった目標設定の仕方をするのは難しい場合もあると思います。競技かるたを題材とした漫画の『ちはやふる』のように、目標にできる大きな何かがあれば、みんなが文化部に入って文化や芸術を楽しみたい!いう気持ちも持ちやすくなりそうだと思うのですが。
文化や芸術に触れる機会や文化部で活動されている皆様にとってモチベーションとなるような発表の場を作る形で、文化や芸術の価値を理解し楽しめる人が増えていくための支援を進めていければと思います。
プロフィール
Bunkamura
BunkamuraについてはこちらのHPをご覧ください。
Bunkamura:https://www.bunkamura.co.jp/
Bunkamuraオープンヴィレッジ:https://www.bunkamura.co.jp/sp/openvillage/
荒木 久一郎(あらき きゅういちろう)さん
1962年生まれ東京都出身。
1985年明治大学経営学部卒業。
大学卒業後、広告会社にて主にマーケティング・プランニング業務を中心に消費財などの
ブランディングや商品開発、地域振興など数多くのクライアント業務に携わる。
2016年より株式会社東急文化村にてチケット販売、広報業務を担当しており、
現在、執行役員マーケティング統括部統括部長。
日本アートマネジメント学会 会員。
著書紹介
今回取材した荒木さんの著書『文化・芸術のマーケティング』も合わせてご覧ください。
関連記事
演劇を用いた実践例などはこちらの記事で紹介しています。合わせてご一読ください。

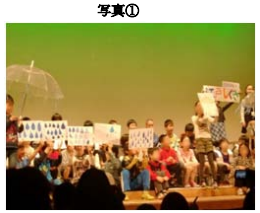

編集後記
芸術を消費するのではなく、じっくり咀嚼して味わうということ。分からないかもしれないけれど、考え続けること。実用的な世界にとらわれ続けるのではなく、こうしたことを大事にできる生き方をしたい、そして、芸術を楽しむ緩やかな輪を広げられる人になりたいと思いました。(下園)
デジタル化、AI化、ファスト化が進む今だからこそ、生の芸術に触れる機会は大切だと感じました。教養を身につけることも大切ではありますが、その手段として鑑賞するのではなく、芸術の価値に気付き、それを子どもたちにも伝えていきたいと思いました。(丸山)
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 下園絢音、丸山和音)


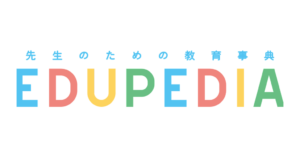








コメント