はじめに
1989年の開業から長きに渡り文化・芸術を発信する「Bunkamura」。
STEAM教育が推進され、自分を表現するツールとしての芸術が注目されている今、どのように芸術を学校や日ごろの活動に取り入れていけるのでしょうか。
学校現場でも活かせる芸術や、芸術を通して育てたい観点をどのように育んでいけるのか、株式会社東急文化村執行役員マーケティング統括部統括部長を務める荒木久一郎さんに伺いました。
なお、本記事は、2025年3月13日に行った取材を記事化したものです。
「Bunkamura」がこれまで取り組んできた教育活動、文化・芸術の役割、そしてこれからの活動についてご紹介した前編記事もあわせてお読みください。


芸術鑑賞会でできること
観て、語って、振り返ることができればよいと思います。現在の鑑賞教室は、観ることがゴールになっています。芸術を鑑賞させられたうえで、感想文も目的があまり理解できていないまま、ただ書かされているというお子様も少なからずいるように見受けられます。
特に大切なのは語ることで、クラスや学校で生徒が同じ芸術作品を一緒に観て語り合うことで「そういう風に思っていたの?!」と、自分と違う見方への気づきに繋げることが大切です。そのうえで、もう一度芸術作品や自分の見方について考えてみるのが感想文なのだと思うのです。語るプロセスがないために、「面白かった」「つまらなかった」というものだけで感想の広がりが留まってしまうことが多いのではないでしょうか。今回芸術を観た経験を、例えば、この芸術の価値はどういった点にあるのか考えを巡らせたり、自分がこの登場人物だったらどう考えるだろうか、どう表現するだろうかといったところまで広げるのは難しいのだと思います。
しかし、これを現実的に学校の先生が実践するのはなかなか難しいです。語り合う場やワークショップを設計することはとても手間のかかることなので学校の授業や工程の中に入れていただくのはなかなか大変なことです。だからこそ、対話型・探究型の新しい芸術鑑賞教室を、学校の方に我々から積極的に提供していきたいです。
我々にとっては文化や芸術に対して想像力があり、文化や芸術の価値に関して解像度の高い未来の観客を育てることに繋がります。学校現場の皆様にとっても教育的な意味合いを持った、新しい見方を生徒が獲得できる機会に繋がっていくのではと思います。
また、芸術を観るとき、全ての人がよいと思うことはないと思います。考えが違うことは起こり得ることですし、それは育ちや生きてきた人生が違うからこそ生まれる文化の違いで、一人一人違ってきます。みんながこれなら文句はないよね、という形を目指すよりも、自分はこう思うということを伝えて、そうでない人とも話し合うことが大切だと思います。
正解は別にないですし、作る側がこういう思いで作ったとしても、受け取る側が違う受け取り方をしても別によいのです。芸術として、それは許容しなければなりません。
一つだけ伝えるとしたら、全部否定的にみてネガティブチェックしていくというのは少し違うと思うのですが、自分の身近な問題に置き換えて観るのがよいのではないかと思います。
日ごろの教室や学校で芸術の取り込み方
手を動かす
まず、音楽や美術のどれをするにしても手を動かすことが大切だと思います。
例えば、美術展を観に行ったときには観るだけに留めるのではなく、ちょっとした落書きのようなものでも構わないので、実際に描いてみるのがよいと思います。児童生徒にとって自分の手を動かせる機会が減ってきているので、そこは進めていただきたいです。
音楽の分野でクラシックを扱うときに、バイオリンを弾いたことがある生徒はなかなかいないでしょう。吹奏楽部におけるトランペットの経験などでもよいので、まともな音を出すことがどれほど大変なことなのかを一度、その楽器に触れてみるだけで見方が全然変わると思います。手を動かしたり触れてみたりすることで親近感が持てるようになるはずなので、ぜひ、小さな経験からでも生徒自身が手を動かせる機会を取り入れてほしいと思います。
読み聞かせ
読書をただ推進するだけではなく、学校やクラスで読み聞かせをするとよいのではと思います。本を音読することと黙読することはかなり違います。例えば、順番で生徒自身に読み聞かせをしてもらうのです。読む生徒はプレゼンテーション能力の向上に繋がりますし、読み聞かせを聞く生徒は音で、しかも自分たちの仲間の声で本を聞くことができるので、黙読することとは違う経験になると思います。
多世代コミュニケーションに挑戦する
なかなか学校で行うのは難しいかもしれませんが、近くの老人ホームに行くなど、生徒が世代の違う人とコミュニケーションを取ることが重要だと思います。いかに話題がないかを感じられるはずです。
こういうときに、古典などの世代を超えて受け継がれているものがコミュニケーションの話題や会話の糸口として助けになります。自分のいる学校においては最近流行している歌を全員が知っているけれど、老人ホームに行ってお年寄りと話すことになったときにお年寄りはその歌手すら知らないため話が成立しないと思います。
だからこそ、何かお互いが理解できる、共通のものを作っていくのが文化や芸術の良さだと思います。
たとえ、コミュニケーションが苦手だったり、共通の話題がなかったりしたとしても、共通の芸術を観た経験があれば、生徒やお年寄りという世代の違う人同士の会話で話すことができると思います。昔であれば、世代を超えた人同士で何か共通のものを作るのが、テレビでした。視聴率が40%の番組もあったくらいですから、それが話題になって、世代間のコミュニケーションに困らなかったと思います。しかし、今は文化や芸術に触れる機会や手段が細分化されすぎていて、クラス全員が見ているものや、全員が共通して興味を持っているものはおそらくありません。だから、それをよいと思っているかどうかは別として、お互いが知っているものを見つけていけるように、古典や芸術などできるだけ多くのものに、触れておく方がよいのではないでしょうか。
プロフィール
Bunkamura
BunkamuraについてはこちらのHPをご覧ください。
Bunkamura:https://www.bunkamura.co.jp/
Bunkamuraオープンヴィレッジ:https://www.bunkamura.co.jp/sp/openvillage/
荒木 久一郎(あらき きゅういちろう)さん
1962年生まれ東京都出身。
1985年明治大学経営学部卒業。
大学卒業後、広告会社にて主にマーケティング・プランニング業務を中心に消費財などの
ブランディングや商品開発、地域振興など数多くのクライアント業務に携わる。
2016年より株式会社東急文化村にてチケット販売、広報業務を担当しており、
現在、執行役員マーケティング統括部統括部長。
日本アートマネジメント学会 会員。
著書紹介
今回取材した荒木さんの著書『文化・芸術のマーケティング』も合わせてご覧ください。
関連記事
演劇を用いた実践例などはこちらの記事で紹介しています。合わせてご一読ください。

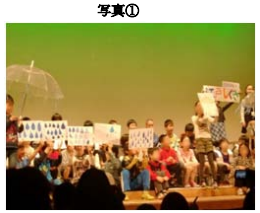

編集後記
映画を友人と鑑賞した後に語り合う時間を取ったことがあるのですが、自分の今の言葉で「語る」ことで題材を身近に感じたり、自分の捉え方や友人との感じ方を知る面白さに気づくことができました。これまで、芸術について「語り合う」経験が少なかったので、もっと早く知りたかったなと少し思いました。芸術を語り合う面白さが学校でも広がるといいなと思います。(下園)
普段観劇の習慣がない子どもにとって、演劇教室として機会が用意されていても、ハードルに感じてしまうことはあると思います。私自身、大学生になるまで、授業以外で観劇をしたことはありませんでした。本記事でご紹介したような「語る」というプロセスを加えることで、そんな子どもでも「正解を探さなくてよいのだ」と、自由に演劇に向き合えるようになれば幸いです。(丸山)
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 下園絢音、丸山和音)


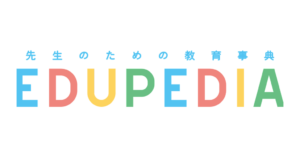








コメント