
1 はじめに
本記事は菊池省三先生の許可を頂き、メールマガジン「菊池省三の未来を創る学級」のサンプル号の内容を引用させて頂いたものです。サンプル号(無料)のうち、この記事では「新・ほめ言葉のシャワー」を紹介します。
メルマガには講演会、メディア情報、読者からの感想など多くの内容が掲載されています。ぜひご覧になってみてください。
メールマガジンの詳細・登録はこちらから→http://www.mag2.com/m/0001629666.html
(毎週土曜日発行。一ヶ月864円。)
2 新・ほめ言葉のシャワー
「ほめ言葉のシャワー」は、全国に少しずつ広がっています。「子どもたちが明るく変わった」「学級の雰囲気が温かくなった」といった、たくさんのうれしい声を聞きます。もちろん、「こんな時はどうしたらいいのでしょう?」「ちょっと気になることが出てきました」といった、ご質問やご意見も耳にします。
このシリーズでは、そのようなご質問やご意見にお答えする形で進めていきます。
Q:「ほめ言葉のシャワー」をしていると、ほめてもらいたくて、わざとにいいことをしようとする子どもが出てくるのではありませんか
A:この質問は、時々あります。その多くは、「ほめ言葉のシャワー」をされていない方です。そして、「それってよくないことですよね」といったお考えでご質問されているように感じることが多いです。
私がお答えする内容は、結論から言うと、「そのような子どもは、います」です。そして、「それって、とてもいいことですよね」とお答えするようにしています。最後に、「少し続けると、そのような子どもはいなくなりますよ」とお伝えしています。
1巡目の時には、ほめられたくて、張り切る子どもがいます。普段とは違って、明らかにがんばる子どもです。
私は、そのような子どもは、メチャクチャほめます。「すばらしい」「がんばっているね」といった言葉の後に、
- 今日の日を特別に感じてくれているんだね
- 君の本当の実力を出そうとしてくれているんだね
- 非日常の今日という日に君らしさをもっと発揮してほしい
- 今日は最高に気合が入っているね
などと言います。そして、「ありがとう」と伝えます。
少し説明をさせていただきます。その理由を3つ書きます。
1.「ほめる」「ほめられる」経験
1つ目は、「ほめる」「ほめられる」ということは、コミュニケーションの技術の一部でもあると考えているからです。技術は体験よって伸びるものです。ですから、多少の「無理」もあっても体験させた方がいいと考えているのです。子どもたちの多くは、「ほめる」「ほめられる」といった経験があまりありません。特に、4月に出会ったばかりの子どもたちには少ないようです。
その技術を体験させることをまずは重視したいと考えているので、1巡目にそのような子どもがいたとしても気にはなりません。逆に、子どもらしくていいことだと思うほどです。小学生の子どもであれば、当然であると考えているぐらいです。張り切らない子どもがいたとしたら・・・少しこわいです。(このことについては、3つ目の理由のところでもふれたいと思います)
2.教室のプラスの空気
2つ目は、その後に広がる教室のプラスの空気があるからです。そのようなわざとほめられようとしている子どもがいて、その子どものそのような行為を「ほめ言葉のシャワー」でほめたとします。しかし、教室の空気はマイナスにはなりません。グッと温かいものになります。例えば、
- ○○君は、今日は主役だったので~~をがんばっていました。そんな無邪気な一面を見ることができてうれしかったです。
- 普段しないような~~もしていました。それが○○君の本当の成長する姿です。これからも私たちのお手本でいてください。
などと、子どもたちはほめるのですから、教室の空気はやわらかいものになるのです。これが毎日続くのですから、その後に広がるこの目に見えない効果は大きいです。
3.子ども達の事実
3つ目は、子どもたちの事実です。最初に述べたように、確かに1巡目にはそのような子どもはいます。しかし、実際に「ほめ言葉のシャワー」を行ってみると、次のような現象が起こります。
学級の人数が30名だったとします。ほめられたくてわざと頑張った子に、残りの29名がほめ言葉を言います。29名全てがほめられたくてがんばった子どものその行為群をほめるのでしょうか?そうではありません。「ほめ言葉のシャワー」を浴びる子どもが、「えっ!?気にしていなかったそんなこと」「本当!?それはほめられるとは思ってもいなかった」といったことも、多くの子どもがほめるのです。これが、実際です。
そうなると、子どもは次のように考え始めます。
- 無理していいことをしなくてもいいんだ
- 普通にしていても、自分のいいところを見つけてもらえるんだ
- 当たり前にしている中にも自分らしさが出ているんだ
このようになりますから、成長しつつある自分を「そのまま」子どもたちは、ほめ合い認め合うようになります。
「ほめ言葉のシャワー」は、1年間で5巡ほど行えます。(1クラス30人程度)ですから、ほめられたくていいことをしようという子どもは、2巡目あたりからいなくなります。ありのままの自分でいいんだ、という自信と安心感が子どもたちと教室の中に広がっていくからです。
3 関連イベント情報
スペシャル・セミナー 『地域を再生・活性化する「主体的・対話的で深い学び」とは?』

日時:2018年8月18日(土) 12:30〜16:50
会場:エル・おおさか 南館 南ホール(大阪府大阪市北浜東3-14)
内容:
○菊池省三先生による講座「いの町・中津市ほかでの取組の現在」
○南惠介先生による講座「木を見て森を見て、そしてまた木を見る~全ての子供たちに小さな社会を紡ぐAL~」
○隂山英男先生による講座「福岡県飯塚市、田川市等における地域ぐるみの取組」
○講師鼎談「地域・学校を再生・活性化する、今後の教育のカタチを考える」
詳細:https://www.kokuchpro.com/event/2d7fd7f0601b587906af123eff0d4aa7
4 プロフィール
–
菊池省三
1959年愛媛県生まれ。山口大学卒業後、北九州市の小学校教諭となる。
2004年第1回北九州市すぐれた教育実践教員表彰。05年福岡県市民教育賞受賞。
文部科学省「熟議に基づく教育政策の在り方に関する懇談会」委員。研究サークル「菊池道場」主宰。
『菊池省三の「話し合い」指導術: 小学生版 白熱教室のつくり方』(小学館)『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)他共著書多数。12年7月にNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演、大反響を呼ぶ。
メールマガジンの詳細・登録はこちらから→http://www.mag2.com/m/0001629666.html
(毎週土曜日発行。一ヶ月864円。)
5 編集後記
この転載記事を読んで「ほめる」ということに対して考え方が変わる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。私自身、菊池先生の長年培われた経験が詰まったこの記事を読んで、子どもにとって「ほめる」「ほめられる」経験が必要なことや教室がプラスの空気に変わることを知って、ほめるということに関して視野が広がりました。そして、あらためて思ったのは、教育においてほめることはとても重要だということです。私は、これからの時代を担う子どもたちに、自信と安心感を持たせてあげることができるようにサポートしていきたいと強く思いました。
(編集・文責:EDUPEDIA編集部 本田耕平)


(後編)-1-300x169.png)
(後編)-300x169.png)

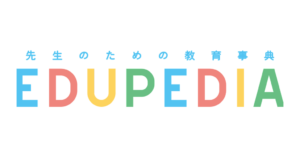


コメント