
1 はじめに
本記事は、雑誌『教育技術』(小学館)とEDUPEDIAのコラボ企画として行われた、中野信子先生へのインタビューを記事化したものです。
「脳科学的に見て、いじめは本来人間に備わった“機能"による行為」であると考える脳科学者の中野先生に、道徳的に教え諭すのではなく、いじめに対するアプローチを変えて、良好な人間関係を維持するためのヒントを伺いました。
『小一教育技術』~『小六教育技術』11月号にもインタビュー記事が載っていますので、そちらも合わせてご覧ください。
⇒教育技術.net
2 インタビュー
いじめという“機能"
——今回の著書では、「なぜいじめが起きるのか」ということを、脳科学の観点から分析し、対応策を考察されています。
いじめは子どもの世界だけでなく、大人の世界でも、時代や国を問わず存在します。近年、こうした人間の複雑で不可解な行動を、科学の視点で解き明かそうとする研究が世界中で進められています。
近年の研究から分かってきたのは、こうした排除行為を行うことは、人間が種として存続するために必要な行為であったのではないだろうか、ということです。つまり、いじめがなくならないのは、いじめという行為は、人間が進化の過程で身につけた「機能」だからなのではないか、ということです。
もし、そうであるならば、いじめについて科学的理解を深めることによって、より有益なアプローチを見いだせるのではないでしょうか。
仲間を守るための制裁
——脳科学の観点から分析した、いじめのメカニズムとはどのようなものなのでしょうか。
人間の肉体は、他の動物と比べ、非常に脆弱です。猛獣と戦って勝てる人はほとんどいません。そんな戦闘的に不利な肉体を持つヒトという種が、生き残るための武器として使っていたものは何か。それは、「高度な社会脳」を持ち、「集団をつくること」です。つまり、集団で協力行動を推進する機能という形で、社会脳が発達してきたということが示唆されるのです。
そして、集団を維持しようという機能が高まることで、集団の邪魔になりそうな人がいた場合、その人に制裁行動を加えて排除しようとする機能も、脳に備え付けられたと推測されるのです。学術用語では、この制裁行動を「サンクション」と言います。
この「サンクション=制裁行動」は集団になれば、ほぼ必ず生じるといってよい行動です。そして、そもそもは、この制裁行動は仲間を守ろう、社会性を保持しようという、集団を維持するための「向社会性」の表れなのです。
「向社会性」は、反社会性の反対の意味であり、それ自体は悪い性質のものではありません。しかし、向社会性が高まっていくと、時に排除しようとする機能が行きすぎてしまうことがあります。
例えば、ルールを破ろうとしているのではなく、ルールを知らなかっただけの人や、少し生意気だったり、ちょっと目立つ可愛さがあったりするなど、みんなのスタンダードと少し違うという人に対しても、制裁感情が過敏に発動してしまうことがあります。これを「過剰な制裁機能(オーバーサンクション)」と言います。この現象は学校や会社といった組織でも、高い可能性で起こりうることです。これが「いじめ」のメカニズムなのです。
いじめと脳内ホルモン
——脳科学的にいじめが起きやすい環境や、過激化しやすい状況とはどのようなものでしょうか?
脳内物質の視点から言うと、「仲がよいほどいじめが起きやすい」という傾向があります。誰かと長時間同じ空間に一緒にいることで、「仲間意識」をつくる「オキシトシン」という脳内ホルモンが分泌されます。オキシトシンは愛情ホルモンとも呼ばれ、脳に愛情や親近感を感じさせるホルモンです。しかし、このオキシトシンが高まりすぎることで、仲間を守ろうという意識が高まり、「邪魔者」は排除しなければ、という意識も同時に高まってしまうということが分かっています。
つまり、集団でいることでオキシトシンが高まり、向社会性も高まり、仲間意識が強く働くことで、集団の中で逸脱した人を排除したいという気持ちも起こる。そこに誘発される制裁行動が「いじめ」なのです。

いじめの快感
この制裁行動が促進されるもう一つの原因は、制裁行動に「快感」を感じるからであると考えられます。実際に、制裁行動が発動する時の脳では、「ドーパミン」が放出され、喜びを感じることが分かっています。これは、ルールに従わない者に罰を与えるという「正義」を持って制裁をするため、そこでは達成欲求や承認欲求が満たされ、「快感」を感じるのです。
ネットの炎上などが分かりやすい例でしょう。誰かが少しでもポリティカル・コレクトネス(政治的・社会的な平等意識)から逸脱したとみなされると、みんなで寄ってたかって叩きに行く。共同体のルールに従わない者を糾弾しようと、正義の側からあらゆる言葉を使ってバッシングする。そして炎上させることで、ある種の承認欲求や達成欲求が満たされ、ドーパミンという脳内麻薬が活性化し、バッシングはさらに過激化します。
いじめている側をどんなに諭そうとしても、「自分は正義を行っている」という無意識の正義欲があり、あるいは正義を行う快感に中毒になっているので、止めることはできません。抑制の機能が備わっていない子どもならなおさら、この機能を止めることは困難です。
さらに、子どもたちのいじめの中で、自殺にまで追い込むような過激ないじめは「小学校高学年から中学校2年生」に多くなると言われます。この時期は、「性ホルモン」である「テストステロン」が急激に増える時期と重なります。テストステロンは、主に男性に多く分泌されるホルモンで、男性の場合、9歳から増えて15歳になるまでにピークに達します。テストステロンは、支配欲や攻撃性を強める働きがあり、女性でもテストステロンが多い女性は攻撃性が高いことが分かっています。
この時期の子どもは、手あたり次第反抗したり、誰かを攻撃したいという衝動が高まっていくため、周囲の大人は、子どもたちの脳が成長過程であることを踏まえて注意深く対応する必要があると考えます。
「いじめは損」と感じさせる
——中野先生は著書の中で大人のいじめ、子どものいじめそれぞれに科学的観点からさまざまな対応策を提案されています。各学校現場でもさまざまないじめ対策が講じられていますが、どのように考えられますか?
子どもの脳は発達段階です。いくら「いじめてはいけない」「相手の気持ちを考えよう」と教え諭しても、「抑制」と「共感」の領域が未発達なため、ブレーキが利かないのです。これを止めるには、子どもに「自分が相手を攻撃すると、自分が損をする」と感じさせ、「いじめ」という行為を放棄させる徹底したシステムを構築することが重要です。しかし、現状の学校現場では、誰も見ていないところで相手を攻撃すれば自分は損をすることはない。つまり、賢く攻撃した者勝ちという構造ができあがっているのです。
仲間と長時間過ごすことでオキシトシンが高まり、仲間意識が強くなる。したがって、集団の邪魔になりそうな人を検出する機能も高まるという観点から言うと、学級のあり方についても議論が必要になるでしょう。学級という狭い空間の中で、「みんな仲よく」「団結しよう」と求めることが、いじめが起きやすい環境につながるということも認識しておくべきだと思います。
対応策としては、例えば習熟度別のクラス分けを増やす、学級以外の人との交流を増やすなど、人間関係を固定化しない工夫が有効です。大学でいじめが深刻化しないのは、さまざまな人と自由な交友関係が担保されているため、無視をしたり、悪口を言ったりといったいじめの効力が無力化するからです。
本当にいじめを防止しようと考えるのであれば、「いじめは脳に組み込まれた機能なのではないか」という可能性を吟味することも大切なのではないでしょうか。そうすれば、この機能をどうコントロールするのかという方向に解決のベクトルが向かっていくはずです。
3 プロフィール
中野信子(なかの のぶこ)先生
脳科学者、医学博士。
東京大学工学部卒業後、2004年東京大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程修了。
2008年、東京大学大学院 医学系研究科 脳神経医学専攻 博士課程修了。
2008~2010年まで、フランス原子力庁サクレー研究所で研究員として勤務。
帰国後、横浜市立大学客員准教授、2015年から東日本国際大学特任教授。
著書に『サイコパス 』(文春新書)、『あなたの脳のしつけ方』(青春出版社) 、『世界で通用する人がいつもやっていること』(アスコム)、『脳科学からみた「祈り」』(潮出版社)などがある。
(2017年10月時点)
4 著書紹介
本書では、子どもはもちろん、大人社会でも多発している「いじめ」にどのように対処すればよいのか、脳科学の視点から考えたヒントが満載です。
5 編集後記
自分が小学生の時、いじめは道徳的な心の問題として考えることが多かったように思います。しかし、それだけではなく、中野先生が提示された、いじめを脳というハード面から考え、「仲がよいほどいじめが起きやすい」「制裁行動に喜びを感じる」といった機能的な視点も持ち合わせることで、いじめてしまう子どもをよく理解することができると思いました。
「いじめっ子」は、自分の意思とは関係なく、脳に操られているのかもしれません。
(EDUPEDIA編集部 大和信治)
6 関連ページ
教育技術.net

『小一教育技術』~『小六教育技術』11月号に掲載のインタビュー記事も合わせてご覧ください。
【教育技術×EDUPEDIAコラボ】スペシャルインタビュー

第1回からのインタビューまとめページはコチラ

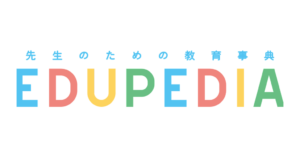

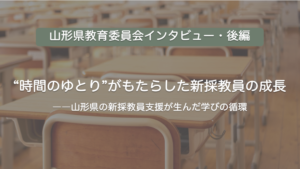

(後編)-1-300x169.png)
(後編)-300x169.png)

コメント