はじめに
この記事は、2024年5月27日に行った、千葉大学教育学部教授である石田祥代先生へのインタビューを記事化したものです。
高い知的能力と困難さを併せ持つ「ギフテッド」。NPO法人ROJEが2022年度に立ち上げたギフテッドプロジェクト「sprinG」では、ギフテッド特性があり学校に馴染みづらい子ども、そしてその保護者の支援活動を実施しています。(ギフテッドの子どもについての詳しい情報はこちらの記事もご覧ください。)
sprinGでは、 2023年度より、文部科学省から「令和5年度特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」の委託を受け、特異な才能のある子どもと関わる教職員向けの勉強会と個別相談の受付を開始しました。
本記事では、教職員向け個別相談を担当し、実際に現場の先生方に向けてアドバイスを行っている千葉大学教授の石田祥代先生に、特異な才能のある子どもに必要な支援、そして学校に求められていることについてインタビューした内容をお伝えします。
◎こんな人におすすめ!
・特異な才能のある子どもの教育や支援について、不安を感じている先生
・特異な才能のある子どもの困難や、必要な配慮を知りたい先生
・特異な才能のある子どもの学校適応をサポートしたい支援者の方
・特異な才能のある子どもの支援について知りたい保護者の方
Q.ご専門はなんですか。
大学院では心身障害学という領域で、教育、心理、病理の3点を複合的に学びました。私はとりわけ教育制度の歴史的変遷を辿るなかで、どのような仕組みがあれば有機的に子どもの支援に結びつくのかについて研究を行ってきました。
大学院修了後、心身障害学の分野で少し働いた後、社会福祉士を養成する大学に勤務しました。当時は、知的障害や重度障害がある子どもたちが学校を卒業すると、作業所や施設に入るという選択肢しかありませんでした。そこで、支援が途切れないようにするため、教育と福祉の連携の道を探ってきました。現在は、子どもをサポートする仕組みを考えるにあたって、北欧にも研究の軸足があります。
Q.ギフテッドに着目したきっかけは何ですか。
ギフテッドに関しては5、6年前から頭の隅にありました。身近な子どもたちのなかに、勉強はよくできるのに学校に行けないケースや、家では問題ないのに学校に行くと悪いところばかりが目立ってしまうケースなどをいろいろなところで見聞きしていたからです。分散した情報を合わせていくと、今まで私たちは「勉強についていけない苦労」や「真ん中」にばかり焦点を当てて「上の方の苦労」を見てこなかったという気づきがありました。北欧でも同様に、予算や仕組みがないということが分かり、国際的に共通した課題だと思いました。
こうした経緯で、「挑戦的研究」という枠組みで研究費を獲得し、4年前に研究を開始しました。(2024年度にも、ギフテッド関係で「挑戦的研究」の研究費を続けて獲得されたそうです)。
Q.どのような制度が望ましいと思いますか。
ギフテッドのことを研究し始めてから、文科省が出している規定を丁寧に見返しています。文科省は、学年を柔軟にしたり、小中一貫校でないとしても中学校の内容を先取りするなどの対応を推奨しています。また、例えば不登校の子どもがオンライン教育を受けてもよく、それが出席扱いになるという通知も出ていますが、「うちの学校では対応してもらえない」という保護者の不満も聞きます。ギフテッド傾向にある子どもの教育も大事だということを管理職の先生や教育委員会側も認識すること、まずはモデル校からでも良いので通知の内容を現場に落としていくことが必要です。
Q.学校現場で通知にあるようなことを実践できない背景にはなにがあるのでしょうか。
何かをして失敗したときの責任の所在を考えると、挑戦的な実践をしづらい慣習がある気がします。また、先生や管理職の転勤制度も、腰を据えてなにかをすることが難しい一因かもしれません。
一方、限られた期間だからこそ挑戦してほしいとも思います。「自分がいる間に学校のここを変えて次に移動したい」というムーブメントがいろいろなところで起こっていくと教育は良い方向に変わると思います。異動があるからこそ、1人の先生に全ての責任がいかず、風通しが良い仕組みだともいえますよね。
Q.ギフテッドに関する社会的な理解の少なさも関係しているでしょうか。
ギフテッドについては教職課程で必ずしも学ばないですよね。知識が十分でなく、子どもの行動の解釈がずれてしまうことはあるので、そこは研究者として根拠のあるリソースを発信しなければと思います。
とはいえ、障害の種類をすべて知っていなきゃいけないとか、検査法が頭に入っていなきゃいけないというのは無理があると思います。今のインクルーシブ教育や特別ニーズ教育の考え方は、その子の持っている力や困り感に視点を移し、そこから支援の方法を考えるという方向に国際的にも変わっています。
知識がなくても、担任の先生だからこそ子どもをみられる部分があります。知識や実践の根拠にとらわれすぎず、自分が持っているスキルでできそうなことを、半歩でも良いのでやってみると良いと思います。
大したことでなくとも、分かっている子どもには「この計算ドリルを使わなくても良いよ」と声がけするくらいの支援でこと足りることもあります。
Q.学校の先生に伝えたいことは何ですか。
先生たちはクラスの子どもの特性をすごくわかっていらっしゃると思うんですよね。きっと「何かをしなくては」と毎日思っていると感じますが、全員には難しいですよね。
私は、例えば40人のクラスの場合、「今週はこの5人を特に注意して見てみよう。来週は別の5人を支援してみよう」というようにルーティン化してもらい、小さなまとまりで子どもたちを見ていくと、やりやすいのではないかという提案をすることがあります。子どもも自分のことを見てくれていると感じやすいので、もしよければ実践してみてください。
Q.最後に一言お願いします。
ギフテッド傾向がある子どもに限定せず、例えば外国籍で日本語が苦手な子どもや、ヤングケアラーで学校しか勉強する場所がないというような子どもも含めて、さまざまな背景がある子どもに対して、学校でできることをするのが重要だと思います。
私自身、学校で困っているさまざまな子どもを支援できる仕組みを作りたいと思っているので、先生たちとも一緒に考えていけたら良いなと思っています。
プロフィール
石田祥代先生

千葉大学教育学部特別支援教育コース 教授
筑波大学大学院心身障害学研究科修了。博士(心身障害学)。筑波大学、東京成徳大学応用心理学部を経て現職。専門は特別支援教育、障害児教育学、児童福祉学。
NPO法人ROJE ギフテッドプロジェクトsprinG
ギフテッド特性があり、学校に馴染みづらいと感じている小・中学生やその保護者に向けた居場所づくりに取り組む。児童精神科医や特別支援教育を専門とする大学講師といった専門職と、教育に志のある大学生が中心となって運営している。



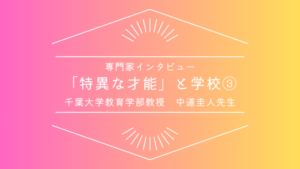
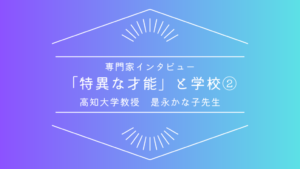
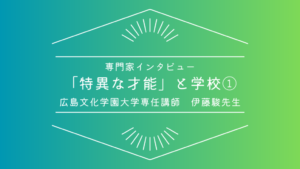
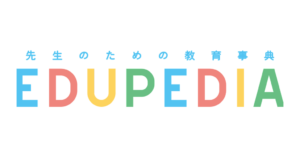

コメント