なぜ丸腰で戦場に赴く?
【①地雷原】学校にはたくさんの地雷が埋まっています。思わぬタイミングで地雷を踏みます。
【②見えない敵】地雷原の向こうの森では敵がひそんでいて、銃弾が飛んできます。
【③巻き込まれ】流れ弾が飛んでくることもあります。
【④支援の欠如】あなたが地雷を踏んでも、弾に撃ち抜かれても、周囲には助ける余裕がありません。
【⑤身内からの攻撃】場合によっては、後方からも弾が飛んできます。
【⑥無策】あなたは丸腰でそこを歩きます。
【⑦持続的な不条理】もし無事にこの地雷原を切り抜けても、その先にもまた地雷原が続いています。
【⑧不休】緊張状態が続き、休みはろくに与えられません。
上記は、教師という仕事についての、筆者のイメージです。要約すると、
「十分な戦略も準備もなく、状況も把握せず、難しいミッションの達成を強いられている」
という感じでしょうか。
かなり悪いイメージですが、そこそこ言い当てていると思います。あくまで私がこの記事のように感じているにすぎませんが、これを参考に学校の現在地を確かめてみるのもよいのではないかと思います。
教育現場は複雑化、多様化、多忙化、個別化、国際化、硬直化、弱体化・・・しており、まとめて言うと過酷化しています。戦場のような現場(学校・学級)は少なくありません。
教師が丸腰で過酷な戦場に赴いてしまっているように、私には思えます。(この記事の執筆は2025年3月時点)
どのように戦場なのか
解決されない課題
1995年辺りからの学級崩壊、2005年辺りからのモンスターペアレンツ問題、ずっと(40年程)引きずっているいじめ問題や不登校問題・・・。それらは多忙化を招き、最近は教員不足で担任不在という問題も報道さてれいます。いつ、どんなクラスを持たされるか分かりませんし、受け持った時点では大丈夫そうであってもその後、問題が持ち上がってくるケースも少なくないです【①地雷原】。
学校が多くの問題を抱えていることが明るみに出て、教員採用試験の倍率低下を招いてしまっています。倍率の低下は教員の志・演算能力の低下につながることも問題視されています。この「低下」は長きにわたる影響が出る恐れがあります【⑦持続的な不条理】。
実際私も自分のクラスを持ちながら隣のクラスで空いた穴を埋めざるを得ない状況に陥ったころもあります。
上に挙げた問題はそれぞれ深刻でありながらも、決め手となる有効な策がないままに対処をせざるを得ません【⑥無策】。
誰と戦っているのか、何と戦っているのかがわからない
オンラインゲームが広がりを見せており、年齢制限がある筈のゲームを小学生がしていると言っているのをよく聞きます。ゲームをしながらチャットや音声通信で悪い言葉を言い合っているそうです。場合によっては深夜までゲームが続くそうです。子供の話を聞いていたら「クラスの友達とチームを作って闘っているんだよ」と教えてくれたことがました。
最近は、貧困家庭も増えており、三食を食べられていなかったり、親が複数の職を掛け持ちして家庭生活が不安定になっていたりするケースもあります。
昔は家族旅行で学校を休むのはご法度でした。15年程前から、だんだん家族旅行で欠席する子供が多くなり始めたものの、15年前は内密にしていました。ところが今や、オープンに友達に「ディズニーランドに行ってきたよー」と話しています。
怠学による不登校や遅刻も増えており、その態度は堂々としたものになってきています。当たり前のように遅刻をしてきます。しかし、不登校や遅刻による学習の遅れを保障するのはたいへんです。
このように、教育現場は絶えず社会や家庭の問題の影響を受けます【③巻き込まれ】。「学校の困難化」の原因には本当に複合的な要素があり、何か一つに原因を特定することは難しいです【②見えない敵】。
子供にとって教育は義務ではなく「受ける権利」であるという認識が広まっています。少ししんどい課題を与えると、びっくりするほど簡単に拒否をしたりエスケープ行動をとったります。
あるクラスで授業中にずっとパーカーのフードをかぶっている子供がいたので、「授業中にフードをかぶるのはマナー違反だからとりなさい」と指導すると、その子から「人それぞれでしょ」と諭されました。私の感覚がおかしいのでしょうか。
学級崩壊やいじめ問題についてはやや収まった部分もありますが、新種・変種の問題も持ち上がってきています。最近は、正面を切って指導不服従をする子供が減ってきている代わりに、なんとなーく、教師の指示・指導に従わずにやり過ごすような子供が多くなっている気がします。これを私は「消極的指導不服従」と呼んでいます。消極的指導不服従の子供が3割程度いるとクラス全体に覇気がなくなってきて、何をするにも日々の活動が重たくなってきます。
令和の小学生の実像がつかみきれません。学校を取り巻く状況が複雑化・困難化し、徐々にかつ、確実に進んで行くために、いったい誰と闘っているのか、何と闘っているのかが分からなくなってきます【②見えない敵】。
戦場と化している実感がありながらも、現状把握がなかなかできません。
原因が多種多様で複雑であるために分かりにくいです。子供の変容だけではなく、親も大きく変容しています。今の親世代の多くが2000年前後から顕著になってきた学級崩壊を経験していることも、影響しているでしょう【②見えない敵】。
また、子供・親世代ともに「税金で学ばせていただいている」「迷惑をおかけしては世間様に申し訳ない」といった心情がびっくりするほどなくなりました。宗教的な心情も失われてしまい、逆に自分が神の位置に立っているかのような万能感に溢れています。私の世代(1960年代生まれ)も無宗教な人が多かったですが、「こんな悪いことをしたら罰が当たるかも」といった最低限の道徳観はまだあったように思います。
私の友人は全国大会に何度もチームを出場させるほどのとても優秀な部活動の指導者なのですが、「遠方まで泊を伴う引率をして帰ってきても、親からの感謝の言葉はほとんどもらうことがなくなった。逆に不平不満苦情は嫌になるほど増えた」とこぼしていました。確かに保護者から「ありがとう」の言葉をいただく機会は減りました。着々と世代交代が進んでいます【②見えない敵】。
もし、子供や親の変容の原因を突き止めたとしても、何か具体的で有効な対応ができるわけではありません【⑥無策】。
忙しいので本来業務(≒授業・学級経営)をしたいのだけれど、部活をしたいとか、派手に行事をしたいとか、研究大会を引き受けたいなどという大きい声が通ってしまい、業務改善もなかなか進みません【③巻き込まれ】【⑥無策】。
兵站(戦闘地帯の後方から必要な物資や兵員を配置する活動全般)も不足しています。マンパワーが足りない、酷い場合は担任が足らないという人員不足の問題は深刻です。建物・施設、備品や消耗品の老朽化も悲しいです。
指導困難な学校では放課後に保護者へのトラブルの報告をしようと、「2台ほどしかない電話」の前に列ができます。病院で内線や業務用PHS(携帯電話)を導入しているのを見ると、羨ましく思います。後手に回っている様子がいたる所で見られます。【④支援の欠如】
学校と言う戦場では、【②見えない敵】に【⑥無策】なままで、今後も教員のハードワークによってカバーし続けなくてはなりません【⑦持続的な不条理】【⑧不休】。
初任者がいきなり教壇に立つ
※ 下記は初任者を例に挙げて書いていますが、教員全般に当てはまるものがあると思います。まとめれば、【⑥無策】【④支援の欠如】ということになるでしょうか。
コンビニのアルバイトであっても初心者を研修もせずに最初から深夜時間帯にワンオペで働かされることはまずありません。であるのに、学校では初任者にいきなり学級担任をさせます【⑥無策】。1か月程度の教育実習の経験など役に立ちません。ベテラン教員でも異動でよその学校へ来れば習慣やルールが違って混乱します。平成元年に初任者研修が設けられるようになりました。初任者に研修するのは一見、妥当と思われる部分もありますが、多忙で不慣れな通常業務に研修が加わると、かえって負担である場合もあります【⑤身内からの攻撃】。
また、困っている教員には周りの教員が助けるという建て前ではありますが、あくまで建て前です。お困り感に寄り添って当人のニーズに応えてくれるかどうかは「支援ガチャ」です。初任者でもほぼワンオペで授業と学級経営を任されます【④支援の欠如】。また管理職や学年スタッフ・初任者担当教官が支援と言いつつ無駄に厳しい場合もあり、初任者はさらに追い込まれます【⑤身内からの攻撃】。
4月1日に事例をもらったばかりの初任者を4月7日には丸腰で教壇に立たせる。これは学校の「丸腰主義」の象徴だと思います。なぜ、こんな不条理に対して鈍感なのか。それは多分、戦場においては人倫が失われることに似ているのだと思います。
※ 自治体によっては、初任者は負担軽減と見習い研修と言う意味を込めて、副担任でスタートするような制度を始めているところもあります。2025年でやっとそうした制度変更が行われるようになってきました。初任者研修はスタートして実に35年が経っており、それまで改められることがなかったのです【⑦持続的な不条理】。いかに学校が【⑥無策】であるかがよくわかります。
遅い改善
例を挙げるときりがないですが、現在の学校の苦境がわかっていただけたでしょうか。
本当に状況が酷かったのは2000年から2010年の間ぐらいだったように思います(あくまで私の体感です)。現在に至るまでに様々な改善が進められてきているのも事実で、その効果は出てきているように思います。
しかし、改善のスピードが遅くて間に合っていません。新手の敵が次々に現れてきます(≒事態の悪化)。この1年で言うと、「教員不足」というだけではなく「教員不足による担任不在」が起こっています。教員採用試験の倍率低下も、じわじわと現場の事態を悪化するでしょう。【⑦持続的な不条理】
事態の悪化のスピード>>>改善スピード
なので、なかなか学校現場に平和は訪れません。
戦場の全体像
ここまでで挙げた困難(ほんの一部です)に立ち向かって戦うには、戦場(教育現場)の現状だけに目を向けていてはいけません。その全体像を俯瞰し、成り立ちを理解せねばなりません。
能澤英樹氏は「先生2.0」(2024)において、
「学校は、同一地区に住む、6~15歳の子どもを全員集め、同年齢の40人以下の「学級」を作り、部屋に閉じ込め、一斉に(半強制的に)好きでもない勉強をさせる(場所)」
であると指摘しています。とても分かりやすいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/03743955.77887bc8.09430918.da38491b/?me_id=1213310&item_id=21012611&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3696%2F9784908983696_1_38.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
先生2.0 日本型「新」学校教育をつくる [ 能澤 英樹 ]
上記の前提を元に様々な現象を考えてみると、「教師が誰と戦っているのか、何と戦っているのか」が見えてくると思います。何をやっているのだかわからなくなってきた時には、この言葉に立ち返ってちょっと俯瞰してみましょう。
そして、法的な建付けについても考えなければなりません。教員の残業を認めず、数%(率は本記事執筆現在審議中)の給与の上乗せだけが支払われて後は「働かせ放題」となってしまう現状を生み出しているのが「給特法」です。
ここで詳しく語ると長文になりすぎますので割愛します。EDUPEDIAでもいくつかの記事で説明・言及していますので是非ご参照ください。「先生2.0」にも給特法について、分かりやすく・詳しく書かれています。

この法律のおかげで命令や通達や「お願い」が濫発され、文科省・教育委員会・管理職によっていくらでも仕事が増やされます【⑧不休】【⑤身内からの攻撃】。
また、社会全体が学校・教師に対して依存をする習性になってしまっています【②見えない敵】。学校は塾が原因で生じたいじめ事件まで解決させられます【⑦持続的な不条理】。
そんな調子で社会は学校に依存しているのに、何かミスが出るとすぐに猛批判の対象になります。教室で起こった「話し合えば解決するような事案」でもマスコミに発表されるし、ネットで叩かれるし、管理職を通り越して教育委員会や文科省に電話を掛けようとします。【①地雷原の爆発】
「戦場で丸腰」を認識し、戦略的思考へ
学校が戦場だなどと書くと、これから教員になろうとする方や、若手教員・異動をする教員が委縮してしまうのではないかと思い、少し躊躇する気持ちもありました。私のイメージが過酷すぎるのかもしれないですし・・・。
ではなぜ、敢えてこの記事のタイトルを「学校は戦場だ、教室は戦場だ(前半) ~なぜ丸腰で戦場に赴く」と、刺激を強い目にしたのかと言うと、タイトルの後半部分について考えてほしかったからです。
教育現場にいると、
「Aさんのお父さんが隠れモンスターペアレントだった!」【①地雷原の爆発】
「どうやらCさんのお母さんに恋人ができたみたいで、Cさんはおじいさんの家に預けられっぱなしみたい。かなりCさんが荒れている。」【②見えない敵】
「学年でダンス発表会をしようという話になっているが、学級が荒れているしダンス指導は得意でないので、とてもそんな状況ではない」【③巻き込まれ】
「隣のクラスが荒れて担任は休職に追い込まれた。代替の担任が来ない。私が空き時間ゼロで授業を担わされる。」【④支援の欠如】
「私の授業の不味さについて子供の前で校長から叱責を喰らった」【⑤身内からの攻撃】
「昨年の終業式の職員会議提案文書のファイルが共有フォルダに入っていないのだけど!」【⑥無策】
「え、今年もこんな荒れた学年の担任?」【⑦持続的な不条理】
「週末は丸二日、成績処理に費やしたわ」【⑧不休】
などなどなどなど、「嘆き」や「愚痴」が聞こえてきます。私もよく嘆き、愚痴っています。
それなのになぜか、嘆いて愚痴っている割に、教師は「戦場で丸腰」であることに慣れて鈍感になってしまっています。
「いや、丸腰ではない、自分はきちんと準備をして仕事に臨んで成果を上げている!」
と、おっしゃる方もいるかもしれません。しかし、それは自分の手の届く範囲であり、教育全体を見渡せば今、地雷原で涙を流す丸腰の教師がたくさんいます。その先には涙を流す子供たちがいるのです。自分(達)が丸腰でなくなったならば、次はもう少し大きなステージでの「丸腰状態改善」への戦略を立ててみてください。「局所的に大局的に」、「短期的に長期的に」、戦術と戦略を考えて動いてゆかなくてはなりません。
後編では丸腰状態を脱して、「どうやって戦場を切り抜けるのか」という改善策について記述をしたいと考えています。前編だけを読むと暗い気持ちになるだけなので、ぜひ、後編も併せてお読みください。嘆いて、愚痴っていてもどうにもなりません。今日一日を生き延び、一年を生き延び、長い教師人生を生き延びるために、一歩でも前へ進まねばなりません。



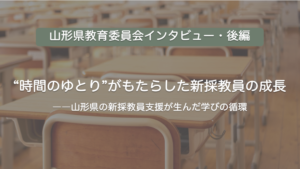






コメント