厳しい現状
前編では、学校の厳しい現状について述べました。「学校が戦場であると思える状態」を表す言葉(あくまで私のイメージです)をいくつか挙げました。
【①地雷原】【②見えない敵】【③巻き込まれ】【④支援の欠如】【⑤身内からの攻撃】【⑥無策】【⑦持続的な不条理】【⑧不休】
前編も是非ご参照ください。↓↓↓

地域差もあるでしょうし、学校による差もあるでしょう。同じ学校でもあるクラスは非常に苦しい状態になっているのに、あるクラスは平和で楽しく過ごせている場合もあります。埋まっている地雷の数や破壊力も違うし、敵の数や強さも違います。
戦場で生き残ることができるかどうかは、教師の実力によるところもありますが、運もあります。銃弾をよけることができたのに、そのせいで地雷を踏んでしまうということもあります。
「学校(学級)は戦場だ」と題して重たい内容を書き連ねているは、ネガティブなイメージを植え付けようとしているわけではありません。教員採用試験の倍率を下げたいわけでもありません。「学校が戦場であり、丸腰で地雷原を歩くのは危険である」という厳しい現状を認識するところからスタートする必要があると思ったからです。
本来は楽園?
中学校の1980年代の校内暴力、小学校の2000年代の学級崩壊を機に、学校や教師の権威が崩れ始め、同時に管理化が進み、過酷化が進みました。その様子については、EDUPEDIA内の下記↓↓↓リンク先等にも書かれていますので、ご参照ください。
学級崩壊という悪夢 ~いったい何なのか、どうやって立て直すのか | EDUPEDIA
校内暴力とは何だったのか ~1980年代教育暗黒史 | EDUPEDIA
ローカルルール(校則)を守らせるという困難 ~学校・教師と懲戒権 | EDUPEDIA
しかし、それ以前の学校はまあまあ牧歌的な楽園だったのです。明るいうちに退勤できましたし、保護者は教師を支えてくれていました。子供も素直で「とりあえず先生のいう事は聞く」という前提で物事が進みました。放課後に教師と子供がのんびりと野球やサッカーをする牧歌的な風景が見られました。
本来、学校や教室は幸せな場所であるべきですし、教師はとてもいい仕事のはずです。状態の悪い時には忘れがちですが、基本的に教師はいい仕事です。裁量権があり、ずっと上司に監視されているわけでもありません。言い方は悪いですが、しょせん相手は子供です。凝り固まった大人に比べれば可塑性があります。平均的な公務員の給与がもらえるし、共働きも可能です。
きちんと育てれば子供たちは成長します。成長する姿を見るのは楽しくて、こちらのモチベーションも上がります。子供のトラブルが減ってそれを指導する時間が減ります。子供が授業や学級経営で役立ってくれるし、保護者からのクレームも減ってきます。お互いを認め、優しさで成立するクラスを作ればそこはもう楽園です。
では厳しい現状の中でどうやって子供を成長させるのか。戦場を切り抜け、楽園を取り戻すことができるのか。一気に現状を変えてしまうような魔法の杖はないと考えた方がいいでしょう。何とか今をしのぎつつ、変えていくためにやるべきことを以下に提案します。
情報戦を戦い抜く ~知識と技術をアップデートする
戦場で丸腰。それを認識しているならば、せめて防弾盾と地雷探査機を携えていくという発想に至るでしょう。どこに地雷が埋まっているのかを確認しながら進みましょう。敵の数は?銃口はどちらに向けられている?敵はどんな兵器を持っている?この盾で大丈夫?
つまり、知識と技術をアップデートするのです。
① 法律やルール、慣例を知っておきましょう。
何が法律によって定められていて、何がローカルルールなのか。学校(校長)判断で「通知表を発行しない」という選択肢を選べることを知らない教員は少なくありません。また、10年前には多くの教員が「労働者には休憩時間があり、その時間は職場を離れることも可能」なことさえも忘れていました。情報不足に陥るのは危険です。
② 「学校の現状」や「教育の歴史」を知っておきましょう。
教育関係の書籍を読んでおきましょう。教育関係に限らなくてもいいので、最低、月に1冊ペースぐらいで本を読む習慣(余裕)は欲しいですね。私のおすすめですが、能澤氏の「学校2.0」は学校の成り立ちがよくわかる名著です。「茹でガエル」「二律背反」「無理ゲー」・・・といったワードが的を射ており、学校という戦場での自分達の立ち位置がどういう状況なのかが分かりやすく書かれています。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/03743955.77887bc8.09430918.da38491b/?me_id=1213310&item_id=21012611&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3696%2F9784908983696_1_38.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext) 先生2.0 日本型「新」学校教育をつくる [ 能澤 英樹 ]
先生2.0 日本型「新」学校教育をつくる [ 能澤 英樹 ]
下記↓↓↓の記事もご参照ください。
「先生2.0」(能澤英樹)【書籍紹介】 ~次世代の学校への提言と応援 | EDUPEDIA
③ 授業や学級経営で困った時には、ネットで検索してみましょう。
教育関係の役に立つ情報は2010年辺りからぐんと増えています。このエデュペディアにもたくさんの教育情報が蓄積されていますので、ぜひご活用ください。
戦術を考える
情報を得ながら、戦術(短期的な取り組み)を考えて組み立てましょう。場当たり的になってしまわないように、1年のスタートの時点で「現実的な目標」と「成功への見通し」がある状態を作りたいです。自分の得意分野を見つけ出して、それを武器にするのがいいでしょう。ウィークポイントを修正すると同時に、ストロングポイントを活かして「勝利のマイ方程式」を作り上げることが必要です。
上手くいかないと研修(授業研究)が足りないのかなと思いがちで、そこにリソースをつぎ込みがちですが、まず目の前の困難な案件に対応することを考えるべきでしょう。時間に追われ出すと授業研究よりも授業準備がおろそかになりがちです。授業準備さえできていないことは学校が戦場になってしまう一つの原因だと思います。授業準備をきちんとする(きちんとできる体制を作る)ことは優先順位が高いと思います。
優先順位を考えて、効き目が早くて確実な実践を選ぶ
子供たちは学校に勉強をしに来ているわけですから、学習面・生活面・精神面での成長が見られれば安定してきます。戦術を考えたらそれを使う優先順位を考えましょう。能力や時間が必要な実践(戦術)を目指すのも大事なことですが、まずは誰にでもできる実践を取り入れていくのが優先です。
下記リンク↓↓↓は、誰にでも比較的確実に効果を生み出すことができる実践について書かれた記事です。
誰にでも、簡単にでき、効果のある教育実践 ~教師の資質や負担に依存しない「点数を稼げる実践」を | EDUPEDIA
戦場に赴かされている自分たちが救われるべきなのはもちろんですが、同時に子供たちも守らなくてはなりません。そのためには、こちらを攻撃してくる子供たちを変え、味方に引き入れる必要があります。攻撃的になりやすいのは、学力不振の子供たちです。
学力保障 ~学校の荒れを防ぐための最優先事項 | EDUPEDIA
特に学年や学期のはじめはたとえ多忙であっても見通しを持って効果的な取り組みから手を付けることが必要です。
1年を見通した学級経営 ~戦略的学級経営 | EDUPEDIA
メンタルをケアする
休む・寝るは、もちろん大事です。退職・休職・休暇も視野に入れておくと気が楽です。
愚痴を聞いてくれる人や相談に乗ってくれる人も探しておきましょう。
誰も褒めてはくれませんから(笑)、時々は自分にご褒美をあげることも大事です。コンビニで高級スイーツやおいしいお酒を買って帰るのもいいと思います。長期休業中には思い切ってお金を使って旅行や食事をしましょう。
私は時には頭に来たり対立したりすることがあっても「本来、誰も敵ではないはず」「耐えて、耐えて、最後は勝ちに行く」と考えるようにしています。ポジティブ過ぎるでもなく、ネガティブ過ぎるでもなく。
見方・考え方を変える
今までの慣習やローカルルールに従って取り組んできたことが本当に必要なのかどうかを考えてみるのもよいかもしれません。
例えば、私は終わりの会をするのをやめました。ランドセルをロッカーから出して帰る準備して、係が前に出てきて・・・といった定番のパターンを取りやめました。授業が終わったらもうすぐに、「起立、気をつけ、さようなら」で帰らせてしまいます。とても爽やかです。浮いた時間で「プチ補習」をやらせることができます。
慣習やローカルルールに縛られず、自由な発想でやり方を変えてみることで、見えてくるものもあると思います。
戦略を考える
じっくりと戦略(長期的に大きな枠で捉えた取り組み)を練ることも大事です。「どのように教師としての自分を成長させていくのか」という個人のキャリアアップだけを考えるのではなく、勤務校の現状を変えるぐらいの勢いがあってもいいと思います。何なら国レベルの教育の改善を夢見て進むのもよいでしょう。同僚だけではなく、学校外の仲間とタッグを組めるようにコネクション作り、改革への地固めに努めるのもよいと思います。
この記事で大きな戦略に関することを述べ始めるととても長くなりそうなので、「団体戦」に関してだけ記述したいと思います。
団体戦
小学校は特に「学級王国」「個人商店」と揶揄されるように、チームで戦っているという意識が薄いです。自分さえ早く退勤できたらいいと「ひとり業務改善」に走ってしまう人もいます。とっても感じのいいクラスを作るのだけれど、どうしたらそうなるのかを教えてくれない先輩もいました。
そうではなく我々の仕事は「団体戦」であるという意識も高めたいです。1人で頑張るのは悪い事ではないですが、最終的には全体(学級 → 学年 → 学校 → 自分の自治体 → 教育全体)を良くするぐらいの野望があっていいと思います。
団体戦として大切なのは「仕事を合理化して増やさない」という前提を共有することです。団体戦は仕事が膨張する方向へと動きがちになります。あるSNSに
「サボる人より厄介なのは『無駄な仕事を作る人』です」
と書かれていました。名言です。職員室の中で「無駄な仕事を減らす」という意識を高め、「みんなで業務改善をしていこう」というムードを醸成することです。
もしあなたが若ければ頼りになる人を見つけておくとよいです。ノミニュケーションが激しすぎた時代はしんどかったですが、それなりに仲間ができました。「○○つながり」みたいなゆるいコミュニティーを作って定例でお茶会とかでもいいと思います。
もしあなたがベテランであれば、「自分はさんざん苦労してきたのだから若手も苦労すべきだ」という考えは捨てましょう。積極的に若手に話しかけてフラットな職場づくりに勤しむといいでしょう。誰かが空けた穴が広がり、戦線が崩壊するケースはままあります。「若手の育成しつつ学級崩壊を回避する」という難しいジョブをやり遂げてください。
いずれにしても、その時々の具体的で自分の身の丈に合った目標を持つことが大切です。高い目標を立てすぎてメンタルを壊してしまった教師もたくさん見てきました。時には逃げることも大切です。押したり引いたりしながら、長い目で見て平和を築くことができればよいと思います。
楽園にたどり着けるのか?
1年を通して、「子供・保護者・教師が、子供の成長を喜ぶ気持ちをどれだけ分かち合えるようになるのか」が大事なポイントだと思います。そのためには子供が「今日は何だか(成長して)楽しかったなあ」という思いを持って家に帰ることができる日をどれだけ増やしていけるのかが大切です。
楽園を取り戻そうとして働き方改革だけを強硬に進めると、子供に投資する時間が減ってしまい、結果的に子供の成長を妨げることになりかねません。成長しなければ子供は荒れてゆきます。しっかりと合理化と効率化を進めながら、子供に投資する時間と投資の質を確保できるように、バランスを考えることは必要だと思います。それはとても難しいですが、タフでクールにひとつずつ、課題の解決を見出していかねばなりません。
最後に、レイモンド・チャンドラー著「PLAY BACK」からの一節をお届けします。戦場を切り抜け、楽園へと辿りつくことができますように。
If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.
「タフでなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格がない」( 生島治郎訳)


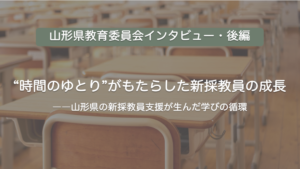






コメント