1 学校・学年で統一を
年度当初に学校全体・各学年で授業規則・生活規則を統一しておくと、浸透しやすくなります。指導の不一致を起こすと、子供はじわじわと規則を崩していきます。特に専科や教科担任制がある高学年においては要注意です。
ルールは作りだすときりがありません。学級として、学年として、学校として何でも「必ず」守らせると言っても無理があります。ミニマムとして、スタンダードとして、これだけは守らせたいルールを絞り込みましょう。学校や学年でどれを統一するのか、個人の教師としてどれを徹底させるのかを、子供の様子や自分の力量と合わせて、しっかりと検討をしてみてください。特に学校・学級が荒れている場合に統一して規則を示すと効果があります。
根気と気迫と学校・学年としてのチーム力が大切です。とは言うものの、ほとんどの校則や「学校・クラスのきまり」はローカルルールです。それをわきまえた上での指導をする必要があります。下記リンクをご参照ください。
ローカルルール(校則)を守らせるという困難 ~学校・教師と懲戒権 | EDUPEDIA
2 授業規則
◇授業中に指名されたら、ハイと返事をする。
◇指名されたら立って答える。
◇授業の開始と終わりのあいさつ。・・・・・「お願いします」「ありがとうございました」と、声を出させることもいいかもしれませんが、しっかり続かせることができないと、毎回叱るはめになっていやなムードになりかねないのでご注意を。
◇授業中は敬語や丁寧語で話す。・・・・・「授業は公式の場」として意識をさせるのもいいかもしれません。
◇手の挙げ方・・・・・「耳に腕がつくまで、まっすぐ挙げる」(低学年向き)「手(パー)が頭より上になるまで」(高学年向き)など、学年によって指示の出し方も様々だと思います。
◇大事な話をするときは、「先生の指示を顔を上げ、手を止めて聞きなさい。」・・・場合によっては鉛筆、消しゴムなどを置いて手に何も持たずに聞きなさい。それでも止まらないときは、「手を後ろに組んで聞きなさい」。
3 生活規則
◇持ち物・・・・・「学校に必要のないものは持ってこない」が基本ですが、いろいろと崩れてくるケースは多いです。妙な文房具が流行ったり、女子の筆箱が巨大化して中にペンが何本も入っていたり。
◇椅子、机を整頓する。
◇黒板は落書きをしない。
◇一日の終わり(清掃の後)には、掃除当番か係か、日直が必ず黒板を完璧にきれいにする。
◇一日の終わり(清掃の後)には、掃除当番か係か、日直が必ず机きれいに並べる。
◇雑巾を必ずきれいにかけておく。(枚数を決めておくのもいいですね。)
◇廊下を走らない。・・・・・走ったら教室に戻って1分間、自分の席でじっとしておくとかいう罰則もいいかもしれません。
◇教室を出るときに机の上をきれいにする。
◇教室を出るときに椅子を入れる。
◇靴を揃える。
◇○○君、○○さんづけで友達を呼び合う。
◇教師に対しては敬語あるいは丁寧語で話をさせる。
◇先生の机の上の物中の物、先生のものは触らない。
◇友達の机の上の物中の物、先生のものは触らない。
◇教室は並んで移動
◇暴言・嫌な言葉を慎む
をご参照ください。
◇掃除についても、ルールが大事です。
掃除を「子どもを伸ばす場」に (岡 篤先生)
をご参照ください。
できるようになったらほめる
上記の例はほんの一部です。ほんの一部でいいですから、根気よくできるまで指導を続けましょう。そして、出来なかったことができるようになったらほめてあげましょう。


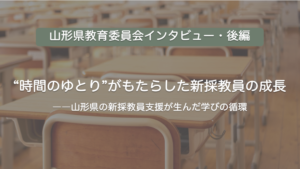

(後編)-1-300x169.png)
(後編)-300x169.png)


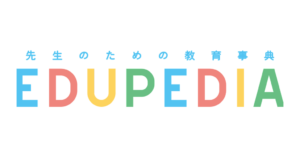
コメント