詰めること
音楽会の合奏の練習をしていました。4クラスでやっていましたが、どうも音にまとまりがない。パート別練習の時間が足りなかったかなと思っていたのですが、もう発表までに時間もない。そこで、リコーダーと鍵盤ハーモニカパートの子供だけを再度、引き受けて、パート別練習をして、できた子供から全体練習を行っている体育館に行って良いことにしました。とりあえず、一番難しい4小節だけを吹かせて、合格したら体育館に戻しました。全員を戻すことができるまでには全部で3時間が必要でした。本当にできていない子供がしかし、これをやったことで全体演奏がまとまって、2ランクぐらいのクオリティーアップを図ることができました。
私は、この過程を「詰める」と表現しています。教師にとっては「できるまでやらせる」子供にとっては「できるまでやる」、という意識を持って指導(学習)に当たることは非常に大切であると考えています。
リコーダーに限らず、何をやっても群衆の中に紛れて、落ちこぼれている子供がいます。そこを流してそのまま先に進むことを繰り返すと、どんどん落ちこぼれが増え、悪化してゆきます。落ちこぼれることに対する免疫ができ、「まあ、いいや」「どうせ自分は・・・」という気分になり、それが学級集団のムードとなってしまうと重たいクラス・学年へと落ちてゆきます。
教師の多忙化が進むとともに、下校時の安心安全が重視されて放課後の居残り勉強がしにくくなってきています。個々の子供に向き合う時間はここ数年がかなり取りにくくなっています。「主体的・対話的で深い学び」を実現するために教科書はやたらと子供に考えさせ話させる内容になっていますが、習熟を図る時間とのバランスに欠けてしまっています。教師は考えさせて話させることに翻弄されてしまいます。「考えられない・話せない・知識理解技術が向上しない」といった子供にとっては3重苦、4重苦の時間になってしまっていると思います
違いが分からない
中国の故事で「馬と鹿の区別がつかない」というところから「馬鹿」という言葉が出来たらしいです(指鹿為馬)。あまり関係ないですが、米津さんです↓↓↓。
馬鹿という言葉はあまりよくないですが、学力が低い子供を見ていると、確かに「違いが分からない」ことがネックになっているようです。先述したリコーダーでは、大勢で合奏している中で、自分が違う音、違うタイミングで音を出していることに気が付いていません。話し合いの授業で言えば、自分が今の話題を理解してるのか、話題に沿って話せているのかに気が付いていません。「分かっていないことに気づいていない」「何が分かっていないのかが、分からない」まま、なんとなく次に進んでしまうと、どんどん落ちこぼれていきます。正解と不正解の違いが認識できないと、学力はなかなか向上しません。プリントやテストに×がついても、特に何も考えずに流してしまう子供は多いです。違いに気が付いて修正できないと成長ができないため、成就感がなく、学校に来ること、教室にいることの意味を見失いがちになってゆきます。
教師も同様で、「できていない子供がいることが分からない」のは困ります。落ちこぼしをどんどん生み出しているのに、自分はできていると思っている教師は少なくありません。自戒を込めて、本当に誠実に仕事ができているのかどうかを確かめる必要があると思います。
そのためには、データをとる習慣をつける必要があります。下記の記事をご参照ください。
詰めるには
・
放課後や長期休業中に補習をさせることが難しくなってきている今、どうやって落ちこぼしに学力をつけるのかについて、しっかりと考える必要があると思います。学期や学年の終わりに習熟度別学習を取り入れるパターンはよく見られますが、そうではなくもっと短いスパンで習熟度別学習の機会を設けた方がよいかもしれません。日々の隙間時間を見つけて、少人数を残して学習させる機会は必要です。下↓↓↓のリンク先には、学力保障の大切さがまとめられているので、是非ご参照ください。
学力保障 ~学校の荒れを防ぐための最優先事項 | EDUPEDIA
私は授業時間の最後あたりで「できるまでやらせる」ようにする機会を設けます。あるいは、終礼の後に「できたらバイバイ」という時間を作り、「できるまでやらせる」ようにします。「できるまでやります」という宣言をすれば、子供は自分が何ができていないのか、自分で気づかざるを得なくなります。教師が示した合格ラインと、自分の今の力との違いが分からないと次には進めません。先生ができるまで許してくれないから、なんとなく流すことが不可能になり、考えるスイッチを入れざるを得なくなります。「やりきる覚悟」もできます。そこにたどり着けるように、本サイトでは以下のような記事も掲載していますので、是非ご参照ください。
もちろん、何でもかんでも「できるまでやらせる」わけではなく、教師は個々の子供の実力と課題をしっかりと見計らいながらサポートしていく必要があります。
「子ども・保護者・教師」喜びを共有する
どうすればスモールステップを作り出し、詰めることができるのか。その方法とツールがあればそれ程しんどくなく力がつくので、お残りをさせても意外と子どもは喜びます。指導に美しいスモールステップが備わっていれば、教師は「できたじゃない、すごいね」「先生もうれしいよ」とプラスの言葉をかけてあげればいいのです。最初は「できるまでやらさせる」ことを嫌がり、癇癪を起したり涙ぐんだりする子供もいますが、教師側の意図が分かっていればだんだん「できる喜び」の方がまさってきます。厳しさと愛情をもって接してあげてください。
データをきちんと取っていれば、成長の様子を子どもに示し、保護者にも示すことができます。「子ども・保護者・教師」が、子どもの成長の喜びを共有することは、学校が活力を取り戻すためのたいへん大事な要素です。
成功体験が積みあがってゆけば、やり切ることに楽しさも覚えるようになってきます。そして、本来あるべき姿「自学自習」ができるようになると最高ですね。
①自分で自分の間違い(課題)を発見し、
②その解決方法を自分で見出し、
③自分で自分を「詰める」
・・・という循環で自分を磨くことができるようになる所まで、教師は上手に子供たちをサポートする必要があると思います。学力を保障するという教師がしなければならない仕事を誠実に履行することによって、個々の子供・保護者との信頼関係が築かれ、ひいてはクラスが安心して過ごすことのできる場所になってゆきます。




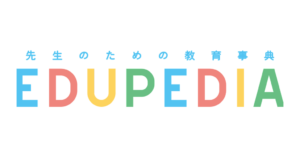




コメント