ついつい
下に挙げた、各項目、ついつい自分はやってしまっていませんか。言ってしまっていませんか。教師も一人間であり、毎日、完ぺきな言動で通すことは難しいでしょう。しかし、何も感じずに1日を過ごすのと、「やってしまった」「言ってしまった」と自分で認識し、少し修正を加えることができるかどうかは雲泥の差です。私たち教師の仕事は日々が勝負、その時々が勝負です。自分の個性、持ち味を生かしながらも、子どもたちに、自分に負けずにがんばって教師として日々に打ち勝っていきましょう。できれば褒めて褒めて、WIN×WINの毎日を過ごしたいですね。
下の各項目は反対のことを言っているように思えるかもしれません。各項目の中に逆接も多いです。それは、教師という仕事の難しさを示していると思います。
ローカルルール(校則)を守らせるという困難 ~学校・教師と懲戒権 | EDUPEDIA
正解はないのかも知れません。子どもたちをよく観察しながら、上手にバランスを取りながらやっていくほかはないのです。
1 流してしまう
子どもは生活場面、授業場面で頻繁に間違った行動をとります。そういうものです。荒れている学級であれば、絶え間なく間違った行動をとります。全てのことを流さず咎めず、叱ってしまうことはできないし、そんなことをしていたら子どもたちも息が詰まってしまいます。
ただし、集団をまとめるためには絶対に流せない場面はあります。「ここは絶対」と自分で決めた範囲に対しては絶対に流さない場面を作ることも必要です。例えば、
・差別的な発言を許さない
・指導不服従・教師反抗を許さない
・教室環境を整える
等々、これだけは年間を通して徹底的にやるのだということを自分で決めておいて、そこは絶対にスルーしない意識でやり通す(やり切る)ことは大事です。
2 流してしまう2
「絶対に○○をやる」と言っておいて、結局やらないのはいけません。例えば「掃除の時間は絶対にしゃべるな」と指示しておいて、子どもたちはしゃべっている。それを先生が気づいていてなおしゃべっていれば、「しゃべっていてもかまわない」ということになってしまいます。ひいては先生が「絶対」と言っても聞かなくてもいいということになってしまい、以降の指示が流されてしまいます。それなら言わない方がましです。
例えば「そこ、しゃべりません。」と注意したのにおしゃべりが止まっていないのを放置している状況も拙いです。教師が「言ってみた」程度の注意であったことを子どもたちは敏感に嗅ぎ取ります。子どもたちの理解は「先生、ああ言っているけどやり切るつもりはないんだ」となり、行動を改める必要はないと考えるようになります。それが慢性化してゆくと他の指示もどんどんきかなくなってゆきます。
3 流してしまう3(見過ごしてしまう)
子どもたちがちょっとした問題行動を起こしている時、気が付いているのに見過ごしてしまう場合はありませんか。「掃除をいい加減にして終わらせる」「授業中に体が横を向いている」「廊下を走っている」・・・・ちょっとしたことでも見過ごしていると、それが大きな穴となり、やがては学級を学年を飲み込む崩壊の始まりとなるケースがあります。見て見ぬふりをしてある程度泳がせてからピシャッと手を打つという方法もあると思いますが、基本的には気が付いたその時・その場でしっかりと注意をすることが大切です。
4 怒ってしまう
自分のイライラを子どもにぶつけて、恐怖政治を行ってしまっていませんか。恐怖政治を行ってしまうと、子どもたちの間にも恐怖政治的な関係が生まれてしまいます。家庭での不満を持ち込んで、子どもに朝一番から「今日の先生、機嫌が悪いなあ」と思わせてしまうようなのは、どうかと思います。1~3で流すのはいけないと書いていながら、怒りっぱなしもいけません。
叱ることは難しい ~子どもを叱る基準や叱り方 | EDUPEDIA
怒鳴る(脅す)は三流? ~「怒鳴る」と「叱る」の違い | EDUPEDIA
をご参照ください。
感情を露わにして怒ることも時には必要でしょうが、できれば冷静に叱ることができるようにならなければいけません。
5 脅してしまう
脅しの文句を使っていませんか? 使っている教師は多いと思います。「~しないと~にするよ」「~していると~にするよ」という文脈で、子どもたちにプレッシャーをかけます。脅さざるを得ない場面は確かにありますし、私も脅し文句を使うことはあります。しかし、脅して何かをさせる(何かをさせない)のは二流のやり方であって、決して良い方法ではありません。また、頻繁に脅しを使って育てられてきた子どもは、脅しに対する耐性がついてしまい、少々のことではいうことを聞かなくなってしまう場合もあります。
脅し文句を使っているときは、教師自身が「今、自分は二流の脅しをしているんだ」という自覚がないといけません。そして、脅さなくても子どもをやる気にさせ、上手に子どもをほめながら育てられる教師になれるように努めましょう。
6 いつも、子どもに顔色を窺わせる(あるいはその逆)
上記、怒る教師、脅す教師等、感情の起伏が激しい教師はいつも子どもが顔色を窺うようになります。それはあまり、いいことではありません。子どもたちは「忖度のコツ」を学ぶために学校に来ているわけではないですから。
逆に全く教師の意向を汲もうとしない子どもたちにしてしまうのもいかがなものかと思います。教師の「想い」は適度に子どもに伝わるようにしたいですね。
7 安易にできない約束をする
リップサービスをやってしまいがちですね。子どもに期待をさせておいて、はしごを外すようなまねは、やめましょう。子どもたちもがっかりします。
8 安易に強い言葉を使ってしまう
「世界一のクラスにしよう」などと、強い言葉で子どもたちを鼓舞していませんでしょうか。あまり安易に強い言葉を使っていると、子どもたちも白けてしまいます。ハードルを上げてしまうことで結局できない目標であることがわかってきたら、残念な気持ちが広がります。教師としての自分の実力、子どもたちの実態を考えて、身の丈に合った言葉を選ぶようにしましょう。
9 教師間の不仲を感じ取らせてしまう
子どもたちに仲よくする事を要求している以上は、子どもたちの前では、たとえ不仲であっても、仲が良いように演技をするべきです。それも仕事です。
衝突をするなら職員室で、アサーティブに。
10 教師間の上下関係を感じ取らせてしまう
教師が子どもや保護者からの信頼を勝ち取ることが難しくなってきています。新任の教師は特に、昔のような「若さ」だけを売りにしてやっていくことが難しい時代です。
こんな状況で先輩教員が若い教員を軽くあしらったり、パシリに使っていたりすると、子どもたちは敏感に教員の中の上下関係を感じ取ってしまいます。
できれば、若い教師をヨイショして、子どもたちに「うちの担任はベテランの先生とも対等に渡り合っているんだ」と思わせるような場をわざと持って、演じましょう。若い教師と子どもの前で話すときには、敬語を使いましょう。
11 できない子どもを見捨てる
クラスの中には何人かの「しんどい子ども」がいます。その子たちと関わっていれば、授業は進まなくなってしまい、時間がいくらあっても足らないという場合があるでしょう。だから、いつまでもその子に付き合うことはできません。その代わりに、「あなたたちのことは見捨てていないよ」というメッセージ(言葉・態度)は伝わるようにしてあげてください。それは他の子どもたちにも伝わります。
できる子供を優先する ~学力保障のために | EDUPEDIA
学力保障 ~学校の荒れを防ぐための最優先事項 | EDUPEDIA
も、ご参照ください。
12 あきらめる
上記の「できない子どもを見捨てる」と同様です。全てのことを何が何でもあきらめないというのは無理だと思います。「あきらめが肝心」という言葉もあることですし。それでも、若い(幼い)子どもたちの前で、先生はあきらめないんだという姿勢を示すべきです。「この先生、言葉ではきれいごとを言うけれど、すぐにあきらめるなあ」と思われてしまっては、子どもたちにもだんだんと頑張りがきかなくなってきます。
13 謝らない
教師という立場上、子どもたちに謝らせることは多いかもしれません。でも、時々自分もミスをしてしまうことがあります。そんな時には潔く謝りましょう。相手が子どもだと思ってうまくごまかそうとすると、子どもたちからの信用を失ってしまう恐れがあります。
14 時間に遅れる
多忙化が進み、休み時間にも職員室に戻って少しでもやらなくてはならない仕事を抱えている時があります。しかし、授業開始時間等にたびたび遅れるようであれば学級の状態は確実に悪くなっていきます。それでも遅れることはあるとは思いますので、先生が遅れた場合に何をしておくかを指示しておくのも大事だと思います。
15 朝令暮改
前言を翻さざるを得ない場合もあります。そういう場合は、素直に子どもに謝りましょう。ただし、あまりにこれが続くと、子どもたちはうんざりしてきて、教師の言うことを聞かなくなります。
16 ぶれる
(朝令暮改とほぼ同じです。)教職だけではなく全ての仕事に言えることです。臨機応変は必要ですが、ぶれてはいけません。一年を通して、教師人生を通して、ぶれない心を持っておくことは大事です。
17 アップデートしない
ぶれてはいけない一方で、考えを改めずに自分をアップデートしない教師もまた問題です。時代も事態も変わっているのに、自分の考えや自分の過去の言動に拘ってしまって柔軟性を欠く態度をとっていては信用を失います。
18 家庭の事情を加味しない
10年前なら、「家から新聞紙を持ってきなさい」という指示は通用しましたが、今は新聞をとっていない家庭が増えているので、この指示は出すべきではありません。各家庭に事情があり、それは子どものせいではない場合があります。家庭の事情を加味して、指示を出さないとしんどい子どもがいることを忘れてはいけません。二分の一成人式で、自分史を振り返らせるような課題も、家庭に事情がある子どもが多くなった昨今、もう時代的にはそぐわないと思います。様々な背景を持っている子どもに寄り添う気持ちを忘れないようにしましょう。
19 目をそらす
性格的に人の目を見るのがあまり好きではない教師はいると思います。人の目をじっと見過ぎるのもいけませんが、目をそらすこと・目を伏せることが多いと、子どもの勢いに負けてしまいます。この職業に目力(めぢから)の強さは必要です。もちろん、優しい方の目力も必要です。
20 比べてしまう
「去年の6年生は云々」「去年のクラスは云々」「前の学校では云々」と、過去のクラスを引き合いに出して、今年のクラスを悪く言うような言い方はやめておいた方がいいです。後になって過去をすっかり超えるようなクラスを作る自信があるのなら引き合いに出すのも悪くないと思いますが・・・
21 褒め切らない
褒めることは大事です。褒めていたのに、何か「チクリ」を追加していませんか。褒める時はできるだけ褒め切った用がいいです。
○ 「この絵、今年のあなたの最高傑作だと思うよ。」
× 「この絵、今年のあなたの最高傑作だと思うよ。背景の塗り方がちょっと雑だけれど。」
22 同調圧力的学級経営
教員が同調圧力で学級集団をコントロールすることの是非については、別に下記の記事で詳細を述べてみます。是非ご参照ください。子どもに忖度することばかりを覚えさせてしまうと、クラスが病んできます。同調圧力が強すぎるのは、いかがなものかと・・・
この記事は2016年8月27日に書かれました。(最終更新日:2026年1月13日)


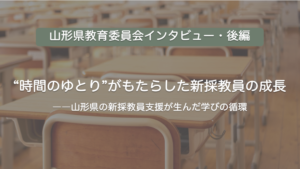

(後編)-1-300x169.png)
(後編)-300x169.png)

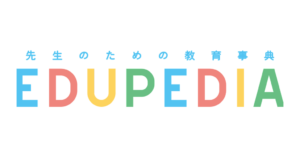
コメント
コメント一覧 (2件)
そうなんだ~
ありがとうございます